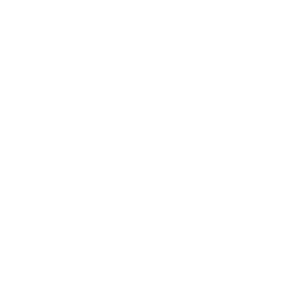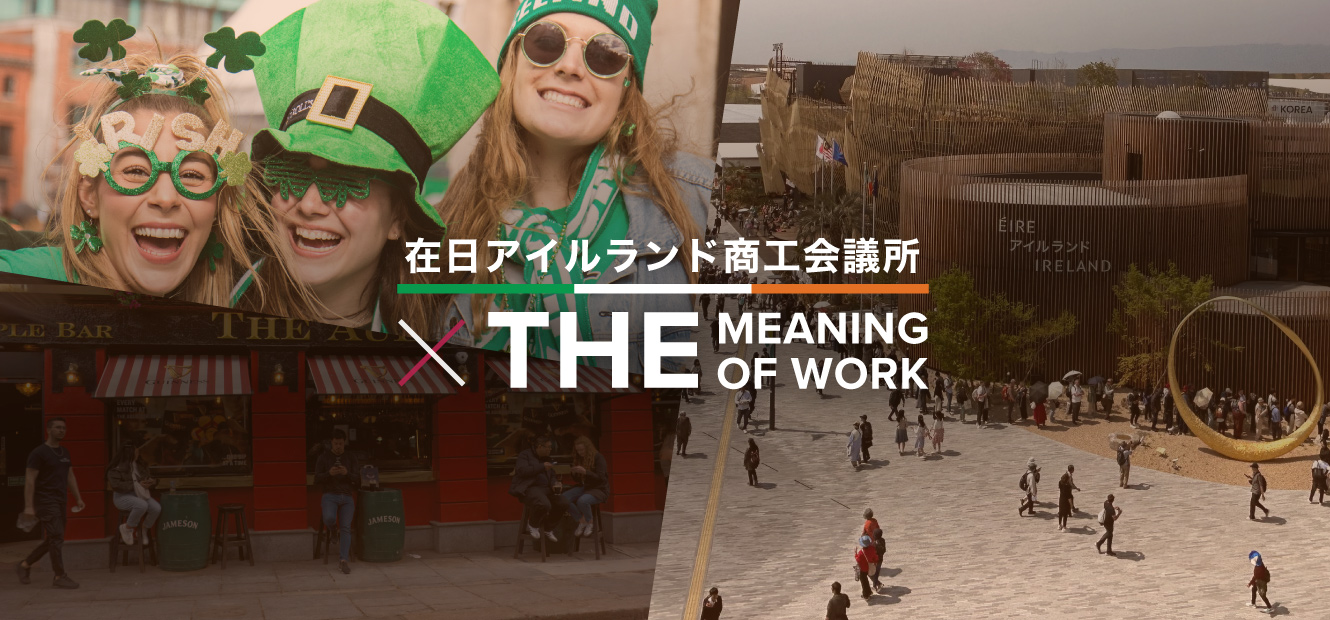伝統と革新の京都で“問い”から始まる共創の場づくりを。
-

平野 哲広AKIHIRO HIRANO
京都信用金庫 QUESTION館長大阪生まれ、京都育ち。2001年、京都信用金庫入庫。営業店からキャリアをスタートし、本部での融資・審査業務、連携支援部での産学連携・創業支援プロジェクト、採用担当、新規店舗開発などに従事。その後、企業成長推進部で部長を務め、創業支援やビジネスマッチング、商談会の企画運営、クラウドファンディングの組成、補助金申請支援などの本業支援業務を統括。2024年4月に「QUESTION」の館長に就任し、さまざまなステークホルダーとともに、勉強会の開催やコミュニティ形成による地域活性化を牽引。地元・伏見の名酒をこよなく愛する。
-

林 幸弘YUKIHIRO HAYASHI
株式会社リンクアンドモチベーション
モチベーションエンジニアリング研究所 上席研究員
「THE MEANING OF WORK」編集長
早稲田大学政治経済学部卒業。2004年、(株)リンクアンドモチベーション入社。組織変革コンサルティングに従事。早稲田大学トランスナショナルHRM研究所の招聘研究員として、日本で働く外国籍従業員のエンゲージメントやマネジメントなどについて研究。現在は、リンクアンドモチベーション内のR&Dに従事。経営と現場をつなぐ「知の創造」を行い、世の中に新しい文脈づくりを模索している。
金融機関の使命は、お金を貸すだけではなくなった。創業支援、ビジネスマッチング、クラウドファンディング、補助金活用……。今や、金融機関は顧客と共に伴走し、変化を実現していく「コミュニティ・バンク」としての役割が求められている。京都信用金庫が運営する「QUESTION」は、多くの人が問いを持ち寄る共創の場だ。20年以上にわたって、地域の企業に寄り添ってきた館長・平野哲広氏との対話から、地域共創と新たな仕事の形を模索する。
日本で初めての「コミュニティ・バンク」

 |
林
まずは、平野さんの原点から伺っていきたいと思います。京都信用金庫に入庫された決め手は何だったのでしょうか。 |
 |
平野
私が入庫した2001年は、就職氷河期の真っ只中でした。当初はメーカー志望だったのですが、なかなか思うようにいかなくて。金融機関に目を向け始めたのは、友人からの薦めがきっかけでした。「金融機関顔だから、受けてみたらいい」なんて言われましてね(笑)。それで何となく気になって、調べているうちに金融っておもしろいなと思い始めたんです。命の次に大事なお金に携わる責任があること。どの金融機関のサービスも同じお金に関わるものなので、人で勝負できること。そして、自らが関わった仕事が建物や商品として残ること。私は大阪生まれの京都育ちですから、自分を育んでくれた地域の役に立てることに何より魅力を感じたんです。 |
 |
林
生まれ育った地に恩返しをする。そうした意味で、京都信用金庫という存在はこれ以上ない場所かもしれませんね。 |
 |
平野
そうですね。信用金庫は、信用金庫法で営業できるエリアや取引できる企業規模が決まっているんです。地銀が東京・海外への開拓が可能であるのに対して、信用金庫は認可が下りた地域でしか営業することができません。私たちで言うと、京都・滋賀・大阪ですね。地域が持続的に発展しないと未来がない。だからこそ、地域企業のお客さまと共に歩み、当事者としてその地域の発展に取り組んでいけるのだと思います。 |
 |
林
京都信用金庫は、1971年に日本の金融機関で初めて「コミュニティ・バンク」を宣言し、また、創立100周年を迎えた2023年にはブランドネーム「コミュニティ・バンク京信」を制定しました。地域社会の一員としての「コミュニティ・バンク」という考え方は、すべての職員のよりどころになっているのでしょうか。 |
 |
平野
はい。京都信用金庫では従前から、「コミュニティ・バンク」という考え方を大切にしてきました。当時の理事長である榊田喜四夫の時代に『コミュニティ・バンク論:地域社会との融合をもとめて』という書籍を出版していて、その中で提唱している「資金供給だけでなく、情報・知恵・人・システムを提供する」という考え方は、私たちの大きな指針となっています。金融機関の仕事は、お金を貸すだけじゃない。お客さまのビジネス分野を推測し、一緒に商品を開発していくといったことも記されていましたので、ずいぶん先を見据えていたのだと驚かされます。 |
 |
林
1970年代の京都には、先見の明があるリーダーがたくさん活躍していました。京都を支える信用金庫でもそれは同じだったのですね。SINIC(サイニック)理論を提唱した立石一真さんもその時代でしたね。SINIC理論において、今は最適化社会から自律社会へと移行するタイミングにあるといわれています。巨大なピラミッド型組織ではなく、小さな組織がつながっていく、ネットワーク型の社会になっていくと。 |
 |
平野
現在の理事長もそうした状況を理解していると思います。小さなピラミッドの連なりを意識し、風通しの良い対話型の経営を実践していますから。トップの役員と職員が年1回対話する「ダイアログ」によって、意見を吸い上げ、迅速に経営に反映させる体制を整えていますし、役員と部長による経営戦略会議は、毎朝行われています。 |
“問い”が集まる革新的な共創施設

 |
林
「コミュニティ・バンク」である京都信用金庫を象徴する存在、それが「QUESTION」であるように感じます。この施設はどのようなものなのでしょうか。 |
 |
平野
「QUESTION」は、一人では解決できない”問い”を持ち寄り、それに対してさまざまな分野の人が集まり、みんなで答えを探しに行く共創施設として、2020年の11月にオープンしました。世界のクリエイティブ都市には同様の共創施設があり、社会課題の解決に一役買っているんです。京都市役所の目の前という好立地を活かして、これまでにないコラボレーションを生み出しています。 |
 |
林
“問い”を持つ人々が集い、まちを変えていく。おもしろいコンセプトですね。 |
 |
平野
オープンにあたって、創設時のプロジェクトメンバーが集い、コンセプトを練り上げました。何かが起きるきっかけは、いつも”問い”です。それぞれに抱いている「?」を持ち寄り、対話し、気づき、共感する。そうしたプロセスを経て、新たな価値が生まれます。「QUESTION」には人々が集う対話の場があり、サポート役のコミュニティマネージャーがいて、地域のネットワークを活かし、多様なジャンルの先駆者と力を合わせて課題解決にあたっていきます。ここでの対話を通じて、一人でも多くの人に新しい気づきや出会いを体験していただき、地域全体をクリエイティブでイノベーションが起こりやすい場所に変えていきたいと考えているんです。 |
 |
林
京都市役所前に位置する「QUESTION」ですが、多くの人々が集う共創の場らしく、おしゃれで開放的な空間になっていますね。どのような施設があるか教えていただけますか。 |
 |
平野
「QUESTION」の1階にある「CAFE BAR HIROBA」は、休憩したり、待ち合わせに利用したり、誰もがゆったりと自由に過ごせる空間です。カフェメニューや日替わりスイーツが充実していますし、夜のバーでは懇親会やイベントも開催できます。2階から8階のスペースには、会員向けのコワーキングスペースやセミナールームに加え、学生のための場所として、学生と企業の有機的なつながりをサポートするフロアも設けています。そのほか、最上階には、コミュニティキッチンなどユニークな施設もありますよ。 |

 |
林
キッチンがあるのは驚きですね。 |
 |
平野
食事をするのって、家庭か飲食店がほとんどですよね。その在り方に一石を投じようと、地域・家族・会社、あらゆるコミュニティが利用できるキッチンをつくりました。食べるだけでなく、みんなでつくり、みんなが交ざり合う、“食”を通じたコミュニケーションを実現しようというのが目的です。会社の懇親会や、飲食業を始める方のトライアルキッチンなど、キッチンを活かしたイベント・会合に活用していただいています。 |
 |
林
おもしろいですね。通常では経験できない、深いコミュニケーションがとれそうです。 |
 |
平野
そうなんです。京都信用金庫でも、支店長が一堂に会する会議でこのキッチンを活用しました。カレーライスと餃子をつくり、一緒に食べる。支店長同士の関係をより深めることができたと思っています。料理なんてしたこともないオジさんたちが奥様から借りてきたであろうエプロンをつけて悪戦苦闘している光景は、かなりインパクトがありましたよ(笑)。 |
共創のエコシステムが地域を革新する起点に

 |
林
「QUESTION」に集う”問い”には、どのようなトレンドがあるのでしょうか。 |
 |
平野
持ち寄られる”問い”は本当に多様で、人それぞれというのが現実ですね。かつては地域のコミュニティをどう育み、どう良くしていくかが中心でしたが、最近ではAIの活用やDXなどテーマが幅広くなっています。館長を務める中で私が強く感じるのは、みんなで一緒になって考えたことを世の中に対するメッセージとして提案する機会が増えてきたことですね。その象徴的な事例が、2024年に開催したトークセッションです。京都市長とコミュニティナース活動を推進する経営者、そして京都信用金庫の理事長が「2050年の京都コミュニティの未来」というテーマでトークセッションを行ったのですが、この対話を受けて、参加同士でディスカッションを行いました。また、京都市長と龍谷大学副学長、そして京都信用金庫の理事長に学生を交えたタウンミーティングが開かれるなど、世の中に波及していくきっかけをつくることができました。こうした広がりが生まれたのは、近隣にある京都市役所との関係性が深まったことが大きいと考えています。 |
 |
林
”問い”から生まれた対話が社会へのメッセージとして発信される。共創の場である「QUESTION」の意義を強く感じさせられます。 |
 |
平野
そうであれば、うれしいですね。もう一つ、大きな手応えを感じている点としては、「QUESTION」がいろいろな枠を飛び越えていくきっかけになってくれていることですね。2025年に開催された「デザイン思考を学ぶワークショップ」では、地域の中小企業をはじめ、オムロン(株)、(株)島津製作所、(株)村田製作所、ローム(株)といった大手企業からの参加も目立ちましたし、小・中・高校・大学それぞれの学校の先生と教育委員会が未来の教育や、産業界が求める人材とのギャップを意見し合うというイベントも開催されています。さらには、西陣織の製作過程で生じる産業廃棄(=産廃)素材をハンドメイドアクセサリーに再利用し、産廃を減らす「sampai(サンパイ)」というアップサイクルブランドが誕生するなど、ここから新たな価値創造の取り組みも生まれています。 |
 |
林
「QUESTION」が共創のエコシステムを生む土台になっているのですね。 |
 |
平野
その媒介になっているのがコミュニティマネージャーの存在です。対話の中で「この人が抱えている課題とあの企業の技術が合わさったらおもしろいだろうな」「あの人に聞いたらこの分野の情報を持っているだろうな」といったアイデアが浮かび、私たちが持つリソースを有効に活かすことができているんです。 |
伝統と革新のまちで変化に伴走していく

 |
林
100年を超える歴史を持ちながらも、イノベーティブな企業が多い。京都というまちが持つ特長が「QUESTION」の後押しになっているようにも感じます。 |
 |
平野
確かに京都は、伝統と革新が混じり合う地域ですよね。京都信用金庫は2023年に創立100周年を迎えましたが、「ようやく100年企業の仲間入りができたね」という感覚でしたから。そんなまちは他にはあまりないのではないでしょうか。特筆すべきは、時代の変化に対応し、変わり続けている企業が多いこと。100年続いているのは、変わり続けているから。「問い続ける力」が京都の企業の強みだと思っています。 |
 |
林
変わらないのではなく、問い続け、変わり続ける。だから、続いていく。私自身、京都に拠点を置く多くの企業と関わる中で、強く感じていることでもあります。 |
 |
平野
長期の視点を大事にしているんですよね。目先の利益ではなく、その先を見ている気がします。京都信用金庫でも、他の金融機関に先駆け、2017年に売上目標や営業ノルマを撤廃しました。半年ごとに数字で評価される形だと、どうしても目先の目標を追って視野が狭くなってしまいます。ノルマ廃止により、営業担当は10年先の未来を見据えて仕事ができるようになりました。金融という枠を超え、まちの未来を話していくための転機だったと言えるでしょうね。 |
 |
林
社会的カテゴリー理論では、概念で自分をくくってしまうと常識の枠から抜け出せないデメリットがあるとされます。「お金を貸すことが金融機関の仕事だ」「目標を達成することが大事だ」と思い込むと、アンテナが機能しなくなってしまう。難しいですが、そうした考え方・ものの見方を解放していくことは、とても大事ですね。 |
 |
平野
「QUESTION」で働くスタッフが金融の枠を超え、好奇心を持って、自ら未知の領域を学びに行く。自分にはない知識を持った人に出会いに行く。そうしなければ、「QUESTION」の良さは出てこないと思っています。まずは、私たちがこのチャレンジを楽しみ、生き生きと働けなければ、地域の未来に貢献することなどできませんから。 |
 |
林
”問い”を抱き、それを解決するために前向きに動く。それは、現代を生きる私たちにとっても大切なことであるように思えます。些細な違和感を気にすることもなく、関心が持てないから、面倒だから、社会ってこういうものだからと諦めていては、”問い”そのものが立ちません。どのようなマインドセットで日々を過ごせば、良質な”問い”を抱き、行動できるようになると思われますか。 |
 |
平野
「当たり前とされていることを当たり前だと思わないこと」が大事だと思います。私自身が「仕事で楽をしたい」「手間をかけたくない」というタイプなので、「なぜ、それをせなあかんのやろ」という疑問を常に持ち続けているんです(笑)。ただ、常識の檻を破るのはそれほど簡単なことではありません。気づけるはずだったのに、気づいていなかった。そういう”問い”も多いですよね。大切なのは、リアリティを持てるかどうか。だからこそ、京都信用金庫では、答えがないことに意見を出し合う時間を大切にしています。幹部だけでなく、職員みんなで抽象的なテーマで議論する。そうすることで、「当たり前ではなかったこと」に気づき、合意形成も図れるようになるんです。金融機関はルーティンの仕事も多いですから、放っておいたら考えずに仕事していることも多いんですよね。 |
まずは気軽に“問い”が交じわる場へ

 |
林
「QUESTION」での活動を通じて、どのような瞬間に喜びを感じていますか。 |
 |
平野
やはり、さまざまな人が集まり、寄せられた”問い”から、解決策を導き出せた瞬間ですね。特に忘れられないのが、「まちの同期会」を開催したことです。きっかけは、地域を支える経営者6名による意見交換会で、「自社内での交流だけでは視野が狭くなってしまう」という意見が多く出たこと。同時に、私たちも地域の中小企業の離職率が高いことに課題を感じていて、そこに歳の近い人が社内におらず、相談できる相手がいないことが大きな要因になっているという仮説を立てていたんです。そこで、まちを1つの企業に見立てて、多様な企業から若手が集まる交流会を開催しようと考えました。 |
 |
林
まちを1つの会社に見立てる。地域発展の伴走者だからこそのアイデアですね。 |
 |
平野
この交流会は、「QUESTION」のコミュニティキッチンで開催しました。システム系の会社から、かやぶき屋根をふく会社まで、バラエティ豊かな方々が集まってくださいました。同じ趣味を持つ人を同じチームにして、タコスをつくる。参加者たちは互いの共通点を探りながら、料理を楽しみ、有意義なコミュニケーションを交わしました。交流会が終了した後も、参加者たちはSNSでつながり、さらに関係を深めているようですよ。 |
 |
林
地域企業の経営者から出た”問い”と、職員の皆さんが抱いていた”問い”が化学反応を起こしたわけですね。 |
 |
平野
ほかにも、いい意味で想定外の収穫もありました。大手企業から参加される人も多かったのですが、彼らは自身の企業全体では同期はいても、配属された営業所には同期がおらず、同様の孤独を感じていたのだそうです。 |
 |
林
共創の輪が広がっているのですね。「QUESTION」を訪問される方々のように、「今のままでいいのか」と考えながらも、行き場のないエネルギーを持っている人は多いと思います。館長として、どのような人たちに利用していただきたいですか。 |
 |
平野
いろいろな方に活用していただきたいというのが本音です。「これがしたいけど、どうしたらいいかわからない」「こういうことを変えないとダメだよね」。そんな疑問を持っているが、周囲に共感してくれる人がいなかったり、いろいろな人や知識に出会いたい、ほかではできない体験をしたいと思っていたり……そんな人たちにとっては、とても魅力的な場所だと思います。まずは気軽に、誰でも利用できるカフェバーに足を運んでみてください。おいしいケーキと愛想のいいスタッフが待っていますよ(笑)。 |