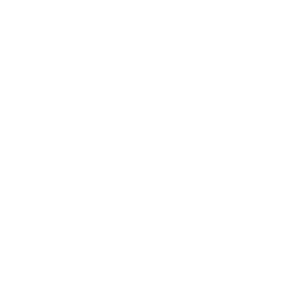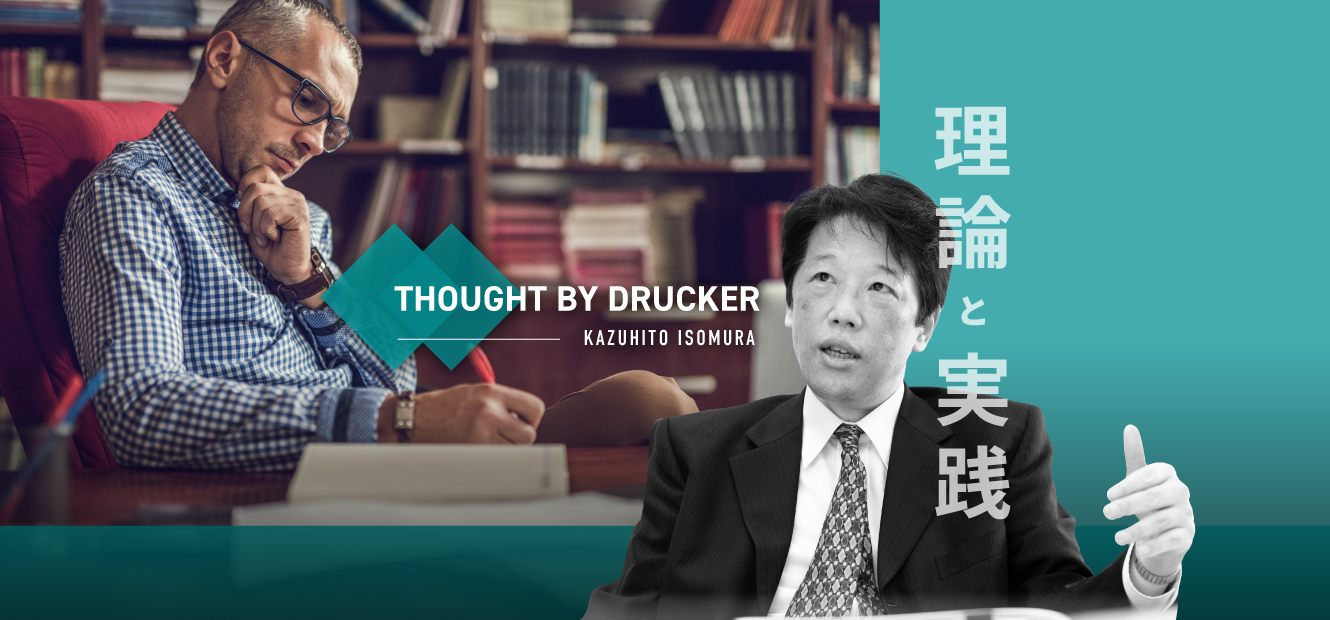AOMに参加する意義と価値を検討する
-

磯村 和人Kazuhito Isomura
中央大学 理工学部ビジネスデータサイエンス学科教授京都大学経済学部卒業、京都大学経済学研究科修士課程修了、京都大学経済学研究科博士課程単位取得退学、京都大学博士(経済学)。主著に、Chester I. Barnard: Innovator of Organization Theory(Springer, 2023年)、『戦略モデルをデザインする』(日本公認会計士協会出版局、2018年)、『組織と権威』(文眞堂、2000年)がある。
-

中島 彰NAKASHIMA AKIRA
株式会社島津製作所 人事部2010年に総合電機メーカーに人事として入社。2017年から総合電子部品メーカーに転職し、人事部にてセンシングデータプラットフォームを活用した採用面接のPoCを企画、2018年11月からグローバル人事企画に従事。2022年7月より現職。
-

林 幸弘YUKIHIRO HAYASHI
株式会社リンクアンドモチベーション
モチベーションエンジニアリング研究所 上席研究員
「THE MEANING OF WORK」編集長
早稲田大学卒業。2004年に(株)リンクアンドモチベーション入社。組織変革コンサルティングに従事。早稲田大学トランスナショナルHRM研究所の招聘研究員として、日本で働く外国籍従業員のエンゲージメントやマネジメントなどについて研究。現在はR&Dに従事、経営と現場をつなぐ「知の創造」を行い、世の中に新しい文脈づくりを模索している。
前回、知のプラットフォーム、データベースとして、AOMがどのようにグローバルに機能していることを理解するために、その概要を論じた。今回、コペンハーゲンで開催された2025年AOM年次大会に実際に参加し、発表した実務家、経営コンサルタント、研究者の視点から、AOMに参加する意義と価値について、それぞれの体験をベースに検討する。
はじめに

前回、経営学に関する世界最大規模の経営学に関する学会であるAcademy of Management(以下、AOM)が知のプラットフォーム、データベースとしてどのように機能しているのか、その概要について説明した。今回、実際に、実務家、経営コンサルタント、研究者として、執筆者がそれぞれコペンハーゲンで開催されたAOM年次大会に参加してみて、どのような意義や価値を体験できたのかを論じることにする。
今回は、さまざまなセッションに参加するなかで、新たに学び、気がついたことにフォーカスし、それぞれが体験したことをベースにして、AOMの意義や価値について論じる。そして、次回は、実際に、AOMで研究成果を発表した経験を踏まえて、ポスターセッションでどのような内容を発表したか、実務家、経営コンサルタントの視点からどのようなことを考えていたのか、発表を通じてどのようなことを学んだのかを論じる。
実務家の視点から
2025年7月、コペンハーゲンで開催されたAOMの年次大会に初めて参加した。世界13,000人を超える研究者、実務家が集い、3,900以上のセッションが繰り広げられるこの場は、まさに、経営学のオリンピックと呼ぶにふさわしい知の饗宴であった。実務家として参加し、組織や人材マネジメントの現場と照らし合わせながら学ぶなかで、理論の意義や研究の蓄積をレビューすることの価値を強く実感した。ここでは、その体験を振り返り、実務家にとって、AOM参加の意義と価値を整理する。図表1のように、実務家にとっての学びをまとめることができる。

最も強く感じたのは、理論がもつ力である。日常の実務では、個別の事例や経験則に頼りがちであるのに対して、AOMではその背後にある理論的フレームワークが提示されていた。センスメイキング理論やリソースベーストビューといった考え方は、現場の判断を整理し、再現性をもたせる翻訳装置として機能する。単なる勘や経験を超え、組織課題を言語化、体系化できることは、実務家にとって非常に大きな意味をもつ。
また、研究の蓄積を体系的にレビューすることの価値も改めて実感した。セッションでは過去数十年にわたる研究成果を整理し、その上に新しい問いを立てるプロセスが多く紹介されていた。これは、日々の業務で短期的な課題解決に追われる自分にとって、新鮮かつ重要な視点であった。組織開発や人材育成の施策を考える際も、研究の蓄積に基づく裏づけがあることで説得力が増し、社内での合意形成がスムーズになる。
さらに、実務にすぐ役立つスキル開発の場も豊富に用意されていた。例えば、「英語での論文執筆・発表スキル」のセッションでは、非ネイティブが直面する課題とその乗り越え方が共有されており、国際的な場での発信に直結する内容だった。ケースメソッドやデータ分析のワークショップも、日常業務に取り込める即効性のあるヒントを与えてくれた。
AOMはネットワーク形成の場としても価値が高いだろう。研究者との対話を通じて、現場の課題を理論的に再定義するヒントを得られた。実務家としての経験を共有すると、研究者が興味をもち、そこから新しい共同研究やアイデアにつながる。単なる人脈作りではなく、互いの知を補完し合う関係が築けることは、今後の実務に直結する大きな財産となる。
今回の参加を通じて実感したのは、理論を学び、研究の蓄積をレビューすることが実務家にとって欠かせない営みであるということである。理論は現場を整理し、研究の蓄積は施策に信頼性を与える。そして、スキル開発やネットワーク形成を通じて、それらを実務に活かす基盤を得られる。AOMは、即効性のある学びと長期的に効く思考の土台を同時に提供してくれる場であった。現場の知を世界の知へと翻訳し、また研究知を現場に還流させる。その往復を加速させることこそ、実務家がAOMに参加する最大の意義だと確信している。
経営コンサルタントの視点から
初めてAOMに参加し、自分自身の背景とのつながりを考えてみると、経営コンサルタントとして、常に「企業はいかに持続的に成長し、革新を続けられるのか」という問いを抱いていることを感じている。AI、DX、グローバル競争、サステナビリティ、人材戦略の多様化、こうした複雑な課題に対応するには、現場経験だけでなく理論的な裏づけと再現性のあるフレームワークが不可欠でることに気がつく。
この課題意識を胸に、2025年7月、北米以外で初開催となったAOM年次大会に参加した。世界13,000人超の研究者、実務家が集うこの場は、知を深め、問いを再設計する貴重な機会となった。
AOMでは、AI導入と組織文化、ハイブリッドワークとエンゲージメント、サステナビリティと人材戦略といった、クライアント課題に直結するテーマが数多く議論されていた。理論が抽象的な概念にとどまらず、実務で活かせるロジックとして体系化されている点で非常に刺激的だった。
さらに、コペンハーゲン開催ならではの学びも大きく、グローバルとローカルのクロスオーバーもあった。北欧企業が実践する従業員主導型イノベーション(Employee-Driven Innovation)、心理的安全性を前提とした対話文化、労使協働による意思決定プロセスには特に多くの示唆があった。現場の従業員が主体となり、小さく試し、成果を全社に展開する、このような文化、制度、行動の三位一体のデザインは、日本企業が現場知をイノベーションに昇華させるうえで欠かせないヒントだと感じた。
セッションでの気づきとして最も印象的だったのは、経営テーマの多様性である。プラットフォーム戦略やエコシステム形成、AIとリーダーシップの関係性、センスメイキング、ウェルビーイング、働く意味(Meaning)、さらにはスピリチュアル領域まで、経営学が組織運営だけでなく、人間の意味づけそのものにまで射程を広げていることを肌で感じた。また、西洋と東洋という単純な二分法を超え、ラテンアメリカと西洋、北欧とアジアといった多元的な比較視点がごく自然に行われており、認知の枠を広げ、新しい発想の起点を得られたことは大きな財産になった。
AOMは、巨大な知のネットワークであると同時に、理論を介した共通言語の場でもある。RBV(リソースベーストビュー)、センスメイキング理論、弱いつながりの理論など、複数分野を横断する理論が自然に共有されており、理論を共通言語として使えば、日本の現場知を世界に翻訳できるという確かな手応えを得ることができた。
また、多様な分野の研究者に共通していたのは、図表2のように、問いを起点とした知の創造プロセスである。

このプロセスは、コンサルティングの現場にも応用できる。課題を定義し、小さく実験し、検証と改善を繰り返すことで、再現性のある知を積み上げられる、このような問いの作法の実践価値を再認識した。
AOMへの参加は、日常の認知の枠を超え、理論と現場を掛け合わせることで思考の幅と設計の深さを大きく広げる機会となった。理論を共通言語にすることで問題意識を研ぎ澄ませるだけでなく、世界中の研究者、実務家とつながり、知を更新し続けるネットワークを得られたことは、今後の挑戦を加速させる強力な基盤になると確信している。
さらに、日本企業の現場知や経営の深さが、理論を介した翻訳によって世界に通じる知へと変わる可能性を強く感じた。今回、ポスターセッションで発表した日本企業の強みを象徴する京都モデルが示す「知の循環と再生」の思想は、グローバルでも普遍的な価値をもつと思われる。今後は、実務事例を交えながらこの知を体系化し、世界に向けて発信していきたいと考えている。
今回の参加を通じ、世界と日本をつなぐ理論と実践の往復が生み出す可能性と確かな手応えを得た。日本発の知を世界の共通言語に翻訳し、グローバル経営の未来を共に創っていくこと、それが、これから私が果たすべき役割であると考えている。
研究者の視点から
2009年にシカゴで開催された年次大会から、コロナ禍を除いて、ほぼ毎年、コンスタントに参加している。当初は、セッションに参加するだけであったが、その後、5回、シンポジウム、コーカサス、ポスターセッションで発表している。
AOMの年次大会は本当に大規模なものである。AOMから大会後に配信されたメールによると、2025年、開催される5日間で13,403人の参加があり、3,936のセッションが行われたとのことである。今年はコペンハーゲンで開催されたこともあり、アメリカからの参加が3,428人で、それ以外が9,297人であった。
1つのセッションはだいたい1時間半を標準としている。1日、そうしたセッションを5、ないしは、6つに参加するとして、5日間で30程度に参加することができる。しかし、3,000のうちの30に参加できるので、全体の1%にもみたないことになる。そのために、図表3のように、大会までにプログラムをよく検討し、事前に興味深いセッションを選択しておくとよいだろう。その際に、個人的には、最新の研究動向をサーチしたいので、あまりなじみのないアイデア、概念、研究方法を採用しているものを選ぶようにしている。

ここ15年間にAOMの年次大会に参加するなかで感じるのは、AOMにおける研究には多様性があるということである。また、最新の研究動向だけではなく、スキルを高めたり、ネットワークを形成したりするセッションが豊富に用意されている。さらに、普段は著書や論文でしか知らない著名な研究者のセッションに、直接、参加することも楽しいものである。これまでに、ヘンリー・ミンツバーグ、エドガー・シャイン、ジェイ・バーニー、クレイトン・クリステンセン(病気のためにオンライン参加)などのセッションに参加した。今年は、アントレプレナーシップ論で著名で、エフェクチュエーションの概念を提唱しているサラス・サラスバシーのセッションに参加した。
スキルを高めるセッションとしては、英語のノンネイティブに向けて、英語で論文を執筆するスキルをどのように高めていくかというものに参加した。このセッションは2024年にも開催されていて、OB(組織行動)部会で継続的に取り組んでいるとのことであった。当たり前のことであるが、英語の文章力を高める特効薬があるわけではなく、指導教員からフィードバックを受けること、毎日、少しずつでも英文の書き続けること、ネイティブでも苦労していること、など、登壇者からさまざまな体験談を共有してもらった。
また、ハーバード・ビジネス・レビュー(HBR)、MITスローン・マネジメント・レビュー(SMR)、カリフォルニア・マネジメント・レビュー(CMR)など代表的なビジネス誌のエディターが研究者向けだけではなく、広く実務家に向けて、研究を発信していくことの重要性を論じるセッションに参加した。共通して、エディターは、実務家が直面する課題に取り組むこと、具体的な解決策を提案すること、十分なエビデンスをもって、議論を展開することの必要性を強調していた。
多様性という点では、ファシズムを、国家、あるいは、国民を統合する経営理念として捉えることを議論するセッションに参加した。取り扱いを誤ると場が荒れる可能性をもつテーマであったが、冷静に発表と議論が進められていた。ただし、発表者の一人が小声で発表していて、聴衆からもっと大きな声を出すように促されると、「声高々に発表するようなことではない。前の席が空いているから、聞きたければ、前に来い」という発言もあり、緊張が走る場面もあった。また、Q&Aでは、ファシズムと呼ばれていることにも多様性があること、ファシズムを標榜する各団体においても考え方が異なることなどのコメントがされていた。
最新の研究動向については、個人的には、現在、自分が取り組んでいる研究、あるいは、興味をもっている領域に関するものを中心に、プログラムを検討して、参加するセッションを選択した。今回は、組織理論については、分散型組織、後期の授業で、アントレプレナーシップ論を担当することもあり、起業に関わるもの、特に、エコシステムとアントレプレナーシップ教育に関わるセッションに参加した。
前者については、今回、ポスターセッションで発表することもあり、分散型組織について取り上げているポスターセッションに下見として参加してみた。プログラム上では、コンセプチュアルな研究であったが、話を聞いてみると、120社を対象とする実証研究に切り替えたとのことであった。特に、権限構造が階層的な組織とどのように異なるか、分散型組織においても完全に権限を委譲するのではなく、権限構造を残すことを論じ、どのように階層的組織と異なるかにフォーカスをしているとのことであった。その際に、分散型組織を中心に研究コミュニティがあり、シンポジウムを企画しているので、参加しないかと誘われ、シンポジウムのセッションにも参加した。
アントレプレナーシップに関するセッションには、いくつか参加した。一つは、アントレプレナーシップがマクロ構造とミクロ構造をどのようにリンクさせているかを論じるセッションであった。起業家についてもエコシステムの視点からマクロ構造にアプローチするものと起業家自身のネットワーク、リーダーシップに注目するものに分かれていて、そのブリッジを模索していた。また、別のセッションでは、ハイプ(hype)という現象からアントレプレナーシップを議論するセッションがあった。起業家が追求する新しいビジネスには、ある種の誇張があり、過大な期待を抱かせ、そのことによって資金を集め、誇張された製品やサービスがリリースされること、これらにどのように対処するかを議論していた。さらに、アントレプレナーシップ教育については、アクションベースの教育について検討を行い、大学などの教育機関でどのように実際にビジネスにむすびつけていくか、その取り組みが紹介されていた。
おわりに

今回、実務家、経営コンサルタントとして、初めて、AOMに参加することで、気がついたポイントを指摘した。これに対して、研究者として、継続的にAOMへ参加を続けているなかで感じている意義と価値を論じた。
共通して感じていることは、理論と実践との往還であり、その結果として、実務家、経営コンサルタント、研究者が広く、深く、知的な交流を進めることによって、知のネットワーク、人的ネットワークを形成できることである。また、日本という比較的に閉じられた世界だけではなく、グローバルにそのつながりを広げ、いわゆる研究、実践の多様性から新しい可能性を広げることができるという感覚が得られることである。
AOMでは、そうしたことを可能にする仕掛けが時間をかけて、作り上げてきたことをさまざまなセッションに参加することで実感でき、大きな刺激を受けることが可能である。理論のもつ力、膨大な知の蓄積とその整理、知を活用するスキル、ネットワーク形成、理論を実践に生かすロジック、グローバルとローカルのクロスオーバー、研究テーマの多様性と最新性、知の創造プロセス、グローバルな研究発信など、AOMに参加することは、研究者だけでなく、実務家、経営コンサルタントにとっても大いなる学びを得ることができる場を形成している。
次回では、実務家、経営コンサルタント、研究者が協働して、どのように研究成果を発表していったか、その軌跡を論じることにする。