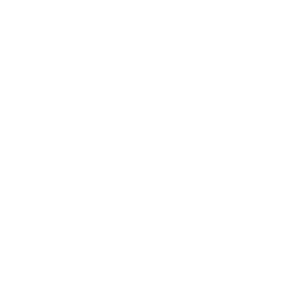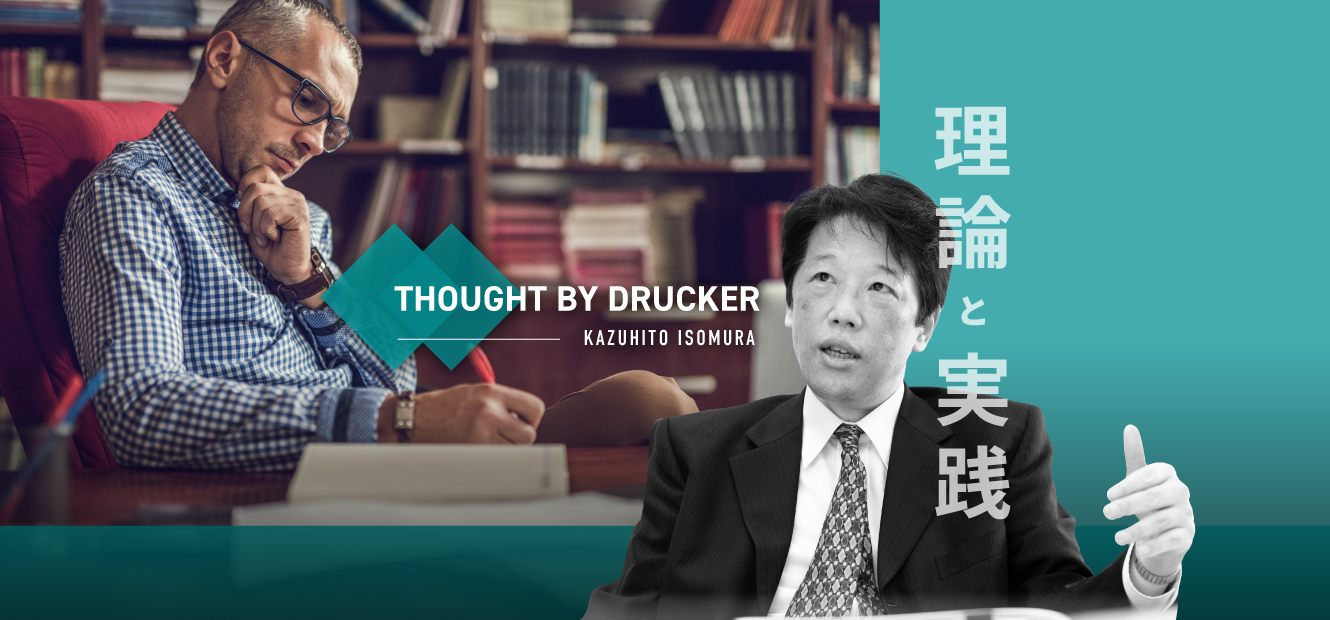AOMで研究発表する
-

磯村 和人Kazuhito Isomura
中央大学 理工学部ビジネスデータサイエンス学科教授京都大学経済学部卒業、京都大学経済学研究科修士課程修了、京都大学経済学研究科博士課程単位取得退学、京都大学博士(経済学)。主著に、Chester I. Barnard: Innovator of Organization Theory(Springer, 2023年)、『戦略モデルをデザインする』(日本公認会計士協会出版局、2018年)、『組織と権威』(文眞堂、2000年)がある。
-

中島 彰NAKASHIMA AKIRA
株式会社島津製作所 人事部2010年に総合電機メーカーに人事として入社。2017年から総合電子部品メーカーに転職し、人事部にてセンシングデータプラットフォームを活用した採用面接のPoCを企画、2018年11月からグローバル人事企画に従事。2022年7月より現職。
-

林 幸弘YUKIHIRO HAYASHI
株式会社リンクアンドモチベーション
モチベーションエンジニアリング研究所 上席研究員
「THE MEANING OF WORK」編集長
早稲田大学卒業。2004年に(株)リンクアンドモチベーション入社。組織変革コンサルティングに従事。早稲田大学トランスナショナルHRM研究所の招聘研究員として、日本で働く外国籍従業員のエンゲージメントやマネジメントなどについて研究。現在はR&Dに従事、経営と現場をつなぐ「知の創造」を行い、世の中に新しい文脈づくりを模索している。
-

クレイマージョーンズ・ジェイJAY KRAEMER-JONES
株式会社リンクグローバルソリューション
コンサルタント
ドイツ生まれ。イギリスのカーディフ大学でビジネスおよび日本学を専攻し、立命館大学に1年間交換留学、2014年に学士号(BSc)を取得。卒業後、会計、税務、コンサルティングなどのプロフェッショナル・サービス事業を展開するアーンスト・アンド・ヤングLLPに入社し、ロンドン本部で人材の国際間異動に関わるコンプライアンスとコンサルティングサービスを提供。2016年に日本政府のJETプログラムに参加、公務員として山形県で地域における国際化に寄与。2018年に(株)リンクグローバルソリューションに異文化コミュニケーションインストラクターとコンサルタントとして入社。日本語能力試験およびビジネス日本語テストともに1級合格。英語とドイツ語を母国語とする。
前回、AOMに参加する意義と価値について、実務家、経営コンサルタント、研究者の視点から検討した。海外に研究発信することを目指し、実務家、経営コンサルタント、研究者の共同チームでAOM年次大会のポスターセッションで発表した。今回、どのような研究成果を発表したか、発表内容をどのように考えているか、発表を通じてどのようなことを学んだかを論じる。
はじめに

前回、Academy of Management(以下、AOM)に参加する意義と価値について、実務家、経営コンサルタント、研究者の視点から検討した。その中で、AOMに参加する意義と価値の一つとして、グローバルに研究成果を発信することを挙げた。これを受けて、実務家、経営コンサルタント、研究者の共同研究チームとして、執筆者たちは、2025年7月25~29日までコペンハーゲンで開催されたAOM年次大会に参加し、ポスターセッションで発表した。
今回、第2節では、どのような研究成果を発表したか、その内容を紹介する。第3節では、それぞれが発表した内容について、どのようなことを考えていたのか、発表を通じてどのようなことを学んだのか、実務家、経営コンサルタントの視点から論じる。3.1は中島彰、3.2は林幸弘、3.3はクレイマージョーンズ・ジェイがそれぞれ担当している。
国際学会にプロポーザルを提出し、アクセプトされ、発表するまでには多くのチャレンジがあり、容易なことではなかった。しかし、それらに対処し、乗り越える中で、同時に得ることができるものが多くあることも実感した。AOMで研究発表するということはどういうことか、自らの体験をレビューする中で考える。
京都モデルを提唱する
2024年9月から、AOMで発表できないかという模索を始め、2025年1月のプロポーザルの提出に向けて準備を進めた。実務家、経営コンサルタント、研究者の共同チームとして、これまで取り組んできたことを活かし、発表を行うことにした。その結果として、今回、「なぜ、京都においてグローバルに事業展開する長寿企業群が形成されているか」というリサーチクエスチョンを立て、京都モデルを提唱することにした。以下では、どのような内容を発表したか、その概要を説明する。
ポスターの冒頭では、京都モデルがどのようなものか、そのサマリーを示した。京都モデルを経営理念によって駆動されるビジネスモデルとして定義した。図表1のように、その基本的な特徴として、①経営理念、経営哲学の重視、②伝統工芸と近代技術の融合、③コミュニティとの強い結びつき、④企業の長寿性、⑤産業、政府、アカデミックの協働を挙げた。

京都モデルの特異性を際立たせるために、産業集積し、独自のエコシステムを形成するイタリアモデル、ドイツモデル、シリコンバレーモデルとの比較を示した。イタリアモデルは、ファッション産業などにおいて伝統的職人と近代デザインを融合させ、地域に根差しながら、ファミリービジネスを展開している。また、ドイツモデルは、中小企業を中心に科学と技術を組み合わせながら、漸進的にイノベーションを実現している。さらに、シリコンバレーモデルは、明確なビジョンに基づいて、新しい技術を高速に発展させ、大きな利益を短期で収穫している。
これに対して、京都モデルは、迅速で、短期的な利益を生み出すシリコンバレーモデルとは対極にある。伝統工芸と近代技術を組み合わせる点では、イタリアモデルと共有するが、京都モデルは、高度な近代的技術で競争力を生み出す製造業を中心に事業を展開している。ドイツモデルについては、製造業を中心にすること、大企業よりは中堅企業を中心にすることで共通点を持つものの、経営理念、経営哲学を駆動し、長寿企業を生み出す点で京都モデルと異なっている。
続いて、ポスターでは、本研究で採用される方法について論じた。京都モデルを明らかにするために、その中心にある経営理念が経営にどのような影響を及ぼしているか、京都をベースに事業を展開する企業に対する事例研究に取り組んだ。図表2のように、さまざまな定性的な研究方法を組み合わせることで、多面的に対象にアプローチすることにした。対象とする企業として、今回、パナソニック、島津製作所、オムロンを取り上げた。

経営理念、経営哲学を継承するための仕組みについて、それぞれの企業に対して、半構造化インタビューを実施した。また、長寿企業ということもあり、経営理念に関するアーカイブズが保存されているので、基本的な文献や資料を検討することで歴史分析にも取り組んでいる。さらに、経営理念、経営哲学、企業の歴史を継承するための施設、その展示について現地調査を実施した。
経営理念、経営哲学を経営に活かす取り組みについては、これまで蓄積されてきた研究について文献レビューを行い、分析フレームワークの構築を目指した。組織とマネジメントの理論とどのように接続するかを検討し、理論的な意義や貢献を特定できるように、理論研究にも従事した。また、上述したように、単に京都モデルを提唱し、その独自性を主張するだけではなく、共通点、相違点を持つ複数のモデルと対照させる比較研究も行うことで、より立体感のある研究を志向した。
図表3のように、ポスターでは、研究の結果として明らかになったことを、①京都企業の長寿性、②経営理念、経営哲学をベースにしたイノベーション、③近代組織論と京都モデルの共振性、という3つのポイントにまとめることで論じた。

まず、京都企業の長寿性については、京都という都市が持つ力をテコにしていることを説明した。京都は、1,000年を超えるかつての日本の首都であり、そのエトスが組織文化に深く根づいているとした。京都は、伝統工芸、商業の発展から近代技術の導入へ、さらに、観光文化産業へと時代に応じて、社会的、あるいは、産業的な転換を図ってきた。
こうした流れに沿う中で、明治以降、近代技術が導入され、伝統工芸と組み合わせることで、独自の強みを持つ長寿企業を生み出してきた。その際、経営哲学と近代技術を融合させ、社会的責任を追求し、アイデンティティを失うことなく、変化に対応する組織文化を形成させた。京都というコミュニティに深く根づきつつ、進化を図る能力によって、長期に存続し、再帰性を持つ京都モデルを構築した。
伝統工芸としては、西陣織、清水焼、酒蔵などがある。また、近代技術をベースに製造業として発展した企業として、島津製作所、オムロン、パナソニックなどを挙げている。さらに、観光文化産業としては、京都電気鉄道、星野リゾート、京都国立近代美術館などがある。
続いて、経営理念、経営哲学が伝統を守りつつ、革新を引き起こすという役割を果たしているとした。ここでは、オムロンの事例を取り上げた。オムロンには、創業者の立石一真によって生み出されたSINIC(サイニック)理論がある。これは、社会の変化に応じて、産業がどのように進化を遂げるかを論じる未来予測理論である。したがって、この理論に従うと、社会の進化に伴って、経営哲学も経営目標も変化させる必要がある。
京都企業は、同様の経営方針を持っていて、単に製品やサービスを改善するだけでなく、価値システムを転換させ、社会構造の変革を志向している。そのため、産・官・学が協働し、京都エコシステムを形成している。例えば、京都大学などの研究機関、京都市、京都をベースにする企業が協力するコミュニティを構築している。技術は社会を変化させるドライバーとしてあり、これが経営理念、経営哲学、コミュニティを組み合わされることで、社会に新しい価値を生み出し、イノベーションを絶えず引き起こそうとする。
具体的な事例としては、AI、センシング、ロボティクス、iPS細胞などがある。最新のテクノロジーがどのような社会をつくり出す可能性を持つか、そのベースになる考え方を経営理念、経営哲学をつき合わせることで、どのような価値を新しく社会に提供できるか、という視点から検討され、次世代の製品やサービスを生み出している。それらは、マーケットとしてニッチであっても、グローバルに展開することで、大きく社会変革をもたらす。
最後に、文献研究を踏まえて、京都モデルと近代組織論との概念的な類似性についても指摘した。1930年代に近代組織論の祖であるチェスター・バーナードは、組織の長期存続において経営哲学、道徳性の重要性を論じている。同時代に、パナソニックの創業者である松下幸之助も企業の長期的な存続と発展において、経営理念、経営哲学の重要性を認識し、共通目的の共有を打ち出している。
したがって、京都モデルは、バーナードが理論的に主張したことを実践的に示した貴重な事例であると考えられる。京都モデルに関する研究を深めることによって、現在にも通じる理論を構築することが可能になり、組織とマネジメントの理論への貢献を果たすことができる。
また、京都モデルは、リソースベースドビューとも共振するとした。リソースベースドビューでは、模倣困難な経営資源として有形、無形資源の重要性を論じているが、京都モデルは、無形資源の中でも、とりわけ、経営理念、経営哲学が組織を長期に存続させ、発展させるものとして位置づけたと考えられる。こうした視点からも京都モデルを検討することは、組織とマネジメントの理論に対して新しい知見を提供することを可能にする。
組織とマネジメントの理論、リソースベースドビュー、経営哲学を組み合わせることによって駆動されるビジネスモデル、エコシステムとして京都モデルを提唱する意義があるとした。
研究発表を通じて考えたこと

3.1 理論と実践の往還から経営知を生む
今回、AOM年次大会で「京都モデル」に関する研究成果を発表する機会を得た。実務家として研究活動に参画し、経営理念、経営哲学が企業の持続性やイノベーションにどのように影響を及ぼすかを整理する過程で、理論と実務の往還の重要性をあらためて実感した。
3.1.1 研究内容に込めた考え
京都モデルは、経営理念を中心に据え、伝統工芸と近代技術を融合しながら地域コミュニティと共生するビジネスモデルである。私はこの研究を通じて、「理念が現場でどのように生きるのか」「企業文化がいかにイノベーションを生み出すのか」という問いに焦点を当てた。島津製作所やオムロンなどの事例を分析する中で、理念は抽象的なスローガンではなく、現場での意思決定や技術開発の基盤として機能していることを確認した。
実務家として特に関心を持ったのは、理念を共有する仕組みよりも、体感させる文化である。京都企業では、言葉で理念を説明するよりも、職場の作法や製品づくりのプロセスの中で理念を体得する仕組みがある。これは人材育成や組織文化形成において極めて実践的な示唆を与える。理念の形式的伝達ではなく、身体知としての継承が持続的な組織の強さを生むと考える。
3.1.2 発表を通じて得た学び
AOMでは、AI、サステナビリティ、ハイブリッドワークなど、世界中の研究者が現場の課題に対して理論的アプローチを試みており、理論が実務と密接に接続されていることに刺激を受けた。特に、印象的だったのは、北欧の研究者による「Employee-Driven Innovation(従業員主導型イノベーション)」の議論である。これは、現場の主体性から変革を起こすというもので、京都企業の理念駆動型イノベーションと深く共鳴する。
また、海外の参加者からは「京都モデルを他地域へ適用できるのか」という問いが多く寄せられた。この指摘を通じて、京都の歴史、文化、地域コミュニティといった文脈を踏まえながらも、普遍的に応用可能な原理を抽出することの重要性を学んだ。理念の共有、知の循環、コミュニティとの共創といった構成要素は、グローバル経営においても再現可能なフレームになりうる。
3.1.3 今後の展望
今回の発表を通じて、理論と実務の往還にこそ新しい経営知が生まれることを確信した。研究の深化とともに、理念や哲学を行動レベルで実装する動的知マネジメントの仕組みづくりを実務の現場に活かしていきたい。実務家として、経営理念を経営の文法として再定義し、企業の持続的成長を支える理論と実践の橋渡しを担うことが、今後の自らの使命であると感じている。
3.2 グローバルな知と京都モデルが示す未来
コペンハーゲンで開催されたAOMでは、AI導入、組織文化変革、ハイブリッドワーク、サステナビリティなど、企業の現場課題に直結するテーマが数多く議論されていた。印象的だったのは、それらの学術知見が実務に活かせるロジックとして再構築されていた点である。理論が現場に降りていく光景を通じて、理論を実務に翻訳する力こそが今後の経営に不可欠だと感じた。理論は遠い存在ではなく、現場の課題を構造化し、普遍性を与える共通言語である。
欧州開催の特徴として、北欧企業や研究者との交流も深まった。とりわけ「Employee-Driven Innovation(従業員主導型イノベーション)」の事例は、ボトムアップ型変革を考えるうえで示唆に富んでいた。制度や仕組みではなく、現場の主体性を起点に価値を創出するプロセス設計こそ、エンゲージメント経営の核心である。
こうした議論を整理する中で、日本企業の潜在力を体現する京都モデルにあらためて注目した。京都企業が長年培ってきた知の循環と再生の仕組みは、世界に通用する経営モデルであり、持続的成長の条件を示している。
3.2.1 開放と閉鎖の二重構造
京都企業は、外部の知を柔軟に取り込みつつ、自らの価値観と哲学を守り続けてきた。島津製作所は職人技を工業技術に昇華し、高精度、多品種少量生産を実現している。外からの刺激を自らの文脈で再構成し、深化させる姿勢が独自性を生む。
3.2.2 身体性ある知の継承
知の継承は言語ではなく身体を通じて行われる。熟練者の暗黙知を観察、体感して学ぶ過程が、知を「生きた知」として定着させる。理念を伝えるのではなく、体感させることが行動変容を促す。
3.2.3 棲み分けによる創発的共創
京都の産業エコシステムは競争よりも補完に基づく。各企業が強みを活かし、相互に補い合うことで、新たな価値を創出してきた。この棲み分けによる創発は、複雑な社会課題を解く共創経営の理想形の一つではないか。
3.2.4 地域連携による知の循環
産・官・学・地域が多層的に連携し、知と人材が循環する知のエコシステムを築いてきた。企業は常に新しい知を取り込み、再生させ続け、地域に根づく持続的経営の基盤を構築する。
以上のように、京都モデルが示すのは、知は静的に管理するものではなく、動的に循環させるべきものだという考え方である。変化の激しい現代において、この動的知マネジメントこそが持続的競争優位の鍵となる。実務家としての現場感覚と研究者としての分析視点を融合させ、日本企業の知を理論化し、世界へ発信していく。理論と実践をつなぎ、知を再生させる営みこそが、これからのビジョンとなる。
3.3 日本における経営知の意義とその適用可能性
今回、コペンハーゲンで開催されたAOM年次大会において、京都モデルに関する研究成果をポスターセッションで発表する機会を得た。私自身の主な役割は、現地で研究者と対話し、フィードバックを受け取ることであったが、その過程で多くの学びを得ることができた。
まず印象的だったのは、京都企業の長寿性と経営理念、経営哲学の重視という特徴が、海外の学術関係者に強い関心を持って受け止められた点である。日本では当然のように思える価値観であっても、グローバルな視点から見るとユニークであり、社会的責任やコミュニティとの結びつきを基盤にした経営の在り方は、国際的にも示唆に富むことを実感した。
これに対して、議論を通じて浮き彫りになった最大の課題は、京都モデルの移転可能性(transferability)であった。複数の参加者から、「京都という歴史や文化、地域コミュニティに根差した独自のエコシステムがあって初めて成立しているのではないか。他の地域や企業に適用できるのか」という問いが投げかけられた。この指摘は、京都モデルの独自性を強調するだけでは不十分であり、どの要素が普遍的に応用可能で、どの要素が文脈依存的なのかを明らかにする必要性を示していると感じた。
実務家としての視点からいえば、これは大変重要な示唆である。日本の経営の強みを紹介するだけでなく、他国や多国籍企業にとっても応用可能な形に落とし込むことで初めて、研究成果がグローバルな実務に貢献できる。今後は、比較研究や追加事例の収集を通じて、この問いに応える研究を深める必要があるだろう。
総じて、今回のAOM参加は、日本発の経営知が国際的に価値を持つことを確認できた一方で、今後の研究の方向性をより明確にするきっかけとなった。今後は、京都モデルの理論的意義をさらに発展させるとともに、実務における適用可能性を検討することで、日本の経営知をグローバルに発信し続けたいと考えている。
おわりに

実務家、経営コンサルタント、研究者の共同チームで、AOMに研究発表をするというプロジェクトに取り組んだ。ここでは、その研究成果がどのようなものであるかを論じてきた。また、発表してみて、理解したこと、感じたこと、学んだことを見直してみた。その概要をまとめると以下のようになる。
研究発表では、京都には伝統工芸と近代技術を融合させ、長期に存続、発展を図る企業群が存在することに注目し、京都モデルを提唱した。単に、日本独自のビジネスモデルやエコシステムのアイデアを提示することにとどまらないように、イタリアモデル、ドイツモデル、シリコンバレーモデルとの比較も試みた。その中で、なぜ、他のモデルとは異なり、長寿性を確保できるのかを考察した。経営理念、経営哲学をベースにして、社会、文化、技術の変化と要請に応えることで、伝統と革新を両立させていることを明らかにした。
1990年まで世界を席巻した日本企業の強さが喧伝された時には、日本企業について研究発表をすることが世界から求められた。しかし、研究発表をしてみて、今でも日本から発信すべき研究成果は蓄積されていて、それらを積極的にグローバルに展開することは十分に価値や意義を持つことを感じることができた。
実務家として、発表に参加したメンバーは、理論と実践の往還を強く実感したことを述べている。また、経営コンサルタントとして、発表したメンバーは、理論と実践をつなぎ、知の動態化を図ることの必要性を理解したという見解を示している。さらには、海外に日本の経営知を伝えるだけでなく、よりその価値を高めるために、応用可能性を追求することの重要性を認識できたという学びがあったことが指摘された。
AOMは、グローバルに知を共有し、展開するプラットフォーム、データベースとしてあり、知にアクセスするだけではなく、知を発信し、知のダイナミズムを生み出している。こうした知のダイナミズムを推進するエージェントとして、参加できるということは、何よりも代えがたい貴重な経験を積み重ねることを可能にしてくれる。