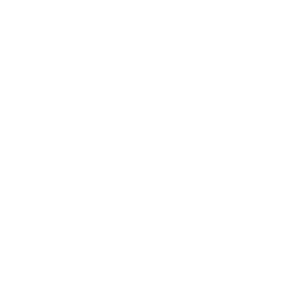第5回 コミュニケーションのメディア(3)
-

徳安 彰AKIRA TOKUYASU
法政大学社会学部教授東京大学文学部社会学科卒業。同大学院社会学研究科博士課程修了。法政大学社会学部専任講師、同助教授、ビーレフェルト大学客員研究員、法政大学社会学部教授、法政大学社会学部学部長を歴任。共著に『社会理論の再興』(ミネルヴァ書房)、『理論社会学の可能性』(新曜社)など。
第5回、第6回に続いて、コミュニケーションのメディアについて論じる。過去2回でコミュニケーションの非蓋然性の三つの契機のうち、理解と到達について論じたので、今回は最後の契機、つまりコミュニケーションの成功の非蓋然性を蓋然性に転換するためのメディアとして、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアについて論じる。このメディアも、理解のためのメディアとしての言語や、到達のためのメディアとしての文字から電子メディアにいたるまでのさまざまな伝達メディアと同様に、社会発展の歴史のなかでしだいにメディアとして確立されてきた、とルーマンは考えている。そして、複数の象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアが、それぞれ異なる意味領域におけるコミュニケーションの成功の蓋然性にかかわるように特化したかたちで発達してきた。この特化した複数のメディアの発達は、社会全体の機能分化の進展というルーマンの社会分化の議論と密接な関係をもってくる。
成功のメディアとしての象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア

それにしても、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアとはいったい何だろうか。先に具体例をあげると、ルーマンは、貨幣、権力、真理、愛といったものを、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの典型として論じている。貨幣はまだしも、権力にはどうしても背後にむき出しの物理的暴力の存在を感じるし、真理は「永遠の真理」という言葉に象徴されるように、根本的な世界のあり方を象徴するものに思われるし、愛はあえて「永遠の愛」とまでは言わないまでも、大切な心のありようを指すものに思われる。これらのどこが、「象徴的に一般化された」ものなのだろうか。またどのような働きがコミュニケーションのメディアといえるのだろうか。
このメディアの概念は、社会学に固有のものであり、社会学のなかでもさほど一般的に使われているわけではない。ルーマンの議論に先行したのはパーソンズの議論だが、「象徴的に一般化された相互交換メディア」という名称がもちいられており(Parsons, 1969=1973-74)、名称だけでなく理論的な位置づけも異なる。ルーマン自身がたびたび指摘している違いを簡単にまとめると、次のようになるだろう(Luhmann, 1997=2009, 1, p.358以下; Luhmann, 2005=2009, p.186以下を参照)。
(1)パーソンズの出発点は行為概念であるのに対して、ルーマンの出発点はコミュニケーション概念であり、行為と体験の概念の組合せをもちいている。
(2)パーソンズのメディアの分類はAGIL図式にもとづいて演繹的に4つが導出されているが、ルーマンのメディアの分類は西洋社会の歴史的発展にそくして経験的に導出されている。
(3)パーソンズのメディアはAGILの4機能への機能分化を前提としているのに対して、ルーマンのメディアは経験的な機能分化をもたらす(あるいは歴史的な機能分化とともに発達する)。
(4)パーソンズのメディアはAGIL図式にもとづいて機能分化した社会の下位システムの相互交換の働きをするのに対して、ルーマンのメディアはむしろ意味的に閉じた(歴史的にはしだいに閉じたものとして分出していく)下位システムの内部でコミュニケーションのオートポイエーシスを再生産する働きをする。
これ以上詳細に二人の理論の比較をするのはここでの主旨ではないので、とりあえずは以上の抽象的な整理にとどめておこう。
ルーマンの議論にもどると、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアは、コミュニケーションが内在的にもつ三つの非蓋然性(コミュニケーションの成り立ちがたさ)である理解、伝達、成功の、最後の成功にかかわるものとされている。成功とは、コミュニケーションが受け入れられ、同じ意味の文脈のなかで続いていくこと、つまりコミュニケーションが再生産されることである。コミュニケーションが拒絶されれば、そこで「話は終わり」となり、コミュニケーションは終了する。もちろん、具体的な個人どうしのコミュニケーションは、二人だけでどこまでも延々と続くわけではない。とくに拒絶しなくても、二人にはそれぞれの生活の都合があり、どこかで話にきりをつけなければならないが、それだけで二人の関係が途絶えるわけではない。会社や学校も24時間制ではないから、終業から次の始業まではコミュニケーションが一休みになるが、そのたびに会社や学校がなくなるわけではない。だが、一般に社会はより多くの人びとの多様なコミュニケーションからなりたっており、この広い範囲での複雑なコミュニケーションがすべて終了してしまうと、コミュニケーションから成り立つ社会システムそのものが崩壊ないし消滅してしまう。象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアは、コミュニケーションの受容=成功によるコミュニケーションの再生産という意味での社会システムの存続・維持に不可欠である。
コミュニケーションの受容=成功は、二人だけ、あるいは少人数の対面状況であれば、まだ音声言語の力によるところが大きい。第5回でオングによる「声の文化」の特徴を紹介したが、音声言語はそれじたいの語り口とコミュニケーションにかかわる人びとの生活世界への密着によって独特の説得力をもち、それによってコミュニケーションの受容=成功をもたらし、社会の恒常性を維持する。音声言語それじたいが、伝達のメディアでもあり、成功のメディアでもありうる。これに対して、「文字の文化」になると、音声が欠落するために、表現は感情を込めることが難しくなって感情中立的になり、さらに伝達の時間的・空間的な範囲が拡大することによって、関係する人びとの生活世界から離れたものになっていく。文字は重要な伝達メディアだが、コミュニケーションは、対面状況における音声言語によるものとは異なる様相を呈するようになる。コミュニケーションの受容=成功という観点から見れば、受容を促すような濃密な雰囲気が薄れ、生活世界に密着した説得力が弱まる。つまりは受容=成功の非蓋然性が増すのである。さらに、伝達メディアが印刷や電子メディアへと発展すると、伝達範囲は空間的・時間的に飛躍的に拡大するかわりに、対面状況において音声言語がもつアウラは消えて、乾いた冗長な反復が起こるだけになる。人びとは、生活世界に密着したコミュニケーションの状況からどんどん離れていくので、その分だけ拒絶することが容易になる。受容=成功の非蓋然性はいよいよ大きくなる。(音声系の電子メディアによるコミュニケーションについては、少し別の考察が必要かもしれない。)
この過程は、原初的な対面状況における音声言語によるコミュニケーションが前提としていた社会的統合から、送り手と受け手をしだいに切り離し、またコミュニケーションの状況からもしだいに切り離していった。それにつれて、コミュニケーションの受容=成功の非蓋然性が大きくなってきたのである。そのような社会状況のもとで、それでもコミュニケーションの受容=成功の蓋然性を高める働きをするのが、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアである。「象徴的に一般化された」という修飾語は、このメディアが、しだいに分離していく送り手としての他我と受け手としての自我をふたたび結びつけ(象徴化)、状況に依存することなくコミュニケーションが受容されるようにする(一般化)ことを意味している。したがって、原初的なコミュニケーション状況から社会が発展し、大規模で複雑になるほど、社会のコミュニケーションのオートポイエーシスを維持するためには、この象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアが必要になってくる。
象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの働きと成り立ち
ルーマンによれば、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアは、コミュニケーションの受容=成功の蓋然性を高めるメディアである。受容=成功の蓋然性を高める働きとは、具体的にどのようなことだろうか。
もっとも一般的には、「選択と動機づけという蓋然性のきわめて低い組み合わせを継続的に可能にしていくこと」(Luhmann, 1997=2009, p.361)であり、「コミュニケーションの選択を条件づけて、同時に動機づけ手段としても働くようにする、つまり当該の選択提案に〔受け手が〕従うだろうと、十分確実に見込めるようにすること」(Luhmann, 1984=2020, p.219)であると述べられている。コミュニケーションにおける送り手は、意味のあるメッセージを送るために、何らかの意味構成上の選択をするわけだが、その選択が特定の条件にしたがってなされていることが受け手に知られている場合に、はじめて受け手はメッセージが意味する選択を受容し、こんどはそれを前提としてみずからの選択をするように動機づけられる、というわけである。送り手からのメッセージがどのような条件にしたがった選択かが理解できなければ(つまり意味不明のメッセージであれば)、受け手は戸惑ったり訝しんだり、あるいは怒ったり無視したりするばかりで、メッセージの受けとりようがない。そのようなメッセージは、受け手にとって自分の選択の前提にしようがないからである。それではコミュニケーションは受容されず、したがって継続されない。メッセージの意味をじっくりと問い直し、理解を深めていくだけの時間的な余裕とお互いの密接な関係があれば、受容=成功の非蓋然性は蓋然性に転換されるかもしれないが、とくに大規模で複雑な社会では、一般に送り手と受け手の関係はさほど密接ではなく、じっくりとメッセージの意味を問い直す時間的な余裕もない。いつでも、だれとでも、コミュニケーションがただちに成り立つような条件がないと、コミュニケーションはたちまち滞ってしまう。そのような状況のためのメディアが、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアなのである。
つぎに、このメディアの成り立ちについて見ていこう。先に述べたように、ルーマンは、みずからのメディアの分類がパーソンズのように演繹的に導出されたものではないと言いながらも、コミュニケーションでは送り手と受け手が存在すること、またコミュニケーションにおける選択が送り手ないし受け手に帰属されるか、それとも送り手ないし受け手の環境に帰属されるかによって、4つのタイプに分類されるとしている。送り手を他者、受け手を自我と言い換え、送り手ないし受け手への選択の帰属を行為、送り手ないし受け手の環境への選択の帰属を体験と呼ぶことによって、次のような分類が得られる(Luhmann, 1997=2009, 1, pp.376-378)。

①他者が自身の体験をコミュニケートすることによって、自我の側で対応する経験を生じさせる。その典型は真理というメディアである。価値も同様である。
②他者の体験から、自我の側での対応する行為が生じる。その典型は愛というメディアである。
③他者の行為が自我によってただ体験される。その典型は所有権/貨幣というメディアである。芸術も同様である。
④他者の行為が自我による対応する行為をひき起こす。その典型は権力/法というメディアである。
このような図式のもとで見ると、コミュニケーションの受容=成功とは、送り手(他者)の選択(体験/行為)を受け手(自我)の選択(体験/行為)の条件として接続することができることである。あるいは、コミュニケーションの受容=成功とは、送り手がさまざまな可能性からの選択として伝えるメッセージを受けとることによって、受け手にとっては新たにみずからの選択のための可能性の地平が開かれることだと言ってもよいだろう。
ただ、これだけではまだあまりに抽象的な説明であり、具体的に挙げられているそれぞれのメディアがどのような選択の条件づけをするのか、よくわからない。そこでつぎに、典型的なものとして挙げられている真理、愛、貨幣、権力について、それぞれ具体的に見ていくことにしよう(それぞれのメディアについての簡潔な解説については、徳安, 2017; 高橋, 2017; 春日, 2017; 長岡, 2017を参照。また貨幣以外については、Baraldi et al., 1997=2013の該当項目も参照)。
真理:科学におけるメディア

私たちは、自分自身を含めた世界(あるいは宇宙)のあり方について、一定の秩序をもつものとして認識している。その認識は、もともと人びとの生活世界のなかで、生活に密着したかたちで、生活に必要なものとして、いわば素朴なかたちで形成されてきた。その認識は、生活世界のなかでは日々の生活に役立てば十分であり、それをこえて世界のあり方を広く全体として展望する必要はなかった。そのような「未開」の認識は、近代科学が発達した先進諸社会においても、今日なお人びとの日常生活においては一定の有効性をもっている。少なくとも、人びとは自分の日常生活を過ごすために、大層な科学的認識を必要としていない。
たとえば、ガリレオ・ガリレイが異端裁判にかけられるきっかけとなった地動説は、その後の研究で科学的な定説となり、日常生活においてもほとんど常識となった。だが今日でも、「日は昇り、日は沈む」という天動説的な言い方のほうが、私たちの日常的な感覚には合っている。人間が立っている大地は、じつは地球という球体の惑星であり、それが太陽のまわりを公転しつつ自転することによって、地球上のある定点から見た太陽は、東の地平線から見えるようになり、頭上に上がって、やがて西の地平線に消えていく。これは小学校で習う理科の知識だが、大人になっても私たちは「日は昇り、日は沈む」と言いつづけている。だからこそ、与謝蕪村の「菜の花や 月は東に 日は西に」という有名な俳句は、今日でも私たちに文学的な感興を呼び起こすのである。
人びとの世界秩序の認識は、歴史的には呪術的・宗教的なかたちで形成されていた。世界のさまざまな形状や運動を統一的に認識し、説明しようとするとき、その認識の真理の源泉となるのは、霊のような呪術的な力であったり、神のような超越的な力であったりした。呪術的・宗教的な世界認識は、今日の科学的認識とは相容れない部分が多いが、それなりに整合的なかたちで、世界秩序のあり方を体系化し、説明してきた。呪術や宗教は、無前提に信じるべき絶対的な真理の源泉を措定することによって、認識の正しさを保証しようとしてきた。マックス・ヴェーバーによれば、そのような世界観に支配された社会は「呪術の園」であり、近代における社会の発展の普遍的な方向は科学による「呪術からの解放」にむかうはずだった。しかし興味深いことに、21世紀の今日になっても、科学がもっとも発達しているはずのアメリカ社会でさえ、他方でキリスト教の根本主義(ファンダメンタリズム)が根強く残り、学校で進化論を教えることに強い拒否反応を示している。世界を創造したのは神であり、ダーウィンが主張したように猿から人間が派生してきたというような進化論は、聖書の教えに反している、というわけである。
それでも歴史的には、呪術や宗教とは異なる世界認識のための知識の体系が、しだいに形成されるようになった。それは、世界のさまざまな現象を事実として認識し、その事実のありようを厳密に記述・説明しようとするものだった。またそれは、絶対的な真理の源泉を措定することなく、人びとの認識のすり合わせによって、より確実な知識に近づいていこうとするものだった。世界についてのさまざまな認識は、正しいと思われれば明確な言明として人びとに提示され、それを受けて言明がほんとうに正しいかどうかの検証が絶えず行われることになった。言明は、検証に耐えているあいだは真とみなされ、反証が成り立てば真ではないとみなされる。つまり、世界認識による知識の体系は、絶対的な真理としてうち立てられるものではなく、絶えず再生産と更新をくり返していくものになった。
世界についての認識は、もちろん人間の能動的な観察(観測)なしには成り立たない。だが、存在する世界がその観察にどのように映るのかが問題なのであって、観察が世界をどのように作るのかが問題なのではない。その意味で、世界の観察によって得られる認識は、観察者としての人間の側ではなく、環境としての世界の側の選択とみなされる。したがってそれは、人間の側からは行為ではなく体験だということになる。世界認識についてのコミュニケーションでは、送り手がみずからの体験として得られた認識を伝達すると、受け手はそれをみずからの世界認識の前提、つまり体験の前提にすることができる。つまり受け手は、送り手の体験としての世界認識を、みずからの体験としての世界認識に接続することによって、認識が真であるか否かを検証することができる。そのように、認識の言明が真であるか否かに焦点を合わせたコミュニケーションが継続的に行われるようになって、科学(より広い表現をすると学術)が成立する。科学における象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアが、真理である。
真理は、もっぱら認識の言明が真であるか否かというかたちで選択を条件づける(選択のあり方を限定する)。真とされる知識は、共有され、蓄積され、体系化されていく。だが、この真理にかかわるコミュニケーションには、だれでも手軽に参加できるわけではない。参加するためには、前提として、世界認識のための観察(観測)の技術や装置を適切にあつかうことができなければならないし、従来の真とされる知識について学び、そもそもどのようなテーマについて議論が行われているかを理解することができなければならない。科学は、専門性の高いコミュニケーション領域であり、その専門家は科学者と呼ばれる。科学のコミュニケーションの主な公式の様式は、学術雑誌や学術書のかたちで出版するか、学会で口頭発表するかである。その背後には、日常的な研究活動において、他人の論文を読んだり、研究仲間と討論したりする、さまざまなコミュニケーションがある。そのすべてが、真理というメディアによって接続されていくことによって、しだいに科学という社会システムが成立してくるのである。
愛:親密関係におけるメディア

愛については、古来さまざまな分類や議論が行われてきた。神の愛から人類愛、兄弟愛、そしてただ一人の相手に対する愛まで、また純粋に精神的な愛から性愛まで、さまざまなものが愛と呼ばれてきた。これらはいずれも広い意味での愛にちがいないが、ルーマンが象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアとしての愛を論じるさいに焦点を合わせているのは、西洋で情熱恋愛からロマンティック・ラブへと展開した特殊な形態の愛の観念である。古くは宮廷風恋愛に端を発するこの愛の観念は、中世以降の西洋社会では、おもに宮廷社会を構成する王侯貴族のあいだで洗練され、やがて興隆するブルジョアジーにも広く流布していくと同時に、ロマンティック・ラブへの変容とともに恋愛が婚姻の前提条件とされるようになっていった。余談ながら、経済学史家のゾンバルトによれば、もともと宮廷で行われていた恋愛では、女性が贅沢に身を飾ったり、男性が贅沢な贈り物をしたりするのが通例だったが、ブルジョアジーがそれをモデルとして模倣することによって奢侈が広まり、資本主義の発達に一役買ったとされている(Sombart, 1912=2000)。
では、愛はどのような意味で象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアといえるのだろうか。理論的な定義によれば、愛は他者の体験と自我の行為を接続するためのメディアである。ルーマンは「愛においては、真理および価値という匿名の世界を超えて、自分の世界観に同意と指示とが与えられうるものと仮定される」と述べている(Luhmann, 1997=2009, p.387)。問題となるのは、科学における普遍的な(その意味で特定の個人に依存しない匿名の)世界認識ではなく、まさに特定の個人の世界観であり、その個人の特別で個別の体験である。この体験は、二者関係のなかで伝達される。送り手=他者の体験は、受け手=自我によって受け入れられ、受け手は自分が送り手の体験を受け入れたことを、すこし大げさにいえば送り手の存在全体を受け入れたことを、自分の行為によって示すことによって、はじめて愛のコミュニケーションが成立する。愛するとは、たんなる心情の問題ではなく、相手の体験を受けとめ、そのことを行為によって目に見えるかたちで示すことであり、愛されるとは、相手が自分の体験を受け入れたことを、行為によって目に見えるかたちで示すことである。ルーマンは講義のなかで、「愛される者は、その内面を察知してもらえればよく、またそうでなければなりませんし、愛する者は、相手の気持ちに先まわりして応えるようにしなければなりません」「愛する者は、相手からやってくるものに対して、それがすばらしいものであることを行為をもって示さなければならないのです」(Luhmann, 2005=2009, pp.202-203)と述べている。送り手は、自分が愛されているか否かを、自分勝手な想像ではなく(それは内面の願望や妄想にすぎない)、受け手の行為によってはじめて知ることとなる。
しかし、このような議論は、愛される者=送り手と愛する者=受け手のあいだに、大きな非対称性を前提にしているように思われる。ジェンダー論的なことは何も明示的に述べられていないが、愛される者は女性、愛する者は男性という暗黙の前提があるようにも思われる。これは理由のないことではない。そもそも情熱恋愛やロマンティック・ラブの源流になったとされる中世の宮廷風恋愛では、その原型は貴婦人(とくに君主の妻)に捧げる従者としての騎士の純愛であり、その特徴は女性に対する男性の崇拝と奉仕だった。この関係は、現実には性的要素がふくまれることが多く、現代風にいえば不倫関係という身も蓋もないものになるのだが、文学的には精神性が重視され、理想化されて至上の愛(fin'amour)という観念に結実した。宮廷風恋愛は、上流階層である王侯貴族が集う宮廷やサロンでしだいに洗練され、言語表現も行動様式も品位と礼儀をそなえたものになっていった。
この洗練の形式性を象徴するのが、社交という社会関係である。これについては、ジンメルが古典的な考察を展開しており、そのなかにコケットリについての議論がある(Simmel, 1917=1979, p.81以下を参照)。ジンメルによれば、社交とは、社会化つまり相互作用によって社会を形成する過程から、現実的な目的内容を取り去って、遊戯的(ゲーム的)な形式へと純化したものであり、そのなかでエロティシズムが遊戯形式となったものがコケットリである。ジンメルは、「女性のコケットリの本質は、与えることを仄めかすかと思えば、拒むことを仄めかすことで刺戟し、一方、男性を惹きつけはするものの、決心させるところまで行かず、他方、避けはするものの、すべての望みを奪いはしないという点にある」のに対して、「男性が、この自由に揺れ動く遊戯、エロティシズムにおける或る決定的なものがただ遠いシンボルのように仄見える遊戯、それ以上のものを求めない時、また、男性が、欲望や欲望への警戒を離れて、あの仄めかすもの、あの仮初のものの魅力を感じるようになった時、その時に漸く社交が始まる」と述べている。コケットリにおいて、男女の非対称性は、その形式性のせいでいっそうきわだったものになっているように思われる。
このような恋愛遊戯の形式性に対して、まさに現実的な内容こそがすべてと強調したのが情熱恋愛であり、ロマンティック・ラブである。それは、一方では婚姻と結びついて、家族形成の不可欠の契機となっていき、他方ではもっぱら受動的に愛される者として位置づけられてきた女性に能動性を与え、愛される者と愛する者の非対称性の解消へとむかっていく。それと同時に、愛にもとづく親密関係は、個別の相互行為の関係として全体社会から分化していき、私的な関係として全体社会の干渉から離れていく。婚姻や家族形成は、かつては全体社会におけるさまざまな制度と結びついていたが、愛の親密関係と結びつくことによって、しだいに制度のしがらみを離れて私的なものになっていく。そうした現代的状況のなかで、ルーマンのいう象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアとしての愛が、今日どのような様態をとっているのか、あるいはそもそもメディアとして機能しつづけているのかは、ルーマンの著書のタイトルでもある「情熱としての愛」以後の問題として、解明していくべきテーマだろう。
貨幣:経済におけるメディア

貨幣は、日常的な感覚で考えると、メディアであることをもっとも納得しやすいものかもしれない。われわれの日々の生活は、完全な自給自足と贈与だけからなるような社会をもはや想像できないほどに経済的交換に覆い尽くされている。その経済的交換を媒介し、経済的な価値を表示するのが、貨幣である。ある人が他の人から何らかの財やサービスを手に入れたとしたら、その人はお金を払ったはずだと考えられるし、財やサービスを他の人に提供したとしたら、その人はお金をもらったはずだと考えられる。もしそこにまったくお金がからまなければ、その財やサービスは純粋な贈り物としてやりとりされたか、あるいは盗み取られたかであろう。また、日常生活における貨幣の主要形態は、比較的最近までは現金(キャッシュ)、つまり紙幣と硬貨だったが、いわゆるキャッシュレス化が進み、クレジットカードはいうに及ばず、スマートフォンや交通系ICカードなどによる電子決済ができるようになってきた。貨幣は、財布や金庫に入っている実物の現金である必要がなく、銀行口座を介してやりとりされる数字でよくなってきた。
日常的な感覚でとらえた現象としての貨幣は、だいたい以上のようなものだが、ルーマンは、それをどのような意味で象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアと考えるのだろうか。先に見たように、理論的には、貨幣は他者の行為と自己の体験を接続するメディアとして位置づけられている。より具体的には、ルーマンは、「物やサービスを売り買いするということ自体は、経済の貨幣化がもたらした驚くべき事態というわけではありません。むしろ驚くべきは、他の人は誰であれ、売り手がお金を払ってもらっているのだからという理由だけで、それをただ傍観するということです」(Luhmann, 2005=2009, p.204)と述べている。今日の貨幣経済における交換の様態はあまりにあたりまえに思えることなので、どこが驚くべき点なのか、直観的にはわかりにくい。だが、純粋な交換ではなく、貨幣がからまない贈与であれば、人びとは贈られた人をうらやましく思ったり、贈った人に自分もせがんだりすることがありうるだろう。また、盗み取られた場合には、盗んだ人を非難して罰を与えようとしたり、盗まれた人に同情して助けようとしたりするかもしれない。それが、純粋な経済的交換の場合には、貨幣によって買われるものが豪邸であろうと宝飾品や高級車であろうと(つまり希少性の高い財)、他の人はうらやましく思ったとしても、くだらない浪費だと蔑んだとしても、指をくわえて傍観するしかない。財やサービスを売り買いするという他者の行為を、自我はあるがままに、正当な代価を支払った取引として傍観するという体験として受けとめる、という意味で、そこに介在する貨幣は、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアなのである。
この説明は、コミュニケーションの送り手と受け手を、通常考えられるような売り手と買い手とはしない点に特徴がある。貨幣の機能を経済的交換の媒介だと考えれば、コミュニケーションの当事者としては売り手と買い手が問題となるわけだが、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアとして見れば、むしろ第三者が交換に一切干渉しないこと、交換を正当なものとして淡々と認めることが重要である。そうしてはじめて、経済的な交換ないし取引は、財やサービスにまつわるさまざまな生活世界的要素を離れて、あるいは贈与や盗みとは区別されて、純粋に経済的なものになり、その分だけ普遍的になると同時に限定的なものになる。日常的な買い物の場面を考えると、下町情緒あふれる商店街では、店の人と客が顔なじみだと、世間話の一つもしながら買い物を行い、なじみのよしみで割引やおまけがついたりすることもある。そこにはまだ、下町の生活世界的な人間関係(いわゆる人情味あふれる関係)が色濃くにじんでいる。それが、大手のスーパーマーケットやコンビニエンスストアになると、もっと淡々とレジで代金を支払うし(最近はセルフレジも増えてきた)、ネットの通信販売になると、画面を何回かクリックするだけで買い物ができるだけでなく、そもそも第三者はそれを見てさえいない。それは、まったく味気ないが、きわめて効率的で合理的な交換の様態である。
「金さえあれば何でも買える」という言葉がある。たしかに、経済的な商品としての財やサービスであれば、そのかぎりにおいて(つまり限定的に)、どんな商品でも(つまり普遍的に)買うことができるだろう。しかし、貨幣のもつ限定性は、貨幣が全体社会のなかのあらゆる領域、あらゆる場面、あらゆる状況において、万能の効力をもつことを禁じている。たとえば、金で地位や名誉を買うことは、現実にはときどき行われているとしても、金で買われるような地位や名誉の正統性が疑われたり、金で買う人の品格が疑われたりする。第三者は、たんなる傍観者ではなくなり、そのような他者の行為を非難することが正当だと考えるようになる。また、しばしば問題となる政治と金の関係を考えると、金にものを言わせて党派を牛耳り、政治的な意思決定を意のままにすることは、正当な政治的行為だとはみなされない。現代政治において、政治活動に一切金がかからないなどということはありえないが、支出される金はすべて正当な経費として計上しなければならず、二重帳簿で裏金作りをすれば粉飾として告発されるし、収入についても、税金でまかなわれる分や正当な献金によるもの以外は賄賂とみなされる。
「金さえあれば何でも買える」という言葉は、経済以外の領域に貨幣をもちこむという問題を示すだけでなく、あらゆるものを経済の領域に引き込んで商品化し、貨幣による交換の対象とするという問題も示している。性の商品化は、つとに非難の対象になっているが、その理由は、性という人間の存在の根源にかかわる領域から発するはずの性的行動をたんなる経済的交換の対象としているからであり、人間(とりわけ女性)の尊厳を損ね、疎外するとみなされるからである。人間のさまざまな感情でさえ、たとえばケア労働においてケアされる人に優しく接したり、接客において笑顔で客に接したりすることが要求される感情労働は、それが労働であるかぎり、資本主義においては商品化されたものであり、労働の代価としての賃金と交換されるものになる。人間の感情という、これまた存在の根源にかかわる要素が、商品となることによって当の人間を疎外する。教育もまた、「教育サービス」とみなされるかぎりにおいて商品化され、サービスとして提供される教育の質は授業料という代価に値するか、つまり経済的交換として成り立つだけの価値をもっているかが問題となり、教育学者は顔をしかめることだろう。
このように、貨幣は社会のなかで絶大な影響力をもち、あらゆる領域に浸透していこうとする傾向ももっている。はたして、ルーマンのいうような象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアとしての貨幣という概念が、このような状況に対してどこまで分析力を発揮できるのか、あるいは現実を無視したある種の綺麗事の建て前にすぎないのかは、今後の研究課題であろう。
権力:政治におけるメディア

権力は、貨幣とならんで、日常的な感覚で理解しやすい現象かもしれない。命令する者と、それに服従する者がいる。服従者がすなおに命令に従えば、権力はスムーズに行使されたことになるが、服従者が命令に従わず、場合によっては抵抗さえ示す場合でも、命令者が十分なサンクションを与える可能性、たとえば物理的に強制したり組織から追放したりする権限をもっていて、その行使を示唆することによって服従者を脅すことができれば、服従者はサンクションの不利益を考えて、嫌々ながらも命令に従う可能性が高い。「「権力」とは、或る社会的関係の内部で抵抗を排してまで自己の意志を貫徹するすべての可能性を意味し、この可能性が何に基づくかは問うところではない」(Weber, 1912=1972, p.86)というマックス・ヴェーバーの有名な権力の定義は、まさにこのような関係をさしている。
権力を象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアと見る場合、問題となるのは他者の行為と自我の行為の接続である。たんなる接続であれば、多様な他者との関係のなかで社会生活を営む私たちの日常は、つねに他者の行為に自分の行為を接続することで成り立っているということができる。他者の行為を前提に自分の行為を考えなければならないかぎりにおいて、何でも好きなようにする、つまり自分の自由意志だけで行為を選択することはできない。ドライブ好きだったといわれるルーマンが例にあげているように、前の車がブレーキをかければ、自分もブレーキをかけなければならない。相手がドアを開けるように鍵を渡せば、自分は無視して鍵が落ちるのを見ているのではなく、手を出して受けとらなければならない。日常生活のほとんどの場面は、このような何気ない行為の接続によって成り立っている。そのなかで権力関係をきわだたせるのは、「他者の行為が、自我の行為に関する決定というかたちで生じており、それに従うよう要求されている」(Luhmann, 1997=2009, p.399)という条件である。つまり他者が、自我が特定の範囲の行為を選択するような決定を選択するのである。
このように権力を定義する場合に、典型的に頭に浮かぶのは、大臣が自分の管轄する官庁に政策立案や政策遂行の指示を出したり、会社や役所で上司が部下に仕事の命令を出したりするケースだろう。しかし、これまでの定義だけでは、いじめっ子が他の子どもに力ずくで言うことを聞かせたり、果てはギャングや暴力団が一般人に「家族がどうなってもいいのか」と脅しをかけて言うことを聞かせたりするケースも、権力関係から排除することができない。だが、これらのケースは、完全に法律で違法と規定されてはいないとしても、社会的に望ましくないものとされており、正当な権力行使とはみなされない。これに対して、大臣や上司は、職務上の権限として命令権を付与されており、そのかぎりにおいて正当な権力行使をしているとみなされる。とはいえ、大臣や上司は恣意的にどんな決定をしてもよいわけではない。職務上の権限はつねに限定的であり、権限を越えた、あるいは権限から外れた命令や指示は、逸脱行為であって、正当とはみなされない。
歴史的には、絶大な権力をもつ支配者が、権力のおよぶ範囲の人びとにみずからの決定を恣意的に押しつけ、力ずくで服従させることもあった。それに対して、支配される側も力で対抗し、過激であれば支配者を打倒し、穏健であれば支配者の恣意をできるだけ制限するようにしてきた。たとえばイギリスでは、13世紀のマグナカルタ(大憲章)によって、貴族や教会の権利を保障するかたちで国王の権力が制限され、17世紀の権利章典によって、議会の権利を保障することをとおして国民の権利を保障するかたちで国王の権力が制限されるなど、長い歴史のなかで支配者である国王の権力がしだいに制限されてきた。このような過程は、最初は抵抗する服従者の力による制限だったかもしれないが、しだいに法そのものによる制限へと展開していった。それは、人治から法治への転換といってもよい。マックス・ヴェーバーの有名な支配の3類型のなかの合法的支配は、その正統性が「制定された諸秩序の合法性と、これらの秩序によって支配の行使の任務を与えられた者の命令権の合法性とに対する、信仰にもとづいたもの」(Weber, 1912=1970, p.10)であり、まさにこの法治を意味している。ルーマンが権力の法的コード化と呼ぶものも同様であり、それによって生み出されたのが法の支配、あるいは法治国家という概念である。
このように見てくると、広い意味での権力現象はかなり広い領域で見られるが、法的にコード化された形態をとる権力現象は、全体社会のレベルではもっぱら政治の領域に限られるものとなり、組織のレベルでは国家や地方自治体の官公庁で見られるものとなる。ヴェーバーは、合法的支配の典型として官僚制の分析を行い、官僚制組織における命令や指示の系統とその権限が形式的に厳密かつ明確にさだめられることによって、組織にかかわる人びとの恣意(つまり不確定な自由度)を排して、組織の作動を十分に計算できるものにすることができると考えた。ヴェーバーが官僚制の特徴の一つとして挙げている非人格性とは、人間の恣意的な裁量ではなく、法や規則によって、組織の作動の仕方をさだめることである。つまり権力を行使する人が交代しても、その人の人格によって裁量の範囲が恣意的に変化することがないようにするのである。ルーマンの用語をもちいれば、他者の決定によって開かれる自我の行為の選択の可能性の地平が、恣意的なゆらぎのないように一意に規定される、ということになる。しかし、官僚制に典型的に見られるような合法的支配は、どのように決定すべきかという形式は整えても、そもそも何を決定すべきかという内容にはタッチしない。人びとの行為を拘束する権力による決定の内容の妥当性や望ましさを評価するには、合法性という支配の正統性とは異なる基準が必要になる。権力者の恣意的な鶴の一声で決まらないとしたら、人びとが持つであろう多様な意見や願望をどのようなかたちで集合的決定につなげていくのかということが、合法的支配における政治の課題であろう。
象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアと社会の意味領域の分化

3回にわたって、コミュニケーションにおける非蓋然性の克服がどのようなかたちで行われ、その克服のされ方がどのように発展してきたかを見てきた。言語によってコミュニケーションにおける理解はより繊細で複雑なものになり、文字から印刷をへて電子メディアにいたる各種のメディアの発達によって伝達の範囲は飛躍的に広がり、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの発達によって、大規模で複雑な社会におけるコミュニケーションの成功が担保されるようになってきた。最後の象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアは、理論的に見て4つの異なる接続様式に分かれていると同時に、それぞれが異なる意味領域における限定的な働きをするようになってきた。このことは、ルーマンのいう全体社会の機能分化と結びついている。次回は、意味領域の分化としての機能分化について論じることにしよう。
参考文献
Giddens, Anthony, 1990, The Consequences of Modernity, Polity Press.(松尾精文・小幡正敏訳『近代とはいかなる時代か? モダニティの帰結』而立書房、1993年)
Habermas, Jürgen, 1990, Strukturwandel der Öffentlichkeit Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Suhrkamp Verlag.(細谷貞雄・山田正行訳『公共性の構造転換 市民社会の一カテゴリーについての探究』未來社、1994年)
Habermas, Jürgen, 2022, Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik, Suhrkamp Verlag.
Luhmann, Niklas, 1996, Die Realität der Massenmedien, Westdeutscher Verlag.(林香里訳『マスメディアのリアリティ』木鐸社、2005年)
Luhmann, Niklas, 1997, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp Verlag.(馬場靖雄・赤堀三郎・菅原謙・高橋徹訳『社会の社会』1・2、法政大学出版局、2009年)
Seeliger, Martin/Sevignani, Sebastian (Hrsg.), 2021, Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit? Leviathan Sonderband 37, Nomos Verlag.