
第5回 コミュニケーションのメディア(1)
-

徳安 彰AKIRA TOKUYASU
法政大学社会学部教授東京大学文学部社会学科卒業。同大学院社会学研究科博士課程修了。法政大学社会学部専任講師、同助教授、ビーレフェルト大学客員研究員、法政大学社会学部教授、法政大学社会学部学部長を歴任。共著に『社会理論の再興』(ミネルヴァ書房)、『理論社会学の可能性』(新曜社)など。
第4回は、コミュニケーションに焦点を合わせて、古典的な情報理論のコミュニケーション観と対比しながら、ルーマンの社会システム理論のコミュニケーション観の特徴を説明した。その特徴は、コミュニケーションとは意味の正確な伝達または共有ではなく、ノイズや偶発性に満ちた絶えざる意味構成の過程である、ということだった。そのために、ダブル・コンティンジェンシーとブラックボックスという2つの概念をもちいて、コミュニケーションの成り立ちがたさにも言及した。ただ、この点を過剰に強調してしまうと、コミュニケーションは、相手が理解しようが誤解しようがおかまいなしに、各自がてんでに勝手な発信や受信を行っているだけになってしまう。つまり、意味構成の安定性がまったく保証されなくなってしまう。それにもかかわらず、現実の社会システムでは、コミュニケーションがある程度スムースに進行し、一定の秩序の安定性が保たれているように思われるのはなぜか。そこにどのようなメカニズムが介在しているのか。これが今回の出発点となる問いである。
コミュニケーションの非蓋然性

われわれは日頃、社会の中でさまざまな他者とさまざまなコミュニケーションを行って生きている。その中には、細かく神経を使って慎重かつ入念に行わなければならないコミュニケーションが、たしかにある。絶対に成功させたい商談、有利な条件でまとめたい交渉、渋る相手の説得、フラれることに怯えながらの告白など、コミュニケーションの成功が強く求められるにもかかわらず、失敗のリスクが大きい状況におかれることは少なくない。また実際、失敗して痛い目を見ることもある。
だが他方で、ほとんど神経を使わないばかりか、コミュニケーションであること自体を意識しないのにスムースにいくコミュニケーションの方が、日常生活でははるかに多い。街の商店街の八百屋や魚屋なら世間話のひとつもしながら買い物をするかもしれないが、スーパーやコンビニでは「これください」「ありがとうございます」くらいの会話があればまだましで、無言のままレジで表示された金額を支払って、品物を受けとって終わりということも多い。会社の仕事でも、上司の「あの件どうなった」という質問に、部下が「うまく行きました」と答えて、話が通じることも多い。何も知らない第三者が聞けば、何の話だかさっぱりわからないが、仕事の文脈を共有している上司と部下にとっては、忙しいなかでのやり取りとしてはそれで十分である。最近では、仕事上のメールのやり取りは組織内だけでなく世界中のクライアントと行うことができるし、導入当初はぎこちなかったリモートのオンライン会議でさえ、すこし慣れてくればスムースに議事が進む。
問題は、内容的、技術的に難しいコミュニケーションにあるのではない。むしろ問題は、スムースで簡単に思えるコミュニケーションが、なぜそのようにスムースで簡単にうまくいっているのかという点にある。この問題に対して、おたがい人間どうしなのだから分かりあえて当然だ、などと答えてはならない。また、人間は社会を形成しないと一人では生きていけないからコミュニケーションが必要なのは当然だ、というような答えも適切とはいえない。第4回で考察したように、社会システム理論のコミュニケーション観によれば、コミュニケーションはつねに大きな非蓋然性、つまり成り立ちがたさを抱えているからである。ルーマンは、その非蓋然性のハードルを3つに分けている(Luhmann, 1984=2020, 上p.214-215)。
第一は「理解」というハードルである。コミュニケーションが成立したといえるのは、どのような場合だろうか。自分が考えたことや感じたことを他者に理解してもらう、あるいは他者が考えたことや感じたことを自分が理解する、というのはそう簡単なことではない。個人の主観的な意味構成を行う意識を閉じたオートポイエティック・システムとみなすと、その個人の意識は、理論的に考えて、他の個人の意識に直接伝達されることはありえない。ブラックボックスの概念をもちいるならば、個人の主観的に構成された意味の表出は、表情や身振りにせよ口頭で発せられる音声にせよ、他者にとってはブラックボックスからの出力にすぎず、その出力の意味するところは、他者がみずから新たに構成しなければならない。そのかぎりにおいて、ある個人が構成する意味を他者がそのまま正確に理解する可能性は、理論的にはまったく保証されず、むしろつねに大きな誤解の可能性がつきまとっている。そのため、コミュニケーションが継続する蓋然性が低くなる。これが「理解」という第一の非蓋然性のハードルである。
第二の非蓋然性のハードルは「到達」である。自己と他者が面と向かってやり取りをする場合には、到達の問題はほとんど起こらない。工事現場の騒音や大音量のライブ会場など、かなり特殊な環境でないかぎり、声が聞こえない、届かないということはありえない。また、相手がよほど他のことに気を取られて、心ここに在らずの状態でないかぎり、話がまったく耳に入らないということも起こらない。だが、対面的でリアルタイムの状況から一歩進んで、その場にいない人(あるいは人びと)に何かを伝えなければならなくなると、コミュニケーションは格段に難しくなる。対面での口頭のやり取りは、ルーマンがよく使う言い回しでは、文字どおり発生しては次の瞬間に消えていく出来事なので、そのままではその場にいない人には到達しない。時間差で相手に到達させる手段、あるいはリアルタイムで遠隔の相手に到達させる手段がなければ、コミュニケーションが伝わることはない。また数多くの人びとに伝達するのも難しい。人びとの多くは、大規模集会のような場合を除けばその場にいないし、たいていは日常生活の中で他のことをしているので、そもそもコミュニケーションに注意を向けてもらうことさえ難しい。これが「到達」という第二の非蓋然性のハードルである。
第三の非蓋然性のハードルは「成功」である。コミュニケーションが、首尾よく目的とする相手に到達し、その意味が理解されたとしても、相手がそれを受け入れるかどうかはわからない。他者の申し出を断る、他者の主張を否定する、他者の指示に従わない、他者の告白につれない返事をするといったことは、たしかにコミュニケーションにおいてしばしば見られる対応である。これが、他者が「それならもういい」といって、ただちにコミュニケーションの終了につながるのであれば、コミュニケーションは失敗に終わるだろう。場合によっては、おたがいの関係そのものの解消にまで行き着くこともあるだろう。だが、他者はその対応を前提にして、別の申し出をしたり、否定の根拠を問いただしたり、指示に従わないとどうなるか脅しをかけたり、つれない返事にまだ一縷の望みをかけたりしながら、コミュニケーションが継続することも大いにありうる。とはいえ一般的には、コミュニケーションの成功とは、相手から伝えられた意味を受け入れ、それに従うことだと考えることができるだろう。他者から伝えられた意味に対して、自分がそれを受けとめて応答するかどうかが重要である。他者から伝えられた意味は偶発性をともなう選択であり、それを自分のつぎの行動の前提として引き受け、自分の(これまた偶発性をともなう)選択をすることが、コミュニケーションの成功である。ルーマン自身の言葉によれば、「コミュニケーションの成功とは、複数の選択を成功裏にカップリングするということなのである」(Luhmann, 1984=2020, 上p.214-215)。これが「成功」という第三の非蓋然性のハードルである。
このように見てくると、日常的になにごともないかのようにスムースに進行するコミュニケーションは、なぜそのようにスムースに進行するのか、という問いに対する答えの道筋が見えてくる。それは、非蓋然性の3つのハードルを越えるための、なんらかのメカニズムが存在するからにほかならない。そのメカニズムは、社会文化的な進化とともに発達し、またさらなる社会文化的な進化を促進している。ルーマンは、「今述べてきたコミュニケーションの破断箇所に据えられて、蓋然性の低い事柄を蓋然性の高い事柄へと変換するために働く進化上の諸成果を、われわれはメディアと呼ぶことにしよう」(Luhmann, 1984=2020, 上p.217)と述べている。そのように、コミュニケーションの蓋然性を高めるメディアは、われわれの日常生活の自明の、あるいは暗黙の前提となっており、だからこそ多くのコミュニケーションが当然のようにスムースに進行し、成功するのである。
ここで一つ注釈をつけておこう。第4回で見たように、ルーマンが考えるコミュニケーションは、情報、伝達、理解という3つの選択の統一体だった。そして、受け手が送り手からのメッセージを理解して、それを受け入れるのか拒むのかという選択は、それ自体としてはコミュニケーションではなく、コミュニケーションによって開かれる行動の選択とされていた。そうなると、ここで説明した3つ非蓋然性との対応関係がすこしややこしくなる。最初の情報という選択にかんする非蓋然性はないのか、またなぜそれ自体としてはコミュニケーションではないとされる受容/拒絶がコミュニケーションの非蓋然性として重要なのか、という疑問が湧いてくる。その答えは、個々の人間の心理システムの内部における意味構成とは異なり、コミュニケーションが個々の人間のあいだに成立する意味構成つまり社会的な意味構成だから、ということになるだろう。そう考えると、ルーマンが考えた3つの非蓋然性は、いずれも心理システム内部の過程ではなくコミュニケーションの過程にかかわるものである。理解の非蓋然性とは、コミュニケーションの選択のなかの送り手における情報と受け手における理解を意味構成という点で媒介することの非蓋然性、到達の非蓋然性とは、コミュニケーションの伝達において情報が送り手から受け手に届いて理解にいたるための空間や時間を媒介することの非蓋然性、成功の非蓋然性とは、コミュニケーションの送り手の選択を受け手の選択に接続させて、さらにつぎの接続を進めることができるように媒介することの非蓋然性である。だからこそ、これらの非蓋然性の克服のためには、媒介のメカニズムであるメディアが必要となる。
つぎに、そのメディアを非蓋然性の3つのハードルに対応させながら見ていこう。
理解のメディア:言語

われわれは、日常的に言語を使ってものを考えている。また、日常的に言語を使ってコミュニケーションを行っている。意識の中で意味が構成される心理システムにおいても、コミュニケーションの中で意味が構成される社会システムにおいても、言語が意味構成の中心的な役割を担っている。もちろん、言葉にならない、あるいは言葉では表現しきれない、喜び、悲しみ、苦しみ、緊張、忘我、恍惚など、さまざまな意識の状態をわれわれは日々経験しているし、それを逐一すべて言葉にして自分の経験を反芻しているわけではない。しかし、それを自分で理解しようとすると、言語を用いるしかないし、他者に伝えようとするなら、なおさら言語で表現するしかない。笑ったり、泣いたり、怒ったりという表情や身振りによる表現は、たしかに自分が一定の感情に動かされていることを他者に伝えるかもしれないが、言語なしでは多くを伝えることは難しい。思考になればなおさらで、思考が複雑になるほど、頭の中で考えていることを言語なしで他者に伝えることはほぼ不可能になる。
くり返しになるが、社会システム理論のコミュニケーション観にもとづけば、個人の心理システムは作動上閉じたオートポイエティック・システムだから、心理システムが構成した意味は、そのままでは他者に直接伝わることはない。その意味が、なんらかのかたちで他者が認知できるように表現され、伝達されなければならない。それによってはじめて、他者はその人の認識、思考、感情などを受けとめて、理解することができるようになる。そこにコミュニケーションが成立するのである。このとき、人と人のコミュニケーションを文字どおり媒介するのがメディアであり、メディアの発達あるいは進化という観点から見たとき、もっとも重要な最初のメディアが言語である。
ここでいうメディアとしての言語は、まず音声言語として始まったと考えられている。われわれは、日常的に口頭でのコミュニケーションを行っており、そこで音声言語を用いているわけだが、すでに文字言語が社会に定着してから長い歴史を経ている現代において、文字のない時代、あるいは文字のない社会における、音声言語とそれを用いた口頭コミュニケーションのあり方を正しく理解するのは容易ではない。言語を扱う人文・社会科学の諸領域における研究も、長いあいだ、すでに読み書きのできる人の書きことばと話しことばの比較が中心だったのであり、書くことをまったく知らない人びとの声の文化(orality)に注目が集まるようになったのは、それほど古いことではない(Ong, 1982=1991, p.21)。
長いあいだの進化の過程で、人類は多様な音を発する声帯を持つようになり、その発声・発音の能力を用いて、弁別可能な音素の組み合わせによって語、語の組み合わせによる句(フレーズ)、そして文を構成することができるようになった。詳しい議論は言語学の音韻論にゆずるとして、ここで重要なのは、動物の比較的単純な鳴き声、唸り声、吠え声などをはるかに越えた、きわめて複雑な音声表現ができるようになったということ、またその音声表現が記号となってなんらかの意味を指し示すようになったということである。さらにいえば、この指し示される意味は、世界のなかの具体的な特定の空間・時間に存在する個別の事物・事象からしだいに抽象化されて、一般的なものになっていく。たとえば、犬を指し示す語は、イヌ(日本語)、dog(英語)、Hund(ドイツ語)、chien(フランス語)など、言語によってさまざまな音素の組み合わせによって表現されるが、いずれも具体的な特定の犬だけを指し示すのではなく、犬一般を指し示すことができ、そのたびに同じ語が反復して用いられる。こうして、記号としての言語における指し示すものと指し示されるものの区別は、日々刻々と過ぎていく生の現実から隔離され、「使用の文脈に左右されることなく安定的に保たれるようになる」(Luhmann, 1997=2009, 1p.231)。人類は、安定的に反復して用いることのできる、また組み合わせによって複雑な意味を指し示すことのできるメディアを手にしたのである。
さて、言語の体系そのものは、比較的長いあいだ安定的に使用することができるが、言語によるコミュニケーションそのものは、とくにオングが声の文化と呼んだ音声言語の時代には、口頭から発せられ、聞かれるやいなや消えていくものだった(Ong, 1982=1991, p.73)。また、「音声言語は聴覚と結びついている。したがって視覚とは異なり、コミュニケーションは時間的に順次化されざるをえなくなる。つまり順次性による秩序を確立せざるをえない」(Luhmann, 1997=2009, 1p.236)。このような特性をもつ音声言語は、表現の様式ばかりでなく思考様式をも決定している。たちどころに消えていく音声言語が指し示す内容を記憶するためには、一定の韻律にのったきまり文句や慣用表現が重要であり、それによって人びとは表現された意味内容をくり返し暗誦し、記憶・想起することが容易になった(Ong, 1982=1991, pp.76-82, 124-145)。
オングはさらに声の文化にもとづく思考と表現の特徴を挙げている(Ong, 1982=1991, pp.82-124)。
⑴累加的:物語における文が、「そして」を多用してどんどん付け加えられていく。複雑な前後関係を示す構文は用いられない。
⑵累積的:きまり文句による記憶と緊密に結びつき、「兵士」ではなく「勇敢な兵士」、「王女」ではなく「美しい王女」などと、表現の構成要素が寄り集まってひとまとまりになる。
⑶冗長ないし多弁的:冗長なくり返しは、たんなる記憶のためだけでなく、話し手と聞き手の両方を、話の本筋からはずれないように引きとどめておく効果がある。
⑷保守的ないし伝統主義的:概念化された知識は、声に出してくり返していないと、すぐに消えてしまうから、たいへんなエネルギーを投入して、何度もくり返さなければならないので、精神が伝統主義的で保守的になる。
⑸人間的な生活世界への密着:すべての知識を、人間的な生活世界に多少とも密接に関係づけるようなしかたで概念化し、ことばにしなければならず、外的で客観的な世界を、もっと直接に、身近に知っている人間同士の相互関係になぞらえて概念化し、ことばにしなければならない。
⑹闘技的トーン:声の文化は、知識を人間の生活世界のなかに埋め込まれたままにしておき、そうした知識を、人びとがやりあう格闘のコンテクストのなかに位置づける。
⑺感情移入的あるいは参加的:声の文化にとっては、学ぶとか知るということは、知られる対象との、密接で、感情移入的で、共有的な一体化をなしとげることを意味するのであって、対象から客観的な距離をとるのではない。
⑻恒常性維持的:声の文化の社会は、ほとんど現在のなかで生きており、もはや現在との関係がなくなった記憶を捨て去ることによって、均衡状態あるいは恒常性を維持している。
⑼状況依存的:声の文化のなかでは、概念が状況依存的で操作的な準拠枠において用いられる傾向がある。その準拠枠は、人が生活している生活世界にまだ密着しているという意味で、抽象の度合はきわめて小さい。
以上のような特徴をもつ音声言語とそれを用いたコミュニケーションは、基本的に声の聞こえる対面的状況においてのみ成立する。空間的に離れてしまえば、いくら大声を出してもおたがいの声は届かなくなるし、時間的に離れてしまえば、時間の流れのなかで瞬時に消え去るおたがいの声は届かなくなる。コミュニケーションのメディアとしての音声言語は、コミュニケーションが成立する空間と時間をきびしく制約する。もちろん、さまざまな記憶と口承の技法によって、その制約をある程度までは緩和することができるが、コミュニケーションによって大規模な社会を形成するには、その制約はあまりに大きい。オングのいう声の文化という独自の意味構成のパターンをもつとはいえ、音声言語によってコミュニケーションの第一のハードルである「理解」の蓋然性は大きく高まった。しかし、第二のハードルである「伝達」の蓋然性がまだきわめて低い。このハードルを越えなければ、コミュニケーションの広がりによる社会の規模の拡大は困難である。
伝達のメディア:文字、印刷、電子メディア
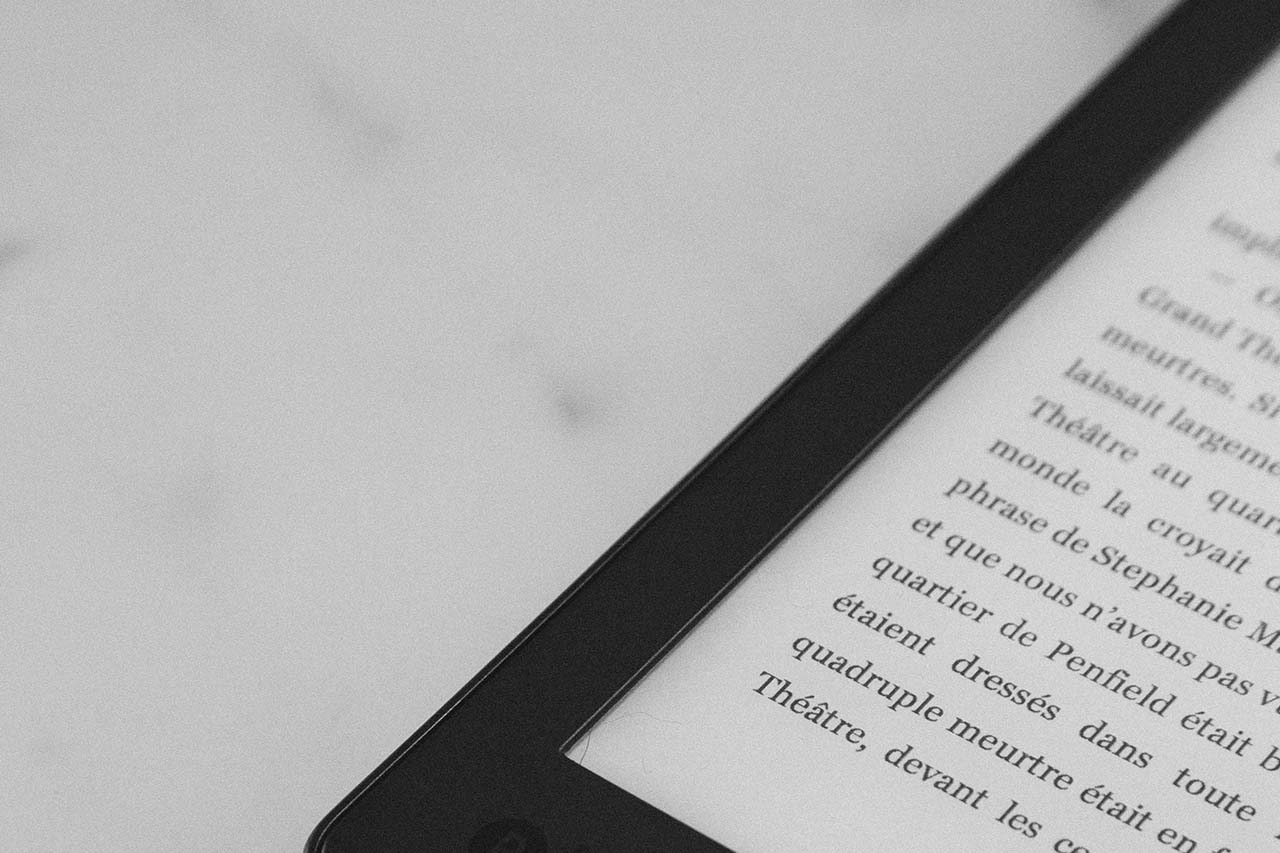
伝達の非蓋然性というハードルは、途中で入ってくる可能性のあるノイズの問題をのぞけば、基本的に空間的・時間的な距離の克服の問題である。今日では、その克服のためのメディア技術があまりに多くなり、とくに電子的な先端メディアの発達はまさに日進月歩なので、伝達ないし流布のためのメディアの始まりを想像する方が難しいくらいである。狼煙や太鼓のように声の届かないところまで合図を送る比較的単純なメディアを別にすれば、複雑に構成された意味を伝達するためには、音声によって伝達されてきた言語を別のかたちの言語に変換して、離れた相手に届けられるようにしなければならない。その始まりが文字である。
(1)文字
われわれは、読み書き能力を身につけた人間として、音声言語による口頭コミュニケーションと文字言語によるコミュニケーションを併用しているので、両者を特性の異なるメディアとして使い分けはしていても、同じ言語を使っていると思いやすい。同じ言語のなかの違いとしては、日常的にはせいぜい口頭コミュニケーションでは口語体(話しことば)と文字によるコミュニケーションでは文語体(書きことば)の違いを気にするくらいではないだろうか。しかし、コミュニケーション・メディアとして見ると、文字言語は伝達のメディアとしての性格をもつことによって、コミュニケーションの様式を口頭コミュニケーションとは異なるものに変化させ、理解のためのさまざまな技法まで変化させる。
まず、口頭コミュニケーションにおいては、情報・伝達・理解というコミュニケーションの三つの構成要素が同じ空間で同時に成立するのに対して、文字コミュニケーションにおいては、この三つが時間的・空間的に分離していく。口頭コミュニケーションでは、一つのコミュニケーションは文字どおりその場で発生しては消え去って完結する瞬間的な出来事だが、文字コミュニケーションでは、一つのコミュニケーションの完結は、空間的な制約がなくなるかわりに、さまざまな長さの時間がかかるようになる(Luhmann, 1997=2009, 1pp.291-293)。文字が書かれる物理的な乗り物としての石板・粘土板、木簡・竹簡、羊皮紙や紙、そして現代の電子的な媒体に至るまで、それらが物理的に破壊され消滅しないかぎり、いつまでも読まれる可能性をもっている。つまり、コミュニケーションが完結するための時間はかぎりなく長くなることがありうるとともに、その物理的な媒体を運ぶことによって、空間的にも大きく拡大することができる。
文字で書かれたもののうち、手紙のように基本的に応答を必要とする場合には、伝達はなるべく速やかに行われ、比較的短いあいだに返信が送り返されるか、手紙の内容に応じた行動が選択される。なんらかの事象を記録するために書かれた記録文書はどうだろうか。歴史学者や考古学者が対象にする歴史資料の場合、それは記録庫に残されているだけでなく、しばしば発見・発掘によって新たに見いだされ、読み方がわからない文字の解読さえ行われる。私的な手紙でさえ、歴史資料として読まれる場合には、ほんらいのコミュニケーションの当事者ではない観察者としての歴史学者による読解が可能になる。ここまでくると、もはや誰から誰にという問いがほとんど意味をなさないという点で、コミュニケーションの臨界に位置するといってもよい。これに対して、マックス・ヴェーバーが官僚制の特徴の一つとして述べた文書主義における記録文書は、国や自治体における公文書であれ、私企業における業務文書であれ、「予備的な討論や最終的な決定、あらゆる種類の処分や指令は、文書の形で固定される」(Weber, 1956=1970, p.16)。このような文書は、ヴェーバーの考えた精密機械のような形式合理性をもつ官僚制組織にとって、継続的な経営のための必須の要素とされる。
文字はさらに、詩や小説のような文学作品の制作、学術的な論文作成のためにも用いられる。声の文化のなかでは、先に挙げたような音声言語の特性から、文学は韻やきまり文句を多用する詩の形式をとり、口承によって伝達された。われわれは今日、声の文化の時代に制作された文学作品も、ほとんど文字化されたかたちで「読む」わけだが、ほんらいは音声言語によって対面的なコミュニケーションの範囲で朗読によって再現されたものを「聴く」ものだった。韻やきまり文句を多用する形式は、文字の発明以降も長く残っているが、しだいにそれとは異なる散文という形式が成立し、小説やエッセーの主流になっていく。それらは音声によって朗読されるのではなく、文字として黙読されるようになっていく。新しい形式は、言語表現の自由度を大きくしたが、同時に音声として読みにくいものにもした。その極北には、具体詩(concrete poetry)のように視覚に訴えるかたちで文字を活字でデザインして配置し、文としての意味の読解を否定するかのような形式さえ現れた(Ong, 1982=1991, pp.265-266)。また、口承による文学の伝達においては、具体的に音声言語によって発話ないし吟詠する人はいても、もともとの作者は不明なことが多い。これに対して、文字の文化になってから「書かれた」文学では、作者が誰であるかが重要な問題になってくる。さらに、手書きの写本の時代には異本が多く、テキスト・クリティークが重要な意義をもつが、印刷の時代になると、もとの手書き原稿にさかのぼって推敲の跡をたどる研究はあっても、手書きの文書のような異本のテキスト・クリティークは意義を失っていく。電子的にワープロで原稿を書くようになると、書くたびにファイルを上書きするのではなく、すべてのバージョンを別々のファイルとして残しておかないかぎり、推敲の跡をたどるのもほとんど不可能になる。
また学術的なコミュニケーションの発達も、文字の発明を前提にしている。声の文化においても、コミュニケーションとしての学術的な対話は成立するし、一定の知識を記憶と口承によって伝えていくこともできただろう。しかし、知識の厳密な表現、蓄積、反復的な検証は、文字による記録によってはじめて可能になったと考えられる。学術的な知識を文書のかたちで固定するためには、音声言語によって思いつくままに順に語っていくのとは違って、厳密な論理展開が必要である。読む側にも、その論理展開を追って、論証過程を検証することが求められる。そうでないと、おたがいに勝手な意見を披露しあうだけになってしまい、知識の検証と蓄積が進まないからである。書く側にも読む側にも複雑で反復的・再帰的な意味の確認と検証が求められ、コミュニケーションのモードは口頭コミュニケーションのように瞬間的に現れては消えていく出来事とは大きく異なるものになる。学会における発表や講演、大学における講義のように、それ自体が口頭コミュニケーションで行われる場合でさえ、あらかじめ文字による問題設定や論理構成を準備しないのはきわめて稀である。講義ノートや速記録をもとにした講義録がそのまま書籍になることがあるが、これも事前準備による知識表現の厳密性が担保されているからである。また、書き手=情報の発信者が特定されることによって、新しい知識を生み出す学術への貢献の業績を誰に帰属させるかも明確になる。それは著作権につながり、さらに自然科学では最初の発見・発明・考案の帰属にかかわる先取権の問題にもつながる。
オングが声の文化について挙げた思考や表現の特徴と対照させて、文字の文化の特徴をまとめると、次のようになるだろう。
⑴従属的:「そして」によって累加的に話が続くのではなく、さまざまな接続詞を用いて分析的で推論的な構文をつくるようになる。
⑵分析的:個々の語によって指し示されるものの意味が、語のまとまりによってきまり文句として累積的に示されるのではなく、個々に分析されるようになる。
⑶簡潔:文字のなかに話の本筋が固定されて読み返すことができるようになるので、表現の冗長度が小さくなって簡潔になる。
⑷革新的ないし進歩主義的:概念化された知識は、文字のなかに固定され、くり返し検証と反証の対象になるので、知識の更新が常態になる。
⑸生活世界からの距離:文字のなかに固定された知識は、そのときどきに展開される生活世界における日常生活から切り離されて、独自の抽象的な体系と空間を形成していく。
⑹客観的トーン:知識は生活世界から切り離され、抽象されていくので、闘技的トーンよりも客観的トーンを帯びるようになる。
⑺感情中立的ないし距離的:音声言語が、声音・声色、テンポ、抑揚などによって表現に感情を込めることができるのに対して、文字は生活世界における感情に対して中立的になり、距離をおくようになる。
⑻進化的ないし変動的:文字言語は、コミュニケーションを現在への拘束から解放し、過去と未来の時間軸のなかで意味をくり返し再構成することができるので、知識は進化的ないし変動的になる。
⑼状況独立的:文字言語は、生活世界からの切り離しによって、そのときどきの特定の状況に依存しないコミュニケーションを可能にする。
以上のような特徴をもつ文字言語とそれを用いたコミュニケーションは、音声言語によるコミュニケーションにおける空間・時間的なきびしい制約を大きく取り払うことになっただけでなく、コミュニケーションにおける表現様式も大きく変えるようになった。とはいえ、手書きの文字は特定の誰かによって書かれなければならず、それを複数の人、さらには多くの人びとに伝えるには、書かれた現物を狭いサークルのなかで回し読みするか、手書きによる複製(写本)に頼るしかなく、まだ複雑で大規模な社会を形成するには遠かった。短い時間で大量の伝達を行うために、文字言語の印刷による複製が始まる。
(2)印刷
西洋だけでなく世界的に見ると、印刷の歴史は複雑である。印刷技術としては、活字印刷ないし活版印刷以前に、木版印刷がある。木版印刷は中国で発明され、それがアジア各地に伝わるだけでなく、ヨーロッパにも伝わっていった。活字印刷もまた、最初の発明は中国とされる。活字印刷は、中国やその他の漢字文化圏では、文字種があまりに多く、また書体も複雑だったので、あまり発達せず、もっぱら木版印刷が用いられるようになった。他方、もともとは中国から伝わった技術としての木版印刷を用いていたヨーロッパでは、15世紀半ばに金属活字を用いた活版印刷が発明される。ほんとうの発明を誰に帰属させるかについては諸説あるが、一般にはヨーロッパにおける活版印刷の発明はグーテンベルクの名によって知られている。
当然のことながら、それまでの手書き文字が、活版印刷の発明によってすべて印刷におきかえられたわけではない。またヨーロッパでは、活版印刷以前の文書の大半は修道院で修道士たちによって作成される写本によって複製されていたとされるが、これまた活版印刷の発明とともに、すべての文書(とくに書籍)の作成・複製が修道院の写本室から世俗の印刷工場へただちに移ったわけではない。12世紀には在俗の書籍商が修道院の写字生にとってかわりはじめていた。そのころ、ヨーロッパ最古の大学が生まれ、宗教的なニーズとならんで世俗的な知識のニーズも増大していた。それとともに、罪の赦しを得るために働く修道士の無料奉仕は、世俗の筆耕の賃労働に移行していった(Eisenstein, 1983=1987, pp.11-19)。ルーマンによれば、書物の複製と市場での流通が可能になったのは、印刷技術そのものから必然的に生じる効果ではなかった。中国や朝鮮では印刷機(木版印刷機)は中央の支配官僚機構の掌中にあり、中央から発せられた伝達を広めるためだけに用いられていたのであり、ヨーロッパにおいてのみ、市場と価格を介した流通、つまり経済的なメカニズムによる流通が発達した。またそれは、宗教や政治の特定の権威や権力による統制を離れた「脱中心的な」かたちでの流布だった(Luhmann, 1997=2009, 1p.326)。
ヨーロッパの文字言語で用いられるアルファベットが、一文字ごとに分解された金属活字の制作とそれによる組版に適していたことはよく指摘される。また、活版印刷の発明に先立って、これまた中国で発明された製紙法がイスラム圏を経由してヨーロッパに伝わり、写本作成で主に用いられていた羊皮紙にとってかわりつつあったことが、活版印刷の普及を容易にしたこともしばしば指摘される(Febvre/Martin, 1958=1985, 上pp.75-101)。技術的に見て、こうした要因が印刷術を発達させたことはまちがいないが、同時に印刷術によって複製された文書を求める社会的ニーズが高まりつつあったことも忘れてはならない。14〜16世紀におけるヨーロッパの大きな文化運動とされるルネサンスは、かならずしも内発的に起こったものではなく、11世紀末から13世紀末にかけての十字軍遠征によるイスラム圏との文化接触をとおして、ヨーロッパ中世とは異なるかたちで保存・伝承されてきた古代ギリシアの文化が再発見され、輸入されたことによって展開したものと考えられている。古代ギリシアの文化は、哲学や文学のような人文的なものから数学や自然科学にいたるまで、世俗的な知識の全域におよんだ。西洋にも、中世以来の自由学芸(ないし自由七科)の伝統があったが、これに輸入された古代ギリシアの文化が重なって、ヨーロッパの知識のあり方は大きく変化し、その後の発展につながっていった。
活版印刷術の発明は、知識の伝達・流布の空間的な範囲を飛躍的に拡大させた。アイゼンステインは、「印刷革命」後の数世紀にわたるヨーロッパにおけるこの空間的な拡大過程を「広がりゆく文芸共和国」と呼んだ(Eisenstein, 1983=1987, pp.99-115)。とはいえ、革命以前の写本の時代、手書き文書の時代には、そもそも文字言語を自由に操る人びとの割合はきわめて小さかったし、その主要な担い手であった聖職者や学者が用いた文字コミュニケーションのための言語はラテン語だった。このラテン語は、一般の人びとが日常生活を営む地域で用いる各国語、さらにはその変種としての方言とは異なり、ヨーロッパ中の聖職者や学者の共通語として用いられた。その意味で、ラテン語はヨーロッパ全域に広がる知識のコミュニケーション空間を形成するのに貢献していた。印刷革命が初期に作り出した活版印刷による書籍もまた、ラテン語で書かれていた。つとに有名なのはグーテンベルクが制作した42行聖書である。15世紀半ばのヨーロッパの文化的環境を考えれば、新しいテクノロジーが最初に伝統的な宗教の聖典を制作したのは不思議なことではないが、その後の印刷術の技術的な自律的発展と印刷物の市場の形成によって、印刷される内容はあらゆる分野に広がっていった。
そうはいっても、印刷革命がまずもたらしたのは、すでに文字言語の使用に熟達していた聖職者や知識人のあいだのコミュニケーションの時間的な速度と空間的な拡大だった。手書き文字の時代から、作成された書物や文書のなかに蓄積された知識や情報は、図書館や文書館といったアーカイブのための施設に収蔵されていたので、これらの施設に行けば現物を読むことができたし、許されれば筆写することもできた。しかし、印刷革命によって書籍や文書が複製されて流通するようになると、いわば書籍や文書が向こうからやってくるようになる。ヨーロッパでは主に修道院に併設された図書館を訪れることなく、市場で流通する書籍を購入することによって、書籍をわがものとして手にし、読むことができるようになった。また、アーカイブされる書籍の量も飛躍的に増大した。こうして、近代を形成する社会文化的な動きとして、人文主義の発達、宗教改革の展開、科学革命の進展が可能になった(Eisenstein, 1983=1987, p.189ff.)。これらの動きを逐一紹介するのは本稿の主要な目的ではないが、社会学ではマックス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』以来一世紀にわたって議論が続いている、宗教改革が近代社会の成立におよぼした影響について、印刷革命の観点から簡単に見てみよう。
16世紀初頭に宗教改革の嚆矢となったルターが「聖書に帰れ」と主張したことはよく知られている。宗教改革以前のキリスト教(カトリック)の世界では、文字(中世以降は基本的にラテン語)で書かれた聖書に直接アクセスできるのは、聖職者や神学者のように高い読み書き能力をもつ一部の人びとだけだった。読み書きのできない一般の信徒は、聖職者がラテン語で聖書の一節を読み聞かせ、その意味をそれぞれの地域の言語で説き教えるのを聴くほかなかった。この聖職者による説教は教会の権威を背景として、一般の信徒にいわば一方的に聖書の解釈を押しつけた。一般の信徒は、聖書の教えに直接触れて、その解釈の真偽をみずから検証するすべをもたなかった。当時の贖宥状のスキャンダルをはじめとするカトリックの腐敗や堕落を糾すためには、一般の信徒がみずから聖書にアクセスして、その教えをわがものとする必要があった。そのためには、一般の信徒が書籍としての聖書を手にし、みずからが日常生活で用いる言語の読み書き能力(リテラシー)によって、その教えを知らなければならなかった。それを可能にしたのが、一方で印刷による聖書の普及であり、聖書のテクストのラテン語から各国語への翻訳だった。また、読み書き能力を身につけるための教育も進められた。これらの過程が複合的に展開することによって、プロテスタントによる宗教改革が進行し、これに対抗するカトリックの改革ともあいまって、印刷物が広く社会に流布するための文化的素地が整ってくるのである。
ところで、読み書き能力の普及は、ただちに複雑な知識そのものが広く社会に普及することを意味しない。そもそも音声言語によるコミュニケーションのテーマとなる事柄は、深遠で高尚な知識だけでなく、あらゆる日常生活の些事にわたる事柄を含んでいたわけだが、文字言語の時代になると、聖職者や学者による文字というメディアの寡占状態とあいまって、文字コミュニケーションのテーマから、いわゆる教養のない庶民の関心事や日常生活にかかわる事柄は、相対的に抜け落ちていった。そのような事柄まで事細かに書き留めるニーズもなければ、書き留める能力のある人材もいなかった。文字資料を中心とした歴史研究において庶民の生活の実相が見えにくかった一因も、文字によって記録された実証的な資料の欠如にあったと考えられる。印刷革命の後も、当初は宗教や学術の高尚な知識を扱う書物の流布が中心だったが、印刷物の流通が経済的な市場の論理によるものになっていったことによって、極端な言い方をすれば、売れるものはなんでも印刷するということになっていった。さらに、流通量と流通速度が増大し、市場における商品の競合が起こると、売れるものは面白く、新奇なものを含んでいなければならなくなった(Luhmann, 1997=2009, 上p.328)。
印刷の普及とともに、読書公衆の成立について語られることも多い(Eisenstein, 1983=1987, p.99ff.)。もともと英語でreading publicと呼ばれてきたこの読書公衆は、たんに読み書き能力を身につけた人びとを指すというより、一定の教養と思考力をもって印刷された文字言語を読む人びとを指すことが多い。有名な岩波文庫の『読書子に寄す』という岩波茂雄の発刊の辞の冒頭にある、「真理は万人によって求められることを自ら欲し、芸術は万人によって愛されることを自ら望む。かつては民を愚昧ならしめるために学芸が最も狭き堂宇に閉鎖されたことがあった。今や知識と美とを特権階級の独占より奪い返すことはつねに進取的なる民衆の切実なる要求である。」という宣言は、20世紀前半の日本社会における狭い意味での読書公衆の成立を期したものとみなすことができる。じっさい、ドイツのレクラム文庫に範をとった岩波文庫は、日本社会においては、いわゆる教養主義が懐疑的に見られるようになる20世紀末になるまで、教養層が愛読するもの、あるいはみずからが教養層の一員になるために読むものだった。
話が時代も社会も飛びすぎたので、ヨーロッパの印刷革命後の時代に戻ろう。経済的な市場の論理によって、売れるものはなんでも印刷するようになると、そのニーズはしだいに庶民にも広がっていく。もちろん、庶民が求めるのは、大部で重厚な教養豊かな書物よりも、いわゆる軽い読み物であり、それさえ読み書き能力があまり普及していない段階では、文字の読める人による朗読、読み聞かせによって聴かれるものだった。じっさい、ヨーロッパの読み書き能力の普及はひじょうに緩やかにしか進行せず、江戸時代末期に日本に来航したヨーロッパ人が、日本人の読み書き能力の高さとその普及度に驚いたというのは、有名なエピソードである。庶民向けの印刷物の内容は多岐にわたり、神話や伝説、科学技術や魔術、宗教や芸術、迷信やゴシップなど、庶民のあらゆる関心事がテーマとなった(Mandrou, 1975=1988;小林, 1988)。印刷物の形式も、簡単なパンフレットやリーフレットの形式をとったり、多くの挿画を用いたりしたものが多かった。宗教改革への印刷の貢献さえ、聖書の印刷だけにとどまらず、反カトリックの運動の機運を高めるための絵入りのパンフレットにいたるまで、多様なものだった。社会学的にいえば、社会運動としての宗教改革には、人びとを動員するための簡潔で単純なメッセージが書かれた「ビラ」が必要だったのである。
庶民への印刷物の普及と読書公衆の成立のためには、グーテンベルク以来の活版印刷の機械化による大量生産が不可欠だった。とくに産業革命の黎明期に発明された輪転印刷機(輪転機)は、印刷の速度を飛躍的に増大させた。産業革命は、蒸気機関の発明以降、書物の大量印刷を可能にしただけでなく、鉄道網の整備ともあいまって、印刷物の迅速な輸送を可能にした。新聞という印刷物は、すでに印刷革命とともに生まれ、印刷技術の発達と新しい情報に対する社会的ニーズの増大にともなってしだいに発行間隔が短くなっていたが、輪転機と鉄道輸送はその流通速度を飛躍的に高め、流通範囲を大きく拡大した。狭い地域で流通する日刊新聞はすでに存在したが、同じ新聞の全国流通が可能になり、同じ情報が国民に広く共有されるようになった。またそれとともに、面白さと新しさを求めて、新聞の形態も分化していく。書籍の多様化がそうであったように、新聞も高級紙と大衆紙に分化していき、高級紙は正統なジャーナリズムによって公共的な言論空間としての公共圏を形成するが、大衆紙は庶民のあらゆる関心に応える内容を掲載し、市場の論理にもとづいて発行部数を伸ばすために、センセーショナルな記事を売り物にしたイエロー・ジャーナリズムを生み出した。庶民の知性と教養の欠如と言ってしまえばそれまでだが、人びとのコミュニケーションの総体によって形成される社会の意味世界は、かつての啓蒙主義が夢見たほど、またハーバーマス(Habermas, 1990=1994)が規範的に求めるほど理性的にはできていないのである。
15世紀半ばの印刷革命からの社会的コミュニケーションの変容をやや詳しく見てきたが、伝達のメディアとしての印刷が、文字言語の印刷と流通によって、コミュニケーションの伝達範囲を飛躍的に拡大し、伝達速度を飛躍的に高めたことを確認しておこう。またそれがひるがえって、伝達されるコミュニケーションの内容や形成される文化のあり方を大きく変容させたことも確認しておこう。いずれにしても、それによって社会の規模は拡大し、構造は複雑になっていった。印刷メディアは、21世紀の今日にいたるまで、依然として有力な伝達のメディアである。しかし、19世紀末に始まった電子メディアの発達が、伝達のメディアのあり方を全体として大きく変えることになり、印刷メディアもその影響を大きく受けるようになる。この伝達のメディアとしての電子メディア、そして第三の非蓋然性を克服するための成功のメディアとしての象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアについては、回を改めて見ていくことにしよう。
(続く)
参考文献
Eisenstein, Elizabeth L., 1983, The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge University Press.(別宮貞徳監訳『印刷革命』みすず書房、1987年)
Febvre, Lucien/Martin, 1958, Henri-jean, L’apparition du livre, Albin Michel.(関根素子・長谷川輝夫・宮下志朗・月村辰雄訳『書物の出現』上・下、筑摩書房、1985年)
Habermas, Jürgen, 1990, Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, 2. Aufl., Suhrkamp Verlag.(細谷貞雄・山田正行訳『〔第2版〕公共性の構造転換:市民社会の一カテゴリーについての探究』未來社、1994年)
小林章夫著『チャップ・ブック:近代イギリスの大衆文化』駸々堂、1988年
Luhmann, Niklas, 1984, Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp Verlag.(馬場靖雄訳『社会システム:或る普遍的理論の要綱』上・下、勁草書房、2020年/佐藤勉監訳『社会システム理論』上・下、恒星社厚生閣、1993-95年)
Luhmann, Niklas, 1997, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp Verlag.(馬場靖雄・赤堀三郎・菅原謙・高橋徹訳『社会の社会』1・2、法政大学出版局、2009年)
Mandrou, Robert, 1975, De la culture populaire aux 17e et 18e siècles, Editions Stock.(二宮宏之・長谷川輝夫訳『民主本の世界:17・18世紀フランスの民衆文化』人文書院、1988年)
Ong, Walter Jackson, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, Methuen, 1982.(桜井直文・林正寛・糟谷啓介訳『声の文化と文字の文化』藤原書店、1991年)
Weber, Max, 1956, Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie, 4. Aufl., J. C. B. Mohr.(世良晃志郎訳『支配の諸類型』創文社、1970年)








