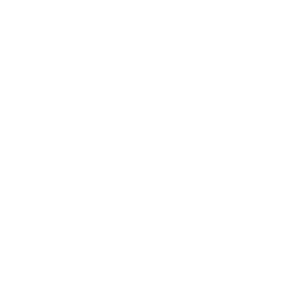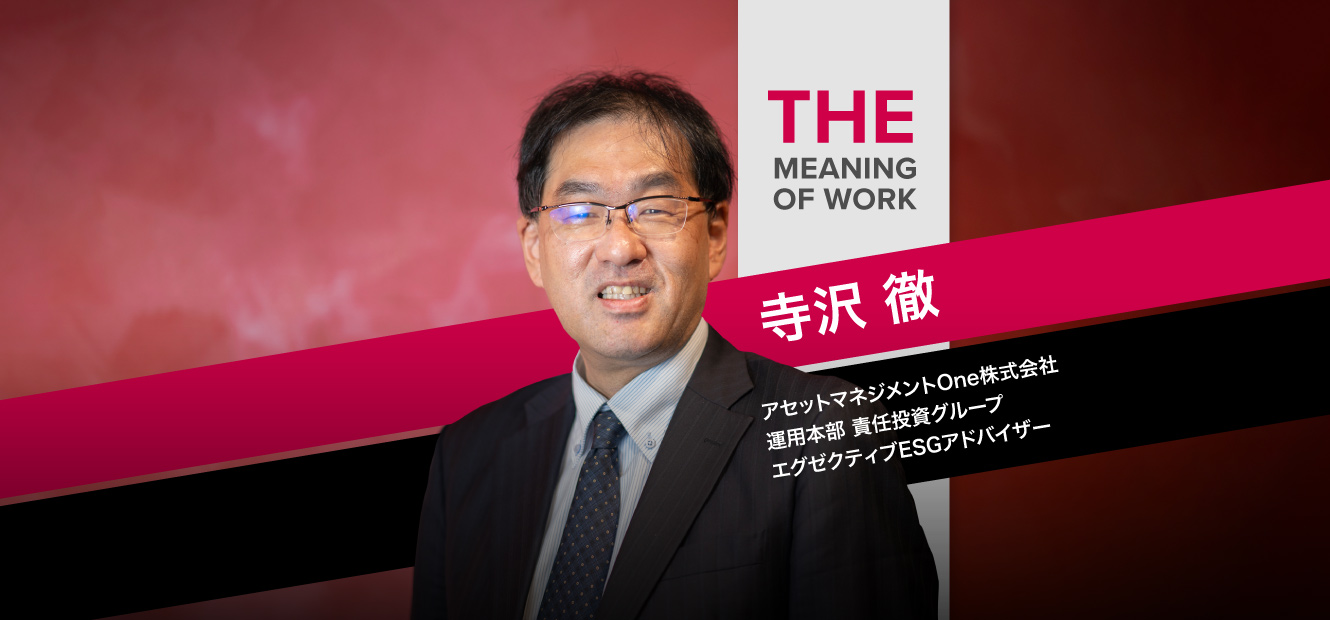伝統を未来へ
敷嶋が拓く「酒蔵」の新たな航路
-

伊東 優MASARU ITOH
伊東株式会社 代表愛知県半田市亀崎町で酒造を営む伊東家の9代目として生まれる。1788年(天明8年)の創業以来、伊東家が醸造する「敷嶋」は全国で親しまれていたが、日本酒需要の低迷により2000年に廃業。自身も一般企業に就職したが、祖父の死をきっかけに酒蔵復興を決意。2018年に退職後、愛知県津島市の長珍酒造(株)、三重県名張市の(株)福持酒造場にて日本酒造りを学ぶ。福持酒造場にて「敷嶋 0歩目」「敷嶋 半歩目」を製造し、ブランドを復活。2021年に清酒製造免許を再取得し、伊東(株)として「敷嶋」の酒蔵復興を果たす。2024年には旧酒蔵を活用した複合施設「伊東合資」をオープン。酒蔵の役割を超えて街の活性化にも取り組む。
-

林 幸弘YUKIHIRO HAYASHI
株式会社リンクアンドモチベーション
モチベーションエンジニアリング研究所 上席研究員
「THE MEANING OF WORK」編集長
早稲田大学政治経済学部卒業。2004年、(株)リンクアンドモチベーション入社。組織変革コンサルティングに従事。早稲田大学トランスナショナルHRM研究所の招聘研究員として、日本で働く外国籍従業員のエンゲージメントやマネジメントなどについて研究。現在は、リンクアンドモチベーション内のR&Dに従事。経営と現場をつなぐ「知の創造」を行い、世の中に新しい文脈づくりを模索している。
日本各地で伝統産業の存続が問われる中、地域と結びついた酒蔵が果たす役割はますます重要になっている。愛知県半田市亀崎町で200年以上の歴史を持つ「敷嶋」を復活させ、地域とともに歩み、伝統と革新の融合を目指す伊東優氏の物語から、地域と伝統産業の未来を探る。
伝統の継承。200年の時を越えて。

 |
林
まずは、前身の伊東合資会社と「敷嶋」の歴史についてお聞かせください。 |
 |
伊東
伊東合資会社は、1788年に愛知県半田市亀崎町で創業しました。江戸時代中期から後期にかけて、知多半島の酒造りは最盛期にあり、明治の初頭には酒蔵の数は200を超えていました。中でも、中部地方で最大規模の日本酒生産量を誇ったのが、伊東合資会社です。「敷嶋」の名は、江戸時代の国学者・本居宣長が詠んだ「敷嶋の大和心を人問はば朝日に匂ふ山桜花」という和歌から取っています。江戸で売るためのプロモーション的な意味合いが強かったのでしょうね。 |
 |
林
知多半島、半田市において、酒造は古くからの伝統産業なのですね。そこでつくられたお酒は江戸にまで流通していた。 |
 |
伊東
当時の流通は海運が中心でした。知多半島からであれば、船ですぐに江戸に運べますから、利便性が高かったんですよ。半田市では、地元の豊かな水源を活かした酒造りを中心に、酢やたまり醤油、味噌などさまざまな製品がつくられ、その販売を手がける卸会社などが集まり、地域の経済を盛り上げていました。半田市は(株)Mizkan(ミツカン)の本社があることでも知られていますよね。 |
 |
林
地域の経済を支えていた伊東合資会社は、日本酒需要の低迷を受け、2000年に廃業し、幕を閉じることになります。しかし、20年余の時を越えて、9代目である伊東さんの手で復活することになった。そのきっかけは何だったのでしょうか。 |
 |
伊東
きっかけは、2014年に祖父が他界したことでした。私の出身地では、親族が亡くなった時に蝋燭の火が消えないように「寝ずの番」をする風習があるのですが、その際、蔵に貯蔵されていた純米大吟醸酒「敷嶋 純」を飲む機会があったんです。芯がありつつ、上品さが残っている。強く、その味に惹きつけられました。これほどおいしいお酒をつくっていたのに、なぜ廃業になってしまったのか。9代目を背負う者として、自らの存在意義を強く意識させられました。自分は何のためにここにいるのか。「9代目としてできること」は本当にないのか。そんなことを考えるようになったんです。 |
 |
林
古くから地域を支えてきた酒蔵。その9代目としての使命を感じられたんですね。 |
 |
伊東
伊東合資会社の建物は、元銀行だった事務所をはじめ、歴史のあるものです(2022年登録有形文化財認定)。「せめて建物を残したい」というのが、最初の想いでしたね。観光地でもない半田市において、その想いを実現するには、古民家カフェのようなハードメインのビジネスをしたとしても難しい。コンテンツをまず興すことが不可欠であり、「もう一度、酒造りを復活させること」が最もしっくりくる方法だったんです。「敷嶋」を復活させ、200年以上続いた歴史を100年先の未来へとつなぐ。それが私の使命になりました。 |
行動が縁を結び途絶えた灯火が再び。

 |
林
「敷嶋」復活に向けて、最大の課題はどこにあったのでしょうか。 |
 |
伊東
最大の課題は、廃業時に清酒製造免許を返納していたことです。清酒製造免許の新規発行は、国内の需要と供給のバランスを調整するため、認められていません。解決方法は、免許を持っている企業にM&Aを行うことのみ。なかなか案件がなく、いいご縁を待つしかありませんでした。そのうえ私は、日本酒好きではあったものの、酒造りについてはまったくの素人。会社の有休を使いながら少しずつ勉強していたのですが、当時勤めていた会社の繁忙期がなぜか酒造りと被っていましてね(笑)。当初有休を取っていたのも難しくなり、それなら日本酒一本で行こうと、会社を辞めることを決めました。 |
 |
林
自分の使命を全うするために、新たな道を選ばれたのですね。 |
 |
伊東
退職後は、愛知県津島市の長珍酒造、三重県名張市の福持酒造場で蔵人として働きながら、日本酒造りを学びました。福持酒造場では、実家の酒蔵を復活させるという目標について相談したところ、タンクを1本貸していただき、OEMとして自分のお酒を造らせて頂くことができたんです。そうして出来上がったお酒に、亀崎での酒造りを復活への第一歩としたいという想いと、「0を1にする」という決意をあわせて、「敷嶋 0歩目」と名づけました。 |
 |
林
免許の再取得という最大の課題は、どのようにして解決したのですか。 |
 |
伊東
もともとSNSが好きで、お酒造りの発信を続けていたところ、ご縁に恵まれ、免許の再取得までたぐり寄せることができました。東京・人形町にある日本酒専門店から問い合わせをいただき、「敷嶋 0歩目」を置いてもらえることになったのですが、そのお店に通われる方に気に入っていただき、M&Aの相手先を一緒に探してくれることになりました。その方から「相手先が見つかりました」という連絡があったのは、それから1か月ほど後のこと。ちょうど、確度が高いと思われていた案件が白紙になってしまったタイミングでのことでした。仲介会社がいなかったため、司法書士さんや弁護士さんに相談しながら、必要な手続きや書類の準備などもすべて自分でやりました。 |
 |
林
ご縁が幸運を運んできた、と。 |
 |
伊東
M&Aが成立したのが2021年3月。そこから9カ月で製造開始にこぎつけました。M&Aを成立させてからの時間を振り返ると、何か大きな力に導かれていたようにも感じますね。こうした奇跡のようなご縁をいただけたのも、一歩踏み出す行動があったからこそ。どれほど素晴らしい志を持っていても、絵に描いた餅のままでは何の意味もないんですよ。 |
自らの存在意義が価値創造のエンジンに。

 |
林
伊東さんが復活させた「敷嶋」は、そのストーリーも含めて大きな話題となり、日本酒愛好家から高い評価を得ています。 |
 |
伊東
「敷嶋」はいわゆる食中酒です。食事の味を流すだけでなく、しっかりと受け止め、口の中で食事とお酒が合わさることにより味を昇華する、そして次のお酒、次のご飯に手が伸びる……。そんな酒を目指しています。そのために、お米をしっかりと溶かして食事の味を受け止められるだけの厚みを出しながら、上質な酸、そして良質な仕込み水に由来するミネラル感で締める味わいを実現しています。 |
 |
林
伊東さんは大手企業で活躍されていて、そのまま続けることもできたわけじゃないですか。リスクもある中で、どうやって決断を下すことができたのでしょうか。 |
 |
伊東
やはり、自らの存在意義を明確に定義したことが大きかったと思います。会社員時代には、事業企画というやりがいのある仕事に携わっていましたが、それはクオリティーに差こそあれ、「替えが利く」ものだったと言えます。けれど、9代目として酒蔵を復活させることは私にしかできないこと。自分の人生において、どちらが価値のある仕事かと考え、後者を選んだ。それだけのことです。 |
 |
林
そうしたマインドセットができたビジネスパーソンは強いですよね。現在、各企業ではパーパス経営が推進され、ビジョンやミッション、フィロソフィーの再定義を行っていますが、それが社員の納得感につながっていないケースが多い。 |
 |
伊東
私は自分の使命をどこまで今のメンバーに伝えられているかはわかりませんが、ある種の志のようなものを芽生えさせることができれば、組織は大きく変わりますよね。 |
 |
林
伊東さんは「0→1」で価値を創造するチャレンジを成し遂げました。新規取得できない酒造免許をどうするのか。経験のない酒造りをどう学ぶのか。それらを実現するためのアイデアやアクションは、ビジネスパーソンにとって大きなヒントになるものだと思います。 |
 |
伊東
実は、もともとそんなに得意じゃないんですよ。会社員時代の上司からは「0から1をつくるのが苦手だね」と言われていたくらい。その悔しさがバネになった面もありますが(笑)、大きな要因は、やはり自分の使命を認識したことだと思っています。視座を高く持ち、目的が明確になれば、おのずとそれを実現する手段は見えてくるものです。 |
酒蔵の復興と地域の復興。

 |
林
伊東さんは、2024年に、酒蔵を中心とした複合施設「伊東合資」をオープンさせました。もともと銀行だった事務所を日本酒バー「蔵の店 かめくち」として活用したり、地域の生産者とつながって地元の食材をふんだんに使ったり、日本酒と食のペアリングが楽しめるといったように、地域の魅力を発信していく取り組みにも注力されています。 |
 |
伊東
「伊東合資」では“知多半島を、世界の「食の半島」へ”というビジョンを定めています。知多半島では温暖な気候を活かして、米作、野菜、果樹、畜産など、さまざまな農業が盛んに行われています。食が豊かな地域の拠点として、「伊東合資」が存在する。そんな未来を思い描いています。また、知多半島は醸造で栄えた歴史を持っています。そして、その醸造文化は酒をきっかけに生まれたものです。歴史から見ても、酒蔵が中心となり、地域を盛り上げ、働きかけることは理にかなった流れだと私は考えます。 |
 |
林
200年以上の歴史を持つ酒蔵を復活させただけでなく、地域全体の活性化を目指す。その原動力はどこにあるのでしょうか。 |
 |
伊東
かつて亀崎が醸造を中心に栄えていたという話をさせていただきましたが、「昔はすごかった」という話は、今を生きる私たちに何の意味もありません。ただ、それって、すごく悔しいことじゃないですか。確かに昔は胸を張って言えるものがそこにあり、そして今はないんですよ。だからこそ、もう一度、私たちの手で亀崎に産業の灯をともしたい。そう考えたんです。そして、これは今の日本も言えると思います。 |
 |
林
「伊東合資」では、さまざまなコラボレーションイベントも開催していますよね。 |
 |
伊東
JR東海との協業で開催した「おとなり酒場」は、その一例ですね。日本最古の現役駅舎といわれる木造駅舎を持つ亀崎駅で、温かいおでんや日本酒を楽しめるイベントです。一般的に鉄道インフラは、乗客の安全を守るために、常にアップデートされていくものです。しかし、この駅舎の文化的価値を考えると、いつか取り壊されてしまうことがもったいないと私は感じています。この「古い」ということに価値を付けられたのであれば、今後の未来は変わるのではないかと思っています。 |
 |
林
さまざまなステークホルダーとともに、地域を盛り上げていく。素晴らしい取り組みだと思います。伊東さんは、どのような世界を未来に届けようと考えているのでしょうか。 |
 |
伊東
自分たちの世界だけで食をつくり上げる「キロメートル・ゼロ」という概念があります。これは、地域の食材を使おうという地産地消の考えから一歩踏み出して、知人だけの食材をつかい、また自らが生産者として、その食材に対する歴史・文化など、すべてのストーリーを体感してもらおうというもの。食のすべてが揃う知多半島だからこそ、そして一生産者である酒蔵だからできる、唯一無二の体験があると考えているんです。 |
 |
林
訪れる人が、食を通じて、その土地のすべてを体感できる。知多半島を訪れる「新たな意味」が生まれそうです。 |
 |
伊東
発酵・醸造は、食料を保存するために、生きるために発達した技術です。食材そのものを味わっていただくのはもちろんですが、地域の文化・歴史を象徴する建物で、味噌やたまり醤油造りを体験していただき、ここで生き、住み、営むことを感じてもらう、なんて取り組みもいいかもしれませんね。物流の進化や、コロナ禍の影響によって、地方に訪れる理由は希薄になってしまいました。特に、東京であれば、あらゆる地域の名産品を味わうこともできるし、特産物を自宅に取り寄せることだってできる。だからこそ、私たちは「ここでしかできないこと」を創造していかなければならないのです。 |
 |
林
実際に行ってみなければ体験できない価値ってありますからね。 |
 |
伊東
そうですね。ウチの本蔵なんて、写真で見るのと実際に見るのとではぜんぜん違いますからね。その空気感は「蔵」というよりも、「寺」に近い感じ。実際に来てみないとわからないことって、たくさんあると思うんです。また、先ほど話題に上った地域食材とのペアリングもグレードアップして、ツアーも含めた30,000円くらいの「体験」のコースみたいなものに変えようと考えているんです。ここでしか味わえない価値・体験でなければ、遠方から訪れていただくことは難しいですから。 |
100年後の未来を見据えて。

 |
林
生産者がつながり、観光業にもその価値が広がっていく。伊東さんは、新たな知多半島のエコシステムをつくるうえで、どのようなことを大切にしていますか。 |
 |
伊東
常に意識しているのは、私たちは観光に従事する者ではなく、生産者であるということです。より品質の高いものをつくり、消費者に届ける。それが、メインの営み。サービスばかりに目がいくと、必然的に質が落ちてしまうからです。それでは、100年先の未来に「敷嶋」を残すことはできなくなってしまいます。本物を届けること。それを継続することが何よりも重要なんです。 |
 |
林
昨今、ビジネスの世界においては、伊東さんのように「突き詰める」ということが難しくなっています。コンプライアンスを遵守する中で、ここまでしかやれないというもどかしさを感じている人も多いのではないでしょうか。 |
 |
伊東
私の目的がお金を稼ぐことであるなら、そもそも酒蔵なんて始めていません(笑)そして、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視し、効率を追い続けるでしょう。けれど、私は自分の使命を「この酒蔵を復活させ、100年後も残すこと」「地域を発展させること」としています。「敷嶋」の質を高め、多くの人に届けるために何をすべきか。この場所に人が来るためには何が必要か。知多半島を「食の半島」にするためにはどうしたらよいかを考えると、最優先すべきはタイパではなくなってくるんです。 |
 |
林
確かに、何のために生きるかによって、優先すべきものは変わりますね。リンクアンドモチベーションでは「ひとりひとりの本気がこの世界を熱くする」というコーポレートキャッチを掲げて、1人の可能性が世界を変えると信じています。伊東さんのチャレンジはそれを体現していると思いますし、「敷嶋」の復活は、伝統と革新を融合させた新たな価値の創造であると私は考えています。 |
 |
伊東
そこまで到達できているわけではありませんが、胸を張ってそう言える価値を生み出していきたいですね。人生は一度きりのもの。その課程では、「やっておけばよかった」という後悔が多く生まれます。だとすれば、人生を左右するほど重大な選択に直面したタイミングにおいては、使命として位置付けてしまい、論理や冷静な判断を放り投げてしまうのも踏み出すための手段なんじゃないかなと思います。たとえ失敗したとしても、その経験は後の糧になります。新たなチャレンジに躊躇している方がいるのなら、その一歩は踏み出すべきです。自分じゃなければできないことを決めて、突き進む。そうすることで、今まで以上に自分の価値は高まっていくはず。まずは、行動してみることで、違う世界が見えてくると思いますよ。 |