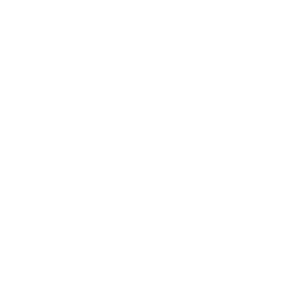第5回 コミュニケーションのメディア(2)
-

徳安 彰AKIRA TOKUYASU
法政大学社会学部教授東京大学文学部社会学科卒業。同大学院社会学研究科博士課程修了。法政大学社会学部専任講師、同助教授、ビーレフェルト大学客員研究員、法政大学社会学部教授、法政大学社会学部学部長を歴任。共著に『社会理論の再興』(ミネルヴァ書房)、『理論社会学の可能性』(新曜社)など。
第5回では、コミュニケーションの非蓋然性、つまり日常的にはごく自然に成り立っているように思われるコミュニケーションが、じつはそう簡単には成り立たないことの三つの契機(理解、到達、成功)から出発し、その非蓋然性を蓋然性に転換するコミュニケーションのメディアについて、理解のメディアとしての言語、伝達のメディアとしての文字、印刷について論じた(第5回 コミュニケーションのメディア(1))。今回はその続きとして、伝達のメディアとしての電子メディアについて論じる。
はじめに
このテーマが複数回に分かれたのは、もちろん扱うべき内容が多いからであるが、また電子メディアについてどう論じるのかが難しいからでもある。というのも、ルーマン自身が中心的に論じている電子メディアは、基本的にラジオ、テレビといったマスメディアであるのに対して、現代の電子メディアの主要な注目点はネットメディアだからである。1998年に亡くなったルーマンにとって、ネットメディアはようやく晩年に姿を現し始めたばかりのメディアだった。それどころか、ルーマン自身は、最後までコンピュータを使わず、原稿書きはタイプライターで通していた。タイプ打ちの原稿あるいは口述筆記の録音を秘書がワープロで打ち直し、あるいは打ち起こし、印刷したものに、また手を入れるというスタイルだった。研究のアイデアは、有名なカードボックスの手書きもしくはタイプ打ちのカードに書き留められていた。ルーマンの生前にもすでに、コンピュータのカード型データベースは存在していたが、本人は長年慣れ親しんだカードボックスを使った。ちなみに、ルーマンのカードボックスの内容は現在、ルーマンが在籍していたビーレフェルト大学でデジタル・アーカイブ化されており、オリジナルの手書きまたはタイプ打ちのカードの画像と、それをデジタルテキストにしたものを、体系化されたかたちで閲覧できる。
筆者が参加していた1990年代半ばのルーマンの教え子たちを中心とした若い世代の研究会のあとの懇親会では、「ルーマンのコンピュータリゼーション」について、なかば冗談、なかば真顔で語られていたほどである。教え子たちの念頭には、当然例のカードボックスがあり、コンピュータでデータベース化すれば、引用や文献リストの作成がはるかに楽になるだろうといわれていた。ルーマンも、コンピュータによるコミュニケーションについて論じてはいるが、それは20世紀末の技術水準のもとで書かれ、21世紀の状況については予測の域を出なかった。21世紀のネットメディアについて論じるのは、ルーマンの社会システム理論を引き継ぐ者の仕事である。この部分については、ルーマン解説にとどまらない議論を試みる。
伝達のメディア:文字、印刷、電子メディア(続)

(3)電子メディアの発達の歴史
メディア史では、電子メディアという言い方は比較的新しく、伝統的には電信(telegraph)と呼ばれてきた。電信は、電気の性質を利用して離れたところに情報を伝える技術全般をさし、電気信号の伝達チャンネルは有線と無線の二つに大別される。
電信技術の開発は、すでに18世紀に始まっており、欧米で産業革命が進展する19世紀半ばまでには有線電信が実用化され、ヨーロッパとアメリカを結ぶ大西洋横断海底ケーブルも敷設された。当時は、ケーブルを通して伝送できる情報量はきわめて小さかったので、きわめて圧縮したかたちで情報を送るために開発されたのが、サミュエル・モールス(米、1791〜1872)の名を冠したモールス符号である。これによって、電気的に符号化されたアルファベット文字(正確には英数字と記号)が伝送され、電報網が形成された。電信では、電気的な情報圧縮もさることながら、少ない文字数で情報を伝達するために、さまざまな略符号も考案された。SOSやOKは、日常の口頭コミュニケーションでも使われるようになったが、文字の略記としては、ABT(about)、AGN(again)からTU(thank you)、VY(very)、WL(wil)にいたるまでさまざまなものがある。略記法は、現代の電子メールやSNSでも使われており、ASAP(As soon as possible)、IMO(In my opinion)をはじめとして、これまたさまざまなものがある。
技術開発によって伝送される情報量が増大すると、19世紀後半には、音声を直接伝える電話が発明される。最初に基本特許を取得したグラハム・ベルは、ベル電話会社を設立して、当初の電話普及期の北米における事業を独占した。これが現在のAT&T社の前身となる。電報が圧縮された文字情報の伝達だとすると、電話は音声情報の直接的な伝達であり、対面的な状況のなかでしか行われなかったリアルタイムでの口頭コミュニケーションの空間的範囲が大きく拡大した。とはいえ、電話はほぼ1世紀のあいだ、音声のみによるコミュニケーション技術だった。対面的な状況に付随する表情や身振りのような情報はすべて捨象され、純粋に音声のみによる口頭コミュニケーションとなったため、ぎゃくにさまざまな状況を、場合によっては擬装的に演出する可能性も生まれた。
19世紀末からは無線電信の開発も進み、20世紀になって実用化されていく。無線電信は、ケーブル敷設にともなう空間的な制約を大幅に緩和し、有線電信以上にコミュニケーションの範囲を拡大した。海上の船舶はもとより、20世紀になって一躍発展する航空機も、無線技術によってコミュニケーションが可能になる。もちろん、中継のための基地や装置は必要だが、有線電信のようにケーブル網を敷きつめる必要はなくなる。先進諸国は、有線、無線の両方が組み合わさって発達していくが、後発諸国はとくに有線電信のためのインフラストラクチャーの整備がなかなか追いつかなかった。有線電信の電話網が普及しなかったのも、そのせいである。しかし、20世紀末の携帯電話の開発によって、無線電信による電話網が実用化されると、後発諸国はむしろ有線の電話網をスキップして、いきなり無線の電話網が普及するようになる。今日では、衛星による中継が可能になり、無線通信網はグローバルに拡大している。
さて、ここまでの議論は、有線、無線ともにおもに一対一のコミュニケーションが対象である。コミュニケーションの送り手と受け手がいて、それぞれが電信の送信機、受信機の前にいて、両者をつなぐ電信のチャンネルをとおしてコミュニケーションを行うというのが、基本的なイメージである。第4回の「コミュニケーションが作る社会システム」でとりあげたシャノンとウィーヴァーの通信理論は、まさにこの電信技術の発展の理論的な裏づけとなったものであり、電信によるコミュニケーション技術が飛躍的に発達し、普及した20世紀において、広い意味でのコミュニケーション全般のモデルとなったのも、うなずける。
また、技術の発達は、一方で送り手側の出力を増大させ、他方で受け手側の受信機を普及させることによって、ラジオ、そしてテレビというマスメディアを生み出す。一対一ではなく一対多の構図のなかで、双方向ではなく一方向に単一の送り手から多数の受け手に向けて、大量の情報が発信されるようになるのである。コミュニケーションの構図としては、新聞や書物・雑誌などの印刷技術によるマスメディアの発達と類似しているが、印刷メディアが文字を基本とするのに対して、電波メディアは音声や画像を基本としている。また、印刷メディアが読み書き能力(本来の意味でのリテラシー)を必要とし、流通のスピードが物理的な印刷メディアの輸送能力に依存しているのに対して、電波メディアは読み書き能力がなくても視聴することができ、流通のスピードは完全にリアルタイムになり、受け手全員に送信と同時に届くようになる。すでに半世紀以上前から衛星中継が実用化されたことによって、いまや電波メディアをとおした情報は世界中にリアルタイムで到達するようになっている。
そして、インターネットである。インターネットは、技術的には、これまでの有線、無線の電信技術の進化型である。ただし、送り手と受け手の端末が送信機かつ受信機としてのコンピュータ(その簡易型としてのタブレットやスマートフォン──これも技術の発展とともに境界が曖昧になりつつあるが)になったことによって、情報のやり取りは多対多で双方向的になった。マスメディアの発達は、完全な情報の受け手、受動的な情報消費者としての大衆を生んだが、インターネットは能動的な情報発信の可能性を万人に開いた。また、多対多の構図は、パーソナル・コミュニケーションとマス・コミュニケーションを、同じネット空間のなかに混在させることを可能にした。インターネットの情報の流通量は、回線の充実によって飛躍的に増大し、文字、音声、映像など、あらゆる形態の情報が飛び交うようになった。
(4)電子メディアの現在地
以上のような電子メディアの発達とその帰結を、ルーマン自身はどのように語っているのだろうか。
例えば、コミュニケーションは現在でも空間的に(したがって、時間的に)制約されてはいる。しかし電話からファックス、電子メールに至るまでのテレコミュニケーションによって、その制限はゼロに近づきつつある。技術によってもたらされたこの可能性を補完するのが、記録装置である。記録装置によってもまた、伝達と受信とを引き離すことが可能になる。つまり両方の側で、時間をそれぞれ異なるかたちで扱えるようになるのである。かくしてコミュニケーションの成立が容易になるわけだ。(Luhmann, 1997=2009, 1, p.338)
コミュニケーションの時間・空間からの解放は、ギデンズの用語を使えば「脱埋め込み」が進展することを意味する。ギデンズは、脱埋め込みを「社会関係を相互行為の局所的な脈絡から「引き離し」、時空間の無限の拡がりのなかに再構築すること」(Giddens, 1990=1993, p.35)と定義しているが、この社会関係をコミュニケーションと読み替えれば、ルーマンと通底する考え方であることがわかるだろう。電子メディアの通信装置は、発明されたときには基本的に固定式であったが、しだいに移動式になり(=モバイル化)、移動しながらコミュニケーションを行うことができるという点で、送り手と受け手がコミュニケーションできる空間的な範囲の制約だけでなく、送り手と受け手がコミュニケーションできる空間的な地点の制約も取り払っている。
また記録装置にしても、現代のインターネットを介したコミュニケーションでは、手元の装置の内部ドライブや外付けドライブだけでなく、ネットワーク上のサーバーに情報が記録されることが多くなってきた。エンドユーザーは、サーバーが世界のどこにあるのかを知ることもなく、自由に情報を保存し、また引き出すことができる。かつての書物が、文字情報の記録装置として作成され、図書館や個人の書庫の蔵書というかたちで保存されていた時代には、その書物のある場所に行かなければ記録にアクセスすることができなかった。しかし今や、利用権限さえあれば、ネットワークを介して世界中のサーバーに記録された情報にアクセスすることができるのである。
次に、映画とテレビについて、ルーマンはこう述べている。
また別の技術上の発明が、すなわち映画とテレビ(こちらはテレコミュニケーションと関連しているわけだが)が、動画のコミュニケーションを可能にした。さらに加えて動画に付随する音声を同期化させれば、登場してくる現実の総体をネガのかたちで複製することが可能になる。二次体験であってもオリジナルに忠実であるとの保証付きで、現実が再生産されるのである。視覚的際限と聴覚的際限は文字によってきわめて明確に分離されてきた。両者は再び融合する。‥‥
結果としてこの発明から生じてきたのは、世界の総体がコミュニケート可能になるという事態であった。存在の現象学の代わりに、コミュニケーションの現象学が登場してくる。世界は、画像コミュニケーションが示唆するように眺められる──もちろん劇的でもないし、完全無欠でもなく、色彩豊かでもないし、そして何より、精練されているわけでもないのだが。知覚によって捉えられる世界は、常により強い圧力に晒されるために、陳腐化していくことになる。これは通常の知覚の場合でも、テレビの世界を知覚する場合でも同様である。それに加えて知覚過程の中では、言語においてわれわれの耳目をひくものが、すなわち情報と伝達とを区別できるしまたそうしなければならないという点が、背景へと退いてしまう。‥‥(Luhmann, 1997=2009, 1, pp.342-343)
この映画やテレビのもつ、世界の総体をコミュニケートするという機能、あるいは世界の総体のリアリティを構築するという機能は、当初はマスメディアとしての映画やテレビの独占だった(Luhmann, 1996=2005)。音声付き動画の制作には、カメラやマイクをはじめとして高価で大型の機器が必要であり、さらに中継の場合には、これまた高価で大型の通信機器が必要だった。映画は上映装置のある映画館でなければ観ることができないし、テレビは本格的な放送設備のあるテレビ局しか送信することができなかった。したがって、マスメディアの時代には、十分な資金をもった一握りの制作会社やテレビ局だけが音声付き動画の配信を独占していた。
しかし今や、スマートフォンでも音声付き動画は簡単に制作することができ、それをそのままネットで中継したり、加工してサーバー経由で配信したりすることができるようになった。今やほとんど誰もが、受動的な観客や視聴者にとどまらず、配信者にもなりうるようになった。何かの事件が街角で起こると、周囲の人びとは、事件への直接的な対応よりも、一斉にスマートフォンを取り出して撮影を始め、撮影した映像をすぐにSNSで発信する、というすっかり日常化してしまった状況がそれをよく表している。そしてその分だけ、リアリティの構築は複雑で錯綜したかたちで行われるようになった。揚げ句に、AIによる画像生成が実用レベルになってきたために、その構築されたリアリティがそもそもファクトかフェイクかということまで問題になっている。
ルーマンの議論から少し先走ってしまった。動画のコミュニケーションを可能にした映画やテレビのようなマスメディアのあとに、コンピュータがくる。
‥‥しかし現在のところ最新の発明は、さらに一歩先に進んでいる。すなわち、コンピュータを介してのコミュニケーションが問題となっているのである。そこでは、コンピュータへのデータの打ち込みと情報の呼び出しを大きく隔てることが可能になっているので、もはやいかなる同一性も成立しない。コミュニケーションに関して言えばこれは、伝達と理解の統一性が放棄されているということを意味している。何かを打ち込む者は、反対の側で何が引き出されるのかを知らない(それを知っているようなら、コンピュータなど必要ないだろう)。両者の間でデータは《処理=加工》されてしまっているからである。同様に受け手のほうも、何かが自分に向かって伝達されるはずになっていたのか否か、何がそうだったのかを知る必要などない。典拠の権威は社会構造的な保護(階層、名声)を必要としたのだが、今や権威も保護も無用になってしまったことになる。それらは技術によって失効宣言を受け、出典の未知性によって置き換えられるのである。‥‥以上のすべてによって、コミュニケーションのメディア基体が、極限に至るまで社会的に脱カップリングされる。‥‥(Luhmann, 1997=2009, 1, pp.346-347)
ルーマンの生きていた20世紀末は、まだコンピュータによる動画のコミュニケーションはあまり普及しておらず、文字が中心だった。たとえば電子メールは、もともとは文字通り、手書きまたはタイプ打ちの手紙に相当するものを電子的に送る手段とみなされていた。送り手と受け手は特定されており、コミュニケーションの目的も明確で、たんに紙がスクリーンに変わっただけのように思われた。しかし、電子メールにしても、いったんメール・アドレスが何らかのかたちで知られると、個人的には知らない送り手から大量のダイレクト・メールが送られてくるようになり、ただの商業的な目的ならまだしも、大半はいわゆる迷惑メールで、フィッシングや詐欺への勧誘などをねらったものになっている。ルーマンが言うように、送り手と受け手は多くの場合に社会的に脱カップリングされている。
現代はさらに事態が進行している。ユーザーが利用するコンピュータ・コミュニケーションのプラットフォームは、中立的なプラットフォームを提供するだけではなく、ユーザーのプロフィール、コミュニケーションや検索の内容にもとづいて、一定のアルゴリズムによってユーザーの傾向に合っている情報を優先的に送るようになる。ネットショッピングであれば、買い物の傾向によって「あなたへのお勧め」の商品が優先的に表示される。ニュース配信サイトであれば、閲覧あるいは検索した記事に類似した内容のものが優先的に表示される。ユーザーは、自分で自由に情報を選び取っているように思いながら、じつはアルゴリズムで選別された情報のみから選択するように仕向けられてしまう。これがフィルターバブルである。また、自分の情報を発信するプラットフォームでは、発信された情報に共感するフォロワーができ、みずからも共感できる情報をフォローし、結果的に発言とフォローのサイクルのなかで、しばしば特定の傾向の意見や思想、あるいは興味や嗜好だけが増幅していく。これがエコーチェンバーである。
これはもはや、マスメディアが特定の傾向の情報を集中的に流すことによって大衆の意見や行動に影響を与える大衆操作とは、まったく構図が異なる。プラットフォームは、それじたいが大衆操作の意図をもって、特定の傾向をもった情報を集中的に流すのではなく、アルゴリズムによって、何であれ、一定の傾向をもった情報が集中的に流れる仕組みを提供する。またマスメディアに代わって、特定のユーザーが、いわゆるインフルエンサーとして、多くのフォロワーを意図的に、また一方的に操作するのでもない。たいていは、ほとんど偶然に、発信されたある情報が反響や共鳴(=エコー)を呼び、閉じた小部屋(=チェンバー)のなかで延々と続くようになるのである。もはや、だれが発信者であるかは重要でなくなり、まさにコミュニケーションがコミュニケーションを再生産するようになる。その意味で、これはネット時代のオートポイエーシスと言えるかもしれない。
これは、プラットフォーム上のあらゆるコミュニケーションについて成り立つといっても過言ではない状況である。ルーマンの長年の論敵であり、90歳を超えて、ネット時代の今日なお研究活動を続けているハーバーマスが、とくに政治的公共圏における新しい構造転換について論じているので、最後に少し紹介しておこう。ハーバーマスの有名な『公共性の構造転換』(Habermas, 1990=1994)は、印刷メディアを主力とするマスメディアの興隆にともなう公共圏の変容を論じたものだったが、近著『新しい公共性の構造転換と熟議政治』では、インターネットの発達によって生じている、新たな公共圏の変容について論じている。マスメディアの場合には、通信社、メディア、出版社のために働くジャーナリスト、つまりメディアや出版社において執筆者、編集者、編集顧問、経営者の機能を遂行する専門家が、情報流通の「ゲートキーパー」の役割を果たしている(Habermas, 2022, pp.39-40)。だがネット社会では、公共圏のプラットフォーム化によってゲートキーパーが存在しなくなり(これまで述べた言い方では、アルゴリズムがゲートキーパーに取って代わり)、公共圏は包括性を失って、さまざまな「半公共圏」のひとつに格下げされてしまうというのである。ハーバーマス自身の言葉に耳を傾けてみよう。
書き手の権限をあたえられたユーザーが自分のメッセージによって注目を集めるのは、構造化されていない公共圏が、読者のコメントとフォロワーの「いいね」によってはじめてつくり出されるからである。そこから自立した共鳴空間が形成されるかぎり、このバブルはさらなるネットワーク化に開かれた透過的性格を古典的な公共圏の形態と共有している。しかしそれと同時に、このバブルは、憶断的で専門職によるフィルターのかかっていない「知識」の固有の同一性を保持するように境界づけられた地平のなかでの、一致しない意見の拒絶と一致する意見の同化的な取り込みによって、公共圏の基本的に包摂的な性格から──また私的なものとの対立から──区別される。自分たちの判断の相互確認によって固定された視野から見ると、それぞれの地平をこえて広がる普遍性要求は根本的に偽善ではないかと疑われる。そのような半公共圏の限られた視点からみると、民主的な立憲国家の政治的公共圏はもはや、真理の妥当と一般的な利害の考慮についての競合する要求の、可能な討議による解決のための包括的空間とは認知されえない。まさしく、この包括的なものとして現れる公共圏は、同じレベルで競合する半公共圏の一つに格下げされる。その徴候は、フェイク・ニュースをばらまくと同時に「嘘つきプレス」に対して戦うという二重の戦略であり、それがまた公共圏と主導的メディアそのものにおける不安定化を呼び起こす。‥‥(Habermas, 2022, pp.62-63)
(5)伝達メディアの発達の傾向

文字の発明から電子メディアにいたる伝達メディアの発達の傾向を、ルーマンは二つにまとめている。一つは、ヒエラルヒー的な秩序からヘテラルヒー的な秩序へむかう傾向であり、もう一つは、全体社会の作動を空間的に統合することの放棄である(Luhmann, 1997=2009, 1, p.350)。
ヒエラルヒーとヘテラルヒーは、対照的な構造をもっている。ヒエラルヒーは、垂直的に分化し、たいていはピラミッド型で、頂点から底辺に末広がりになっている。これに対してヘテラルヒーは、水平的に分化し、頂点があるとしても、いくつもの小さな頂点が散在している。社会全体の構造として見れば、前近代社会はヒエラルヒー的な構造をもつ階層分化した社会であり、近代社会はヘテラルヒー的な構造をもつ機能分化した社会だというのが、ルーマンの社会分化論の基本的な構図である。
伝達メディアとの関連でいえば、このヒエラルヒー/ヘテラルヒーの構造の変化は、社会構造と知識構造の二重の意味で生じている。文字情報の時代は、リテラシーの低さとあいまって、長いあいだ知識は上位階層が独占していた。また、その上位階層の多くは、宗教ないし政治の領域に属していたが、彼らは社会の身分制度におけるヒエラルヒーの上位に位置するとともに、彼らが独占する知識そのものの権威が宗教的ないし政治的な源泉にもとづくものだった。これは、典型的なヒエラルヒーの構図である。しかし、前回の印刷術のところですでに指摘したように、ヨーロッパではすでに写本の時代から、修道院や教会を離れた世俗の仕事として筆耕が存在しており、印刷術の発明によって、世俗での書物の流通がさらに進展するようになった。これは宗教や政治からしだいに分離していく経済的な活動であり、その結果、売れるものは何でも印刷されるようになった。そうなると、知識は上位階層の独占でなくなるだけでなく、その権威の源泉も宗教的ないし政治的なものである必要がなくなった。科学革命や啓蒙主義をへて、世俗的な知識が普及していく時代に、それを最初に享受したのは、経済的な力をつけてきたブルジョアジーであったし、そうした世俗的な知識の権威の源泉は、宗教や政治にとらわれない科学(あるいは学術)になった。これが、ヒエラルヒーからヘテラルヒーへの転換であり、社会構造が階層分化から機能分化に移行するとともに、知識の権威の源泉も、宗教や政治だけでなく科学に求められるようになった。
このようにして成立したヘテラルヒー構造のもとは、電子メディアを含めてマスメディアが主流の時代までは、知識や情報の権威の源泉がある程度保たれてきた。しかしルーマンは、コンピュータの時代になって、専門家の権威の掘り崩しが起こっているという。ルーマンは、20世紀末に「原理的にはそう遠くない将来において」と断っているが(Luhmann, 1997=2009, 1, p.351)、21世紀の現在ではじっさいに、コンピュータを介して蓄積された知識の総体は、個々の権威ある専門家の知識を凌駕し、その蓄積された知識にアクセスすることによって、素人でも専門家の発言を検証することができるようになっている。ただしそれは、専門知識そのものの権威を掘り崩すわけではない。ルーマンによれば、それは具体的な専門家個人の人格への信頼から、コンピュータを介した専門知識のシステムへの信頼への移行である。この点については、ギデンズは「専門家システム」について語っている。ギデンズは、専門家システムを「われわれが今日暮らしている物質的社会環境の広大な領域を体系づけている。科学技術上の成果や職業上の専門家知識の体系」と定義している(Giddens, 1990=1993, p.42)。日常生活において、人びとは個別の専門家との接触はあまりなくとも、専門家が提供する知識の体系を信頼しているというのである。ギデンズのいう専門家システムは、きわめて抽象化されたものだが、具体的にはコンピュータを介して社会に実装されつつある。
現在ではさらに事態は進行し、マスメディアが主流の時代のヒエラルヒー的構造がネットメディアのヘテラルヒー的構造に転換し、システムそのものが不安定化し、システム信頼も揺らいできている。ハーバーマスのいう「フェイク・ニュースをばらまくと同時に『嘘つきプレス』に対して戦うという二重の戦略」は、政治的公共圏だけではなく、あらゆる領域の権威を脱構築しつつある。とりわけ科学的な定説が確立され、常識化されるに至っていない問題についてはその傾向が強い。たとえばコロナウイルスによるパンデミックのように、未知のリスクに対する不安が高まると、その傾向は強まる。専門家の意見も分かれ、素人も加わってデマや陰謀論が飛び交い、何が確かな真実なのか分からなくなる。専門家システムそのものの信頼性が揺らぐのである。そこで、コンピュータのアルゴリズムが生み出すフィルターバブルやエコーチェンバーが、不確実な状況に対する不安を心理的に緩和ないし解消する役割を果たすようになったと見ることができる。そうしたフィルターバブルやエコーチェンバーの世界は、社会全体の構造のなかでは、一種の島宇宙であり、ハーバーマスのいう半公共圏である。この徹底したヘテラルヒー化の進展がもたらすものは、果てしない混沌しかないのか、それとも新たな秩序と権威の出現はありうるのか、今はまだ見通すことができない。
全体社会の作動の空間的統合の必然性の後退についてはどうだろうか。統合がシステムの自由度の制限だとすれば、これまで見てきたように、伝達メディアの発達は、しだいにコミュニケーションの空間を拡大し、いまやネットメディアは完全にグローバル化している。伝達メディアの発達は、文字の発明から印刷術の発明を経て、電子メディアにいたるまで、コミュニケーションを行う人間の身体を、しだいに特定の場所から解放していく。同じ場所でじかに顔を突き合わせなくても、相互のコミュニケーションは成り立つし、事件の現場に居合わせなくても、その場にいるかのように事件の中継動画を体験することができる。また情報や知識のありかも、図書館のような特定の場所から、広く流通する書物、雑誌、新聞を売る書店や駅の売店に拡大し、さらにネットワーク上のサーバーにおかれて流通するようになると、それにアクセスする個人の身体の居場所からしだいに解放されていく。
ここまで全体社会の作動の空間的統合の必然性が後退していくと、われわれの日常生活におけるコミュニケーション体験はどのように変化するのだろうか。ギデンズは、脱埋め込みの概念を補完するために、再埋め込みという概念を提示した。再埋め込みとは、「脱埋め込みを達成した社会関係が、(いかに局所的な、あるいは一時的なかたちのものであっても)時間的空間的に限定された状況のなかで、再度充当利用されたり作り直されていくこと」である。そのためには「顔の見えるコミットメント」と「顔の見えないコミットメント」を区別することが重要であり、顔の見えるコミットメントとは、ともにそこに居合わせている状況のもとで確立する社会的結びつきによって維持されたり、あるいはそうした結びつきのなかに表出される信頼関係、顔の見えないコミットメントは、抽象的システムへの信頼関係をいう(Giddens, 1990=1993, p.102)。両者の関係を媒介するのが、抽象的システムに責任を負う個人や集団と出会う「アクセス・ポイント」である(Giddens, 1990=1993, p.107)。ギデンズは、裁判官、医師、旅客機の客室乗務員などをアクセス・ポイントの例にあげて、一般人が直接アクセスできない抽象的システムのなかの知識や技能を媒介することによって、抽象的システムへの信頼を維持することができるとしている(Giddens, 1990=1993, p.109)。
ところが、コンピュータを介したネット空間でのコミュニケーションにおいては、アクセスのための電子端末そのものが、そのような顔の見えるコミットメントを可能にするようなアクセス・ポイントに取って代わりつつある。デジタル・ノマドと呼ばれる人びとは、特定の固定された住居や仕事場をもたず、電子端末をたずさえて自由に空間を移動しながら、ギデンズのいう意味でのアクセス・ポイントではなく、ネット空間へのアクセス・ポイントに電子端末を接続する。つまり、みずからをネット空間に接続する。もちろん、日常生活すべてをネット上で行うわけにはいかないが、多くのコミュニケーションを顔の見えるコミットメントなしで行うことが可能になってきているのである。顔の見えるコミットメントのために、当事者どうしが同じ場所に居合わせることが必要だとしたら、コロナ禍を契機として普及したリモートの会議や授業は、すでに顔の見えるコミットメントの要件を逸脱している。スクリーンに映る出席者の顔、さらに技術が進めば実現するであろう三次元ホログラムが、顔の見えるコミットメントを代替しうるかどうか、つまり従来の現実の空間としての会議室や教室におけるアクセス・ポイントの完全な機能的等価物になりうるかどうかは、定かではない。メタバースのような試みは、ギデンズのいう意味でのアクセス・ポイントそのものを仮想的な空間のなかで作ろうとしていると言えるかもしれないが、これも自由にアバターを設定できるようにすることによって、本来的な意味での顔の見えるコミットメントにはなりえないだろう。
ワールド・ワイド・ウェブやその中で構築されたさまざまなプラットフォームは、成立時の理想としては、権力による検閲を排除し、万人のアクセスと言論の自由を保証しようとするものだったかもしれない。それは、ある意味でハーバーマスが考える理想的な公共圏のためのインフラストラクチャーになりうるものだったかもしれない。なぜなら、それらは任意の人によるアクセスを許し、アクセスをコントロールすることを放棄することによって、空間的な統合を構造的に無規定にしておくからである(Luhmann, 1997=2009, 1, p.353)。たしかに、そのようにして成立したネット上のコミュニケーション空間は、作動の空間的統合を必要としなくなった。だがそれと同時に、プラットフォームのアルゴリズムによって徹底したヘテラルヒーが生まれ、言論の自由を錦の御旗にファクト・チェックが廃され、ありとあらゆる情報が飛び交うなかで、きわめて偶発的なコミュニケーション空間が一時的に成立するだけになってきているように思われる。もちろん、アメリカの大統領選挙について論じられているように、フェイスブックのデータを解析したケンブリッジ・アナリティカの結果にもとづいて、意図的に投票行動を操作する試みがなされるような事象が現実に起こったことによって、ネット空間の公共圏の理想は無残に潰えた幻想にすぎなかったという言い方もできるだろう(Seeliger/Sevignani, 2021)。ヘテラルヒー化し、作動の空間的統合を必要としなくなった伝達メディアの行方は、現時点では不透明といわざるをえない。
ようやく伝達のメディアの現在まで議論が進んだ。この部分は、一般的な意味でのメディア史の研究領域である。ルーマンのコミュニケーション・メディアの議論では、理解、到達という二つの非蓋然性の克服の先に、さらに成功の非蓋然性が待ち受けている。この成功の非蓋然性を克服するために発達したのが、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアと呼ばれるものである。すでに前回指摘したように、この成功の非蓋然性は、ルーマンの考える情報、伝達、理解の統一体としてのコミュニケーションには含まれず、コミュニケーションによって開かれる行動の選択の問題である。そして、この問題が重要なのは、コミュニケーションが社会的な意味構成だからである。この問題は、パーソンズやルーマンによって、社会学に固有のメディア論として論じられてきた。これについては、機能分化の問題とも関連させながら、次回あらためて論じたい。
参考文献
Giddens, Anthony, 1990, The Consequences of Modernity, Polity Press.(松尾精文・小幡正敏訳『近代とはいかなる時代か? モダニティの帰結』而立書房、1993年)
Habermas, Jürgen, 1990, Strukturwandel der Öffentlichkeit Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Suhrkamp Verlag.(細谷貞雄・山田正行訳『公共性の構造転換 市民社会の一カテゴリーについての探究』未來社、1994年)
Habermas, Jürgen, 2022, Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik, Suhrkamp Verlag.
Luhmann, Niklas, 1996, Die Realität der Massenmedien, Westdeutscher Verlag.(林香里訳『マスメディアのリアリティ』木鐸社、2005年)
Luhmann, Niklas, 1997, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp Verlag.(馬場靖雄・赤堀三郎・菅原謙・高橋徹訳『社会の社会』1・2、法政大学出版局、2009年)
Seeliger, Martin/Sevignani, Sebastian (Hrsg.), 2021, Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit? Leviathan Sonderband 37, Nomos Verlag.