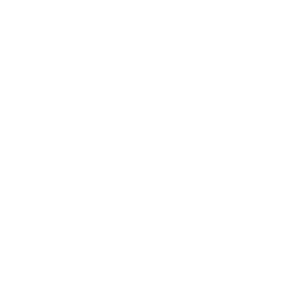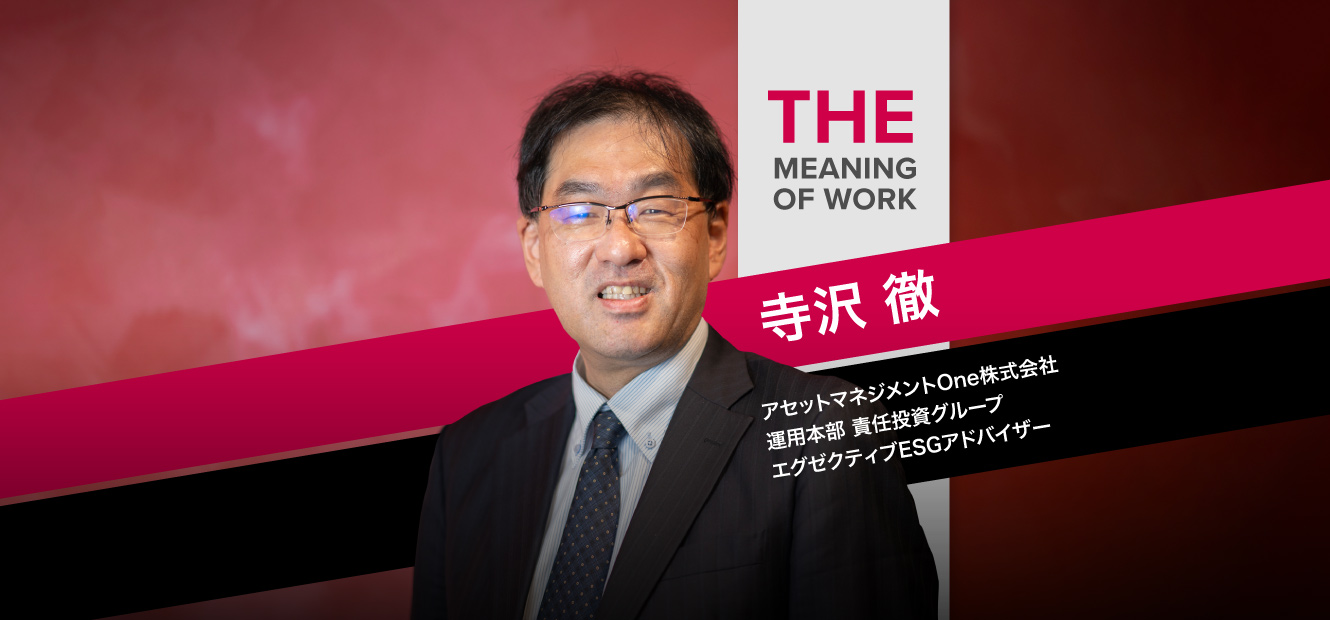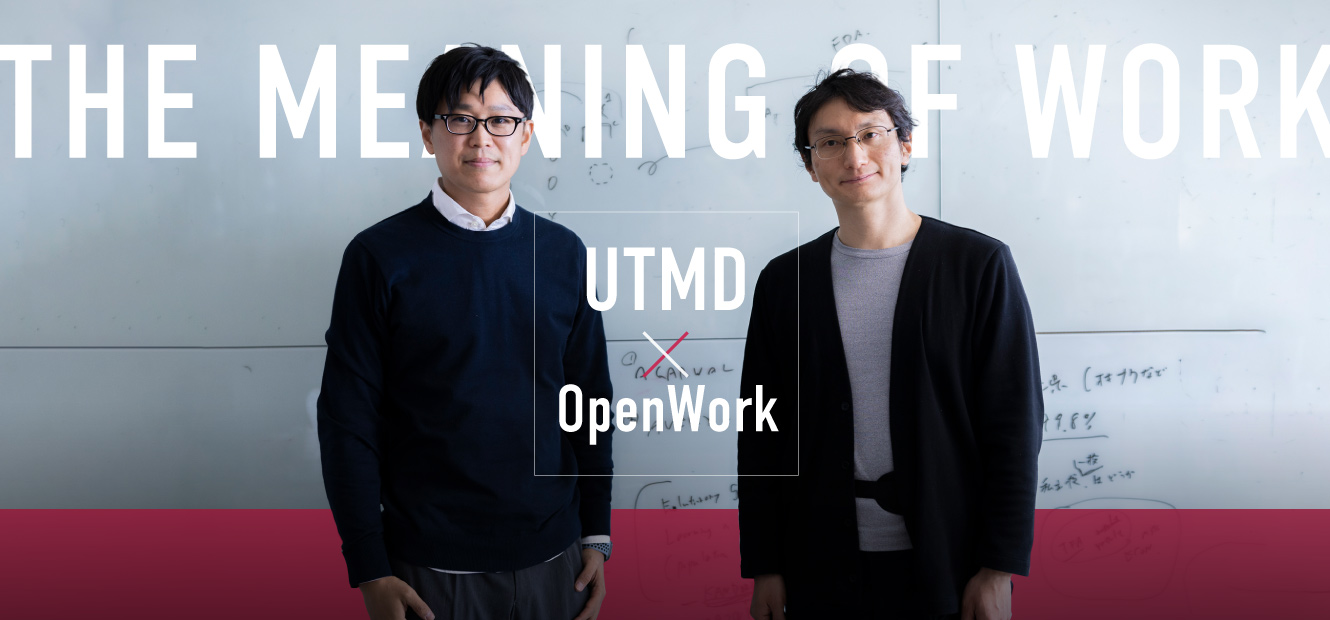Park Lineが描く未来の公共空間の可能性
-

前田 賢治KENJI MAEDA
一般社団法人Park Line推進協議会 事務局長同志社大学商学部卒業。大成建設(株)入社。国土交通省と経済産業省の共管シンクタンク「一般社団法人日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)」にて公共政策研究、環境まちづくりプロジェクトに従事後、営業企画、国策連動のナショナルプロジェクト(オリンピック、IR等)に従事。2020年、Park Line推進協議会の立ち上げに参画。事務局長に就任。中小企業診断士。
-

林 幸弘YUKIHIRO HAYASHI
株式会社リンクアンドモチベーション
モチベーションエンジニアリング研究所 上席研究員
「THE MEANING OF WORK」編集長
早稲田大学政治経済学部卒業。2004年、(株)リンクアンドモチベーション入社。組織変革コンサルティングに従事。早稲田大学トランスナショナルHRM研究所の招聘研究員として、日本で働く外国籍従業員のエンゲージメントやマネジメントなどについて研究。現在は、リンクアンドモチベーション内のR&Dに従事。経営と現場をつなぐ「知の創造」を行い、世の中に新しい文脈づくりを模索している。
急速に進む公共インフラの老朽化は、深刻な社会課題となっている。人々の暮らしを豊かで安全なものにするために。増大するコストを最適化するために。公共インフラ市場の「民間開放」を牽引するのが、一般社団法人Park Line推進協議会だ。未来の公共空間創造に挑む、同協議会事務局長・前田賢治氏に話を聞いた。
Park Line推進協議会とは
Park Line推進協議会は、将来の公共インフラのあり方、公共空間の新たな活用方策、および民間マネジメントによる公共空間の質的転換など、「公共空間マネジメント」の観点から設立された、社会・地域の課題解決に資する「中間支援組織」。民間主導による公共空間マネジメントを切り口とした地域共創プロジェクトの推進を通して、全国展開で持続的な地域価値向上の実現を担っている。
主な事業領域
(1)ターゲットエリアの地域診断、成長戦略の策定
(2)ターゲットエリアの環境・経済・社会の課題解決に資する地域連携・地域共創プロジェクトの推進
① 基盤整備(グリーンインフラ×インフラ分野のDX)
② 周遊交通(ウォーカブルを補完するグリーンスローモビリティ)
③ 地域資源活用(観光まちづくり、公共空間・歴史的資源を活用したまちづくり)
④ 地域経営(エリアマネジメント)
(3)まちづくりに関する行政機関、まちづくり協議会などとの情報共有、連絡調整、および意見提案
一般社団法人Park Line推進協議会 オフィシャルサイト公共空間を革新するソーシャルビジネス。

 |
林
Park Line推進協議会(以下、Park Line)が生まれた社会背景についてお聞かせください。 |
 |
前田
急速に進む公共インフラの老朽化は重大な社会・地域課題です。維持管理・更新費などのコストは大幅に増大し、それらを管理する自治体の財政も厳しい状況にあります。さらには、インフラ技術者の不足などにより、これまでと同様の運用を維持・継続していくことも難しくなっているのです。こうした状況のもと、国は官民連携による公共インフラ市場の「民間開放」を進めており、公共インフラにも「経営的な視点」を持って戦略的に維持管理、運営、更新を行うマネジメントモデルが求められるようになりました。 |
 |
林
民間の叡智を結集して、これからのまちをつくっていこうというわけですね。 |
 |
前田
今後の人口動態を見据えると、これからは、まちを広げていく時代ではありません。都市の既存ストックの質を持続的に高めていくことが求められていると言えるでしょう。まちづくり視点では、都市は「図」(建築)とそれをつなぐ「地」(公共空間:道路、公園、水辺など)で構成されます。これまで、民間が関与できるのは、「図」の部分のみ。「地」は、行政の所管でした。近年、2017年の「公園の民間開放(Park-PFI)」を皮切りに、「地」、すなわち公共空間は、国策として、道路、水辺も含め、段階的に民間に開放されつつあります。既存ストックの質を高めていくうえで、特に私たちが着目しているのは、都市の約25%を構成する「道路」です。「道路」が変われば、まちも変わる。そう考えています。 |
 |
林
Park Lineは中間支援組織ということですが、具体的にどのような活動を行っているのですか。 |
 |
前田
自治体の上位計画策定の段階から並走し、行政と地域、あるいは、行政と民間企業をつないでいく活動です。どちらかというと、ソーシャルビジネスに近いかもしれませんね。自治体や地域経済界など、地域のステークホルダーと連携しながら、民間主導による公共空間マネジメントを切り口とした地域共創プロジェクトを推進し、持続的な地域価値の向上を目指しています。まちづくりの担い手は、官か民かの二択ではなく、ファウンデーション(財団、基金)やPark Lineのような中間支援組織なども入れながら、ポートフォリオを増やしていく必要があると考えています。 |
 |
林
まちづくりのオープンイノベーションを牽引する役割を果たされているのですね。Park Lineが目指すのは、どのような公共空間なのでしょうか。 |
 |
前田
Park Lineが目指しているのは、自宅のリビングのように過ごすことができる質の高い公共空間を実現すること。私たちはその概念に「Open Living」という名前をつけました。これまでの「地」は「図」に至るまでの通り道でしかありませんでしたが、道路などの公共空間を「Open Living」化し、連続させていくことで、まちの回遊性・滞留性・快適性の向上が実現します。 |
その理念は、選ばれるまちを創る。

 |
林
Park Lineの活動が社会課題、地域課題を解決するソーシャルビジネスであるならば、その価値を提供するメインターゲットは、その地域に住み、働き、学ぶ市民ということになりますね。 |
 |
前田
そうですね。「生活空間の拡張領域としてのパークライン(Line)」によって、より豊かな生活を実現すること。そして、「にぎわいと商業空間としてのパークライン(Node)」によって、地域経済を活性化し、コミュニティーの魅力を引き出すこと。これら2つの軸からアプローチすることで、価値を提供していきたいと考えています。市民にとって居心地が良く、誇りに思えるまちは、インバウンドを含む来街者から見ても魅力的に映るもの。地域社会や住民のQOLの向上、シビックプライドの醸成を図り、「住んでよし」「訪れてよし」の好循環を生み出したいと考えています。 |
 |
林
確かに、そうした都市には大きな魅力がありますね。私自身、スペインのバルセロナを観光した時に、魅力的な公共空間の力のようなものを感じました。 |
 |
前田
バルセロナは市内全域に歩行者空間化を適応することにより公共空間の質的転換を実現した代表的なまちです。そうした都市は、持続的にエリアの価値が高まり、世界的にも「選ばれるまち」になっています。市民の満足度が高く、来街者も魅了される。都市計画における世界の潮流として、近年、居住地を起点に生活に必要な場所(公園、カフェ、スポーツ施設、病院、学校、職場など)に15~20分以内にアクセスできるまちづくりの考え方があります。パリの「15-Minute City(15分都市)」やポートランドやメルボルンの「20-minute Neighborhood(20分生活圏)」構想などです。私たちが推進する「Open Living」も、これらの都市計画と連動したものになっています。 |
 |
林
Park Lineでは、ICTインフラを活用したスマート・グリーンシティの実装にも取り組んでいます。こちらも世界のトレンドですよね。 |
 |
前田
はい。ただし、ICTはあくまで手段であって、目的ではありません。私たちはICTの活用による「コミュニティーの創造」というアウトカムに軸足を置いています。確かに、経済的価値から見ると、効果的・効率的なまちづくりの追求は重要ではありますが、社会的・文化的価値も加味すると、ICTインフラを活用する場面や可能性は、もっと広がるでしょう。「都市はコンピューターではない」といわれて久しいですが、まさにそのとおりだと思いますね。 |
公共空間の質を変える革新的チャレンジ。

 |
林
Park Lineではさらに、公共空間の質を転換するさまざまな取り組みを実践されています。具体的にどのようなプロジェクトを行っているかお聞かせください。 |
 |
前田
横浜の都心臨海部では、日本大通りの「Open Living」化実証(2022年)、山下公園における歩行者共存型の自動走行モビリティ実証(2023年)に続き、直近では、横浜みなとみらいエリアで2024年12月21日~3月23日にかけて、モビリティハブ「グリーン・マルチモビリティハブステーション」の社会実証を実施しました。みなとみらいエリアは、週末やイベント開催の度に、来街者が自家用車でまちに流入するため、まちの中心部では、常に渋滞が発生するという地域課題を抱えています。そこで、地域課題解決の観点から、「パーク&ライド」の実現と、域内の移動そのものを楽しむ「まちを楽しむ多彩な交通の充実」を「脱炭素」の切り口で実現するために行われたのが同社会実証です。これまでにないシェアリングモビリティの種類・設置台数を完備した大規模なモビリティハブ※を設置し、利用者の移動の選択肢の幅を広げることに加え、日本の気候風土を踏まえた居心地の良い滞留・快適空間を具備したモビリティハブのショーケース。まちの回遊性・滞留性・快適性向上に向けた新しい都市インフラの提案です。この社会実証は、実装を強く意識した約3カ月にも及ぶ長期の取り組みで、実施主体は、Park Line単体ではなく、神奈川県オールトヨタ販売店が運営する(株)アットヨコハマと日産自動車(株)との共創型推進体制による、企業の枠を超えた有意義なチャレンジでした。民間主導による公共空間の質的転換を通して社会・地域課題の解決を目指す、地域共創プロジェクトの優良事例になったのではないでしょうか。Park Lineが有するまちづくりのノウハウは社会実証の機会を通して全てオープンにしています。 |
 |
林
Park Lineが手がけるプロジェクトは、さまざまな企業・団体が社会・地域課題の解決のために参画しています。現状、多くのオープンイノベーションプロジェクトがなかなか成果を出せずにいる中で、確かな成果を出せていることは大きな驚きです。 |
 |
前田
ありがとうございます。もうひとつ、観光まちづくり分野では、2024年1月、横浜にある国指定名勝「三溪園」における、重要文化財の特別公開、および市指定有形文化財(通常時は内部非公開)での宿泊体験プログラム「滞在型ラグジュアリツーリズム」を企画・プロデュースしました。「三溪園」は東の桂離宮とも称され、歴史的建造物にとどまらず、四季折々に花の名所として楽しむことができます。本プロジェクトは、観光庁の富裕層インバウンド向け事業「観光再始動事業」に採択されました。 |
 |
林
国指定名勝の貸切利用、文化財での宿泊。とても魅力的な体験になりますね。 |
 |
前田
地域の歴史・文化資源の活用は観光まちづくりの大きなテーマとなります。こうした文化財は今後、増える一方です。それらを保全するために税金を投入し続けるのでは、地方自治体の負担は今後ますます厳しいものになっていくでしょう。文化財を「保存」から「活用」へ転換していく流れは国の方針として打ち出されていますが、ここにコミットするプレイヤーはまだまだ少ないのが現状です。私たちはこの流れにいち早く着目し、本プロジェクトを実行しました。プログラム自体は貸切1組限定で行うというものでしたが、横浜の歴史・文化資源の新たな活用可能性を検証し、インバウンド誘客を促す観光コンテンツ造成を図る上で、意義ある取り組みになったといえるでしょう。 |
それぞれの枠を超えて社会課題を解決する。

 |
林
「社会のために」という同じ志を抱いた仲間が集い、新たな価値創造に挑む。大きな可能性を感じますね。こうした社会実証を経て、これからどのようなまちが実現するのか。私たち市民にとっても大きな楽しみです。 |
 |
前田
まちづくりは、いきなり新たな価値を実装できるようなものではありませんし、一度、何かを仕掛けて終わりというものでもありません。社会実証を積み重ね、地域のニーズや課題を棚卸ししながら、地域のステークホルダーとの意思統一を図り、螺旋階段をゆっくり上るようにして実現していくものです。大切なのは、「過去に学び」(原点回帰)、「未来を創造」すること。プロジェクトを推進していくうえで、迷いが生じた時は、ヘーゲルの弁証法にある「螺旋的発展の法則」に立ち返ることにしています。私たちが目指す課題解決とは、マイナスをゼロにするのみならず、新たな価値を創造していく一連のエコシステムを構築することです。志を同じくするパートナーとともに、それができればこれ以上の幸せはありません。 |

虹を見たければ雨を楽しもう。

 |
林
前田さんが民間主導による新たな公共空間の創造に挑む理由は、どこにあるのでしょうか。 |
 |
前田
日本のために、社会のために、未来のために、所属する組織の枠を超えて、共に価値を創造する喜びを知っているからでしょうか。原体験のひとつとして、かつて私が出向していた一般社団法人日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)での経験が大きいです。本団体は、産・官・学・民が一丸となって、「防災・減災・国土強靭化」、「国際立地競争力強化」、「地方活性化」の切り口から持続的な国の成長戦略を構想し、プロジェクト推進までを一気通貫で担う公益法人です。独立非営利、世界目線、まちづくり視点の立ち位置で、東京湾横断道路(東京湾アクアライン)、幕張メッセ、関西国際空港などのナショナルプロジェクトの推進に貢献してきた団体での研究員としての経験は、現在、私が取り組んでいる中間支援組織としてのPark Lineの活動に活かされています。民間企業や政府、大学、研究機関などが連携して、日本の社会課題の解決に取り組む。その過程で得られたやりがいや、今でも同志と呼び合える仲間は、私にとって唯一無二の財産になっています。 |
 |
林
その喜びを知っているから、さらなるチャレンジを続けていく。とても素敵な理由ですね。 |
 |
前田
ただ、現実はそうキレイなものではありませんでした。Park Lineは、今でこそ、国、自治体、地域経済界からの外部評価も高まり、認知されるようになりましたが、発足当初は知名度もなく、心の折れそうな日々が続きました。 |
 |
林
でも、そこで心の灯が消えることはなかった。 |
 |
前田
私の好きな言葉に「虹を見たければ、雨を楽しもう」という言葉があります。ゴールだけに喜びを求めるのではなく、思いどおりにいかない時の苦しさや、困難な壁すらも「学び」の機会として楽しみながら前に進むべきだと考えています。そして、何より、困難を乗り越えた先に得られる社会の評価や、「Open Living」化された公共空間を楽しむ人たちの笑顔は、私にさらなるパワーを与えてくれています。それぞれの所属や地位に関係なく、多くの価値観に出会い、志を1つに新たなチャレンジに向き合う。これほどおもしろいことはありません。さらなる価値創造に挑戦し、もっとキレイな虹を見にいきたいものです。 |