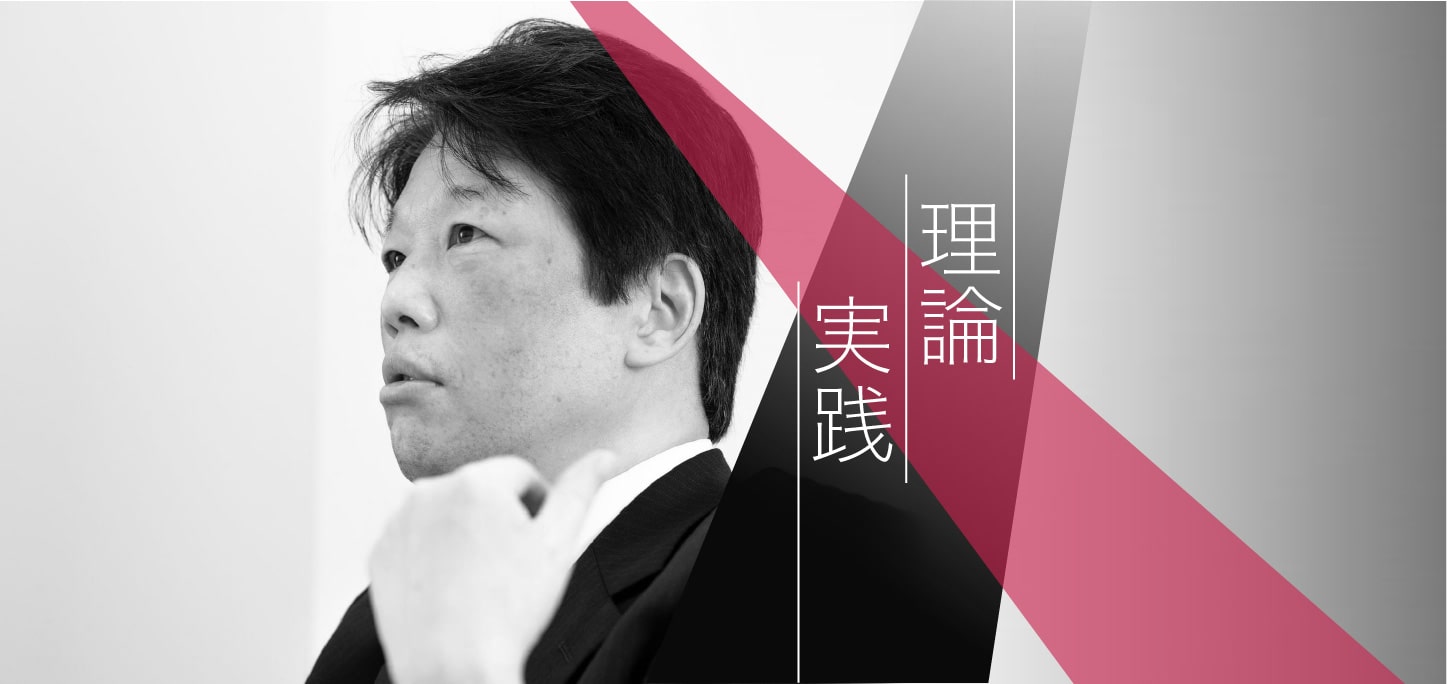第1回 思想のなかのシステム
-

徳安 彰AKIRA TOKUYASU
法政大学社会学部教授東京大学文学部社会学科卒業。同大学院社会学研究科博士課程修了。法政大学社会学部専任講師、同助教授、ビーレフェルト大学客員研究員、法政大学社会学部教授、法政大学社会学部学部長を歴任。共著に『社会理論の再興』(ミネルヴァ書房)、『理論社会学の可能性』(新曜社)など。
このコラムは、ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンの社会システム理論の理論的、実践的な解説を目的としている。本論に入る前に、ルーマンの社会システム理論を理解する助けとなる理論的、思想的な背景を2回にわたって素描し、それにもとづいてルーマン理論の解説に進む。第1回は、ヨーロッパの社会思想や哲学における社会システムのイメージを知るために、システムという言葉の意味から出発して、個人主義と集合主義、要素還元論と全体論の対立を概観し、集合主義や全体論の立場から出てくる社会システムが、人間にとって一種の異物として捉えられることによって、社会システムが人間の主体性や自由を抑圧するものとしてイメージされる契機を明らかにする。
はじめに

このコラムは、ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンの社会システム理論の理論的、実践的な解説を目的としている。ルーマンの理論は、社会の全域を射程におさめ、一般システム理論やサイバネティクスから思想史まで多様な領域の理論や概念を援用し、きわめて抽象的なレベルで展開されている。またルーマンの理論は、1980年代に入って「オートポイエーシス的転回」を遂げ、その前後で用語や概念が大きく変わっており、どの時点の理論を取り上げるかによって、解説の前提まで変わってくる。さらに、その著作は、書籍、論文とも膨大な数にのぼり、専門の社会学者でさえ、どこから取りついたらいいのか見当がつきにくい。多くの邦訳もあるが、翻訳にありがちなことで、すべての邦訳で基本的な用語の訳が統一されているわけではないことも、ドイツ語にアクセスできない読者の理解を困難にしている。
このコラムでは、まず2回にわたってルーマンの社会システム理論を理解する助けとなる理論的、思想的な背景を素描し、それにもとづいてルーマン理論の解説に進むことにしよう。ルーマン理論を理解するための背景として、ヨーロッパの社会思想や哲学における社会システムのイメージあるいは概念の捉え方と、一般システム理論やサイバネティクスにおけるシステムの概念の捉え方の2つを挙げたい。
ルーマンは、ドイツの社会学者なので、ヨーロッパの知的伝統の文脈のなかで理論構築を行っている。その知的伝統のなかには、社会システムの概念にかんして、ルーマン理論の理解の鍵と同時に、誤解の契機もふくまれている。とくに、いわゆるハーバーマス=ルーマン論争におけるハーバーマスの批判に関連させながら、社会システム観の違いについて考えてみたい(第1回)。またルーマンは、一般システム理論やサイバネティクスの理論や概念を援用しているので、その基本的な理解も必要になる。これらの理論がシステムをどのように概念化してきたのか、概観することにしよう(第2回)。
システムという言葉は何を指すのか

はじめに、そもそもシステムとは、どのようなもの、こと、状態を指す言葉なのか。英語圏でもっとも網羅的で権威ある辞典とされる、オックスフォード英語辞典(Oxford English Dictionary:OED)のオンライン版の「システム(system)」の項目から見ていこう。現在通用している用法のなかで、このコラムのテーマに関連しそうなものを項番つきで抜き出すと、次のようになる。
Ⅰ.組織された、あるいは関係づけられた、ものの集合
3.
a. 統一体あるいは複雑な全体と解されたり思われたりする、関係づけられた、あるいは結合された、ものの集まり、あるいは集合。
b. 結合するネットワークの部分として協働する人びとの集合。
c.
(a) 機械、道路、建築物などの構成要素として、特定の目的のために組織された人工物の集まり。
d. 結合された全体あるいは複雑な全体と考えられる、あるいはそれを形成すると考えられる、自然物、特徴、あるいは現象。
5.
a. 生物学:共通の構造あるいは機能をもつ器官、その他の身体部分、あるいは組織の集合。通常は弁別的な言葉をともなう。
b. 定冠詞または所有形容詞をともなう。全体としての身体(あるいは身体と精神)およびその生命機能。
11. コンピューティング
a. コンピュータ、典型的には結合されたハードウエアとソフトウエアをともなうと考えられる;ネットワーク化されたコンピュータの集まり、とりわけ単一の用途専用のもの。
b. 関係づけられた、あるいは結合されたプログラムの集まり。
Ⅱ.原理、信念などの集合;枠組、方法
14.
a. 組織された行為の枠組ないし計画、とりわけ複雑あるいは包括的なもの;手続き、統治、経営などの秩序立った、あるいは規則的な方法。
d. 定冠詞をともなう
(a) 行き渡っている政治的、経済的、社会的秩序、とりわけ抑圧的あるいは重苦しいとみなされるもの;権力機構;何らかの非人格的、拘束的な組織。しばしば大文字のイニシャルをともなう。
これらの項目で指されているもの、こと、状態は、具体的にはそれぞれがかなり異なっている。これらの項目以外にも、音楽、天文学、韻律学、結晶学、層序学、気象学、化学、言語学などの領域でシステムと呼ばれる指示対象が挙げられており、システムという用語がじつに多様な意味内容をもっていることがわかる。現在では使われなくなっているが、被造物の全体系、宇宙そのものを指す用法も、かつてはあったとされている。まずは、Ⅰの「組織された、あるいは関係づけられた、ものの集合」だけでなく、Ⅱの「原理、信念などの集合;枠組、方法」もシステムと呼ばれてきたことを押さえておきたい。Ⅰは多様な領域における具体的で経験的な対象のあり方を指しており、Ⅱはとくに人間社会の領域における諸活動の原理を指している、と考えることができる。
システム理論と呼ばれる研究分野においても、これらすべてを網羅する一般原理が追究されているわけではない。一般システム理論を提唱したベルタランフィの出発点は5.a、5.bという生物学の対象領域であり、そこから抽出した開放システムの原理を他の対象にまで拡張しようとしたと考えることができる。サイバネティクスを提唱したウィーナーの出発点は3.c.(a)という工学の対象領域であり、そこから抽出したフィードバックの原理を他の対象にまで拡張しようと考えることができる。社会システム理論が主要な対象とするのは、3.b、14.a、14.d(a)であり、それを概念的により精緻化しているといえるだろう。一般システム理論やサイバネティクスの話は次回にまわすことにして、今回は、社会思想のなかでシステムがどのように考えられてきたのかということ、つまり社会システムという概念のもつ意味に焦点を合わせることにしよう。社会システム観の違いにかんしてとくに焦点となるのは、14.d(a)の用法である。
社会思想のなかの個人主義と集合主義

社会思想のなかには、社会のあり方について、個人主義と集合主義という二つの考え方がある。両者の概要を図式的に比較してみよう。
個人主義は、まず独立した諸個人がいて、その諸個人はそれぞれが主体的に考えて行動することができ、協力、協働が必要なかぎりにおいて、関係を結んで社会を形成すると考える。つまり、社会は諸個人の協力の意志にもとづいて形成されるし、形成された社会に何か不具合や不都合があれば、諸個人の意志によって変化させることができる、ということになる。OEDの3.bの用法はこれに近い。この用法はかなり古くからあり、OEDには1651年に発表されたトマス・ホッブズ『リヴァイアサン』の用例が載っている。(もちろんホッブズの理論は社会システム理論とはいわないが)。
じっさい、社会の規模がきわめて小さければ、社会を構成するメンバーの諸個人も見えやすいし、一人の行動の影響力もわかりやすいから、このような個人主義的な社会観はもっともに思われる。しかし現代のように、少なくとも数百万人、多ければ数億人が構成している一つの社会(とりあえず国家を単位とした社会)を思い浮かべると、社会が形成されるために諸個人が明確で主体的な協力の意志をもっているとも考えにくいし、諸個人の意志によって社会をいかようにも変化させることができるとも思えない。むしろ、一人ひとりの個人は、社会に対する自分の影響力について、無力感にかられてしまうのではないだろうか。
英語で「社会」を意味する‘society’には、他にもいくつかの用法があり、その中には「協会、団体」といったものを指すものがある。学会などの英語の名称にもよく使われている。現代風にいえば、ある目的を達成するために作られた組織が一つの典型であろう。こちらであれば、個人主義的な社会観があてはまりそうだが、それでも組織の規模が大きくなるにつれて、個人主義的な前提は成り立たなくなるように思われる。同じ「組織」という名称で呼ばれても、少人数で起業したばかりの零細企業ならいざしらず、数万人、数十万人を擁する巨大企業では、個人の力で何かを成し遂げるのは容易ではない。無力感にかられると、しょせん自分は会社の歯車、などと愚痴の一つもでてくる。
他方、集合主義は、まず社会が存在し、諸個人はその中でさまざまな社会的制約をうけて行動している、と考える。協力や協働も、諸個人の内発的な動機によるものというより、むしろ社会的な必要にもとづく強制とみなされる。人類学や民族学で扱われる部族社会では、小規模であるにもかかわらず、人びとは個々人の主体的な意志ではなく伝統による社会的制約にもとづいて行動していると考えられる。また、われわれが歴史で学ぶ古代から近世までの社会では、ほとんどの場合に強大な権力をもった王や君主(支配者、統治者)が存在し、その権力の強制力のもとで人びとは生活し、行動してきた。権力に服従する社会の大部分の人びとにとって、自分たちの主体的な意志によって社会を形成するなどという発想はなかったものと考えられる。
現代の民主主義の社会では、強大な個人の権力者は排除され、すくなくとも建て前としては、一人ひとりのメンバー(市民)が主体的な意志を発揮して、全体としての社会を形成することができるとされている。しかし、社会の規模が大きくなり、構造が複雑になるほど、社会は個々のメンバーにとって見通しのきかないものになり、かりに社会を変革しようという意志はあっても、どのようにしたらじっさいに社会を変化させることができるのか、見当がつかなくなる。場合によっては、社会の側が個人の主体性を抑圧しているようにさえ思われるのだが、特定の権力者が存在しないだけに、何に抵抗していいのかもわからない。大規模組織でも同じような状況が生まれてくる。OEDの14.d(a)の用法は、このような事態を指している。
また、大規模な社会や組織で大きな問題が発生したとき、問題の原因は特定の個人の行動ではなく「構造的」な問題だ、としばしば言われる。この場合の「構造的」は「システム的」と言いかえてもよい。個人主義的な考え方だと、問題を生み出すのはあくまで特定の個人または複数の個人たちであり、かれらの行動の結果として問題が発生するのだから、責任もかれらにあるということになる。しかし、集合主義的な考え方だと、問題を生み出すのは複雑な社会や組織の構造の矛盾や機能不全であり、特定の個人の誤りや悪意にもとづく行動ではないから、特定の個人に責任を帰属させるのが難しいということになる。犯罪の場合、刑法上は犯人を特定し、その動機や意図を解明し、それによって犯人に刑事罰を科すわけだが、ときどき「そのような犯罪を生み出したのは社会だ」とか「犯人もまた社会の矛盾の犠牲者だ」という言い方がされるのも、一種の集合主義的な見方といえよう。また政治や経営の領域では、しばしばトップの責任が問われるが、実質的に全権を掌握している独裁者はすくない。だが、構造的な問題であっても、形式的な権限と責任が集中している地位にあるという理由で、トップはその問題の責任をとらざるをえないのである。
ちなみに、集合主義は、全体主義や社会主義ともいわれるが、これらの名称は、とくに20世紀初頭に成立したソビエト連邦に始まる現実の社会主義国家、あるいはナチスドイツ(ナチスの正式な政党名は国民社会主義ドイツ労働者党であり、ここにも社会主義という言葉が入っている!)を典型とするようなファシズム国家の権威主義的専制を思い起こさせ、ネガティブなイデオロギー的含意をもっているため、避けられることが多い。ただし、社会主義という言葉の名誉のために言っておけば、この言葉は19世紀前半、フランスの社会思想家ピエール・ルルーに端を発するとされ、ルルー自身は個人主義に対抗する理念を表す言葉として用いている(今村、1998)。ルルーの用法は、のちにマルクス/エンゲルスによって空想的社会主義と呼ばれるサン=シモンやフーリエなどの社会主義の、個人主義や自由主義に対して社会的な共同性を重視するという理念を表している。マルクス/エンゲルス以降、社会主義は資本主義の対立項になっていく。ちなみに、1980年代ごろから盛んになった、リバタリアニズムとコミュニタリアニズムの論争も、個人を優先するのか、共同体を優先するのかという点で、この個人主義と集合主義の問題の伝統に連なるものである。
社会思想における、以上のような個人主義と集合主義の対比は、社会学のなかでは「個人と社会」の問題として古典的に定式化された。社会システム理論では、「社会」という概念は「社会システム」という概念におきかえられる。じっさいには、社会に対置される「個人」の側も別のかたちで概念化されているのだが、詳しくはルーマン理論の解説のさいに紹介することにして、とりあえず、図表1のように、やや実体的に図式化してみよう。この図表では、右向きの矢印が「諸個人が社会システムをつくる」「諸個人の相互作用の結果として社会システムが生まれる」という個人主義的な考え方を表しており、左向きの矢印が「社会システムが諸個人(の行動)をつくる」「社会システムの規制の結果として諸個人の相互作用が生まれる」という集合主義的な考え方を表している。社会学のなかには、現実の社会過程では二つの矢印の作用がどちらも存在し、両者は円環的で弁証法的な関係になっている、という考え方もあるのだが、それを理論的に明瞭に定式化するのは容易ではない。さしあたり、個人主義と集合主義の対比では、つねにどちらか一方が強調されてきたことを確認しておきたい。

古典社会学のなかの個人主義と集合主義

個人主義と集合主義の思想は、古典社会学のなかにもさまざまなかたちで現れている。いくつか典型的なものを見ていこう。
最初は、社会学という言葉を作ったという意味で、社会学の祖とされるフランスのコント(Auguste Comte, 1798-1857)である。コントが生きた19世紀前半のフランスは、政治的にはフランス革命の後、ナポレオンの帝政、王政復古、共和制、ナポレオン三世の帝政とめまぐるしく体制が変わり、経済的にはイギリス発の産業革命の影響が大陸にも及んで経済発展が進む時代だった。フランス革命によって大きな社会の転換が始まったが、新しい社会の姿はかならずしも明確になっておらず、さまざまな社会構想が論じられた時代である。
サン=シモンやフーリエの社会主義思想も、そのような時代のなかで生まれてきた。かれらよりもすこし世代の若いコントは、そのような時代の流れのなかで、人類の精神的側面について、神学的、形而上学的、実証的という三つの発展段階を考え、それに対応する社会的側面について、軍事的、法律的、産業的という三つの発展段階を考えた。コントは、社会学という学問の名称からもわかるように、第一に社会のあり方を重視した集合主義的な立場をとっており、次の引用でもわかるように、社会がまず存在するのであって、「人間」や「個人」はすべて社会の産物であるとまで述べている。社会思想としては、この考え方はサン=シモンやフーリエの社会主義思想と同根とみなすことができよう。図表1にそくしていえば、社会システムが諸個人をつくるという左向きの矢印を強調していることがわかるだろう。
‥‥実証的精神は、まさにその特徴である現実性の結果として、可能な限り、しかも何の努力も要さずして直接に社会的である。この精神から見れば、固有の意味での人間は存在しない。存在するのは人類だけである。なぜなら、人間の発達は、どの角度から考えても、すべて社会によるものだからである。もし、「社会」という観念が依然として知性の抽象的産物のように思われるとしたら、それは主として古い哲学体制の影響である。なぜなら、少なくとも人類にあっては、抽象的性格を持っているのは、実は「個人」の観念のほうだからである。新しい哲学の全体は、実際生活においても思索生活においても、ひとりの人間が多種多様な局面で他のすべての人間と結びついていることを常に強調するように努めるだろう。そして、私たちは、あらゆる時と場所に正しく拡大された社会的連帯という深い感情に、知らず知らずのうちに親しむことになるであろう。(Comte, 訳pp.205-206)
つぎに、イギリスにおける社会学の祖といわれるスペンサー(Herbert Spencer, 1820-1903)である。スペンサーは、軍事型、産業型という社会の発展段階を考え、社会進化論を唱えたことで知られる。イギリスは、功利主義の思想が展開された国であり、それと関連して個人主義の思想が展開された国である。この思想は、経済活動について、国家の統制をできるだけ廃して、個人の自由を重視するという自由放任(レッセフェール)の考え方につながり、政治的にも、絶対主義の時代には国王の権力をできるだけ制約し、議会政治が確立してからは議会の権力をできるだけ制約するという自由主義の考え方につながっている。
スペンサーの軍事型社会とは、たんに戦争ばかりしている社会という意味ではなく、軍隊に典型的に見られるような強制的な協力が支配的な構成原理になる社会であり、産業型社会とは、たんに産業革命によって経済が発達した社会という意味ではなく、企業組織に典型的に見られるような自発的な協力が支配的な構成原理になる社会である。19世紀以降の社会発展の方向性を「産業」という言葉で語ったという意味では、コントとスペンサーは似ているように思われるが、その社会構成の原理は正反対といっていいほど対照的である。次の引用は、まさにスペンサーの個人主義的な立場を明らかにしている。図表1にそくしていえば、諸個人が社会システムをつくるという右向きの矢印を強調していると解釈することができる。
‥‥軍事的組織形態の特徴となる観念と感情に変化が生じうるのは、産業的組織形態の発展をもたらす環境があるときに限られる。強制的な協力ではなく自発的な協力によって動かれるので、われわれの知っている産業生活は人々を独立した活動に慣れさせ、他の人々の権利を尊重すると同時に自分自身の権利を実行するように導き、個人権の意識を強め、政府の統制の行きすぎに抵抗するように促す。(Spencer, 1884=2017, 訳pp.417-418)
じっさい、スペンサーは『社会学原理』のなかでコントの思想に触れて、コントは産業国家の到来を期待しながら、構想した社会組織の原理はスペンサーのいう軍事型であり、産業型社会の特徴である個人主義を深く嫌悪している、と批判している。それと同じく、マルクス主義思想にもとづいて成立したドイツの社会主義政党も、主張する産業社会の再組織化の原理がスペンサーのいう軍事型の強制にもとづくものだ、と述べている(Spencer, 1898, Vol. II: 257)。
このスペンサーの考え方を厳しく批判しながら、コントの伝統を継承しつつ、集合主義の立場を強調したのが、フランスの近代社会学の確立者とされるデュルケム(Émile Durkheim, 1858-1917)である。デュルケムは、分業の発達段階によって社会の連帯のあり方が異なることを強調し、機械的連帯と有機的連帯という二つの社会発展の段階を考えた。デュルケムによれば、近代社会は分業が発達した有機的連帯の社会だが、主体的な個人が自由意志にもとづいて分業するという個人主義、功利主義的な見方をとらない。むしろ、次の引用に見られるように、分業によって人間は一個の人格をもつ個人となり、その一方でいっそう密接に社会に依存するようになると述べている。諸個人の相互依存ではなく、社会への依存という見方が重要である。そのかぎりにおいて、図表1にそくしていえば、コントと同じく集合主義的に左向きの矢印を強調しているといえるだろう。
分業が生みだす連帯は、‥‥諸個人がたがいに異なることを前提とする。前者〔機械的連帯〕は、個人的人格が集合的人格に吸収されつくされているかぎりにおいてのみ可能であるが、後者〔有機的連帯〕は、各人が固有の活動領域を、したがって一個の人格をもつかぎりにおいてのみ可能である。だから、集合意識が規制しえない専門諸機能がそこに確立されるためには、集合意識は個人意識の一部分を蔽わぬままに残しておかなければならない。また、この開放部分が広ければ広いほど、この連帯から由来する凝集力は強い。じじつ、一方では、個人は、その労働が分割されればされるほど、いっそう密接に社会に依存し、他方、各人の活動が専門化されるほど、いっそう個人的となる。(Durkheim, 1893=1971, 訳p. 129)
哲学のなかの要素還元論と全体論

以上のような個人主義と集合主義の対立的な見方を、より抽象的なレベルで展開したのが、哲学のなかの要素還元論と全体論という対立的な見方である。個人主義と集合主義の考え方が、人間と社会の関係に限定されているのに対して、要素還元論と全体論(ホーリズム)の考え方は、ある意味で森羅万象に及んでおり、そもそもは自然のあり方をどのように捉えるのかという問題意識から生まれたものだといってよいだろう。ぎゃくにいえば、社会思想のなかの個人主義と集合主義の対立は、要素還元論と全体論の対立の社会現象への適用と見ることもできる。
思想史的には、要素還元論は、要素論、原子論、機械論、還元主義などの一連の考え方の総称といってもよい。これに対して、全体論は有機体論やシステム論と親和性をもつ。全体論の概念上の起源はドイツ・ロマン主義の自然哲学にあり、自然科学において優勢だった機械論に抗して自然の全体的認識をめざしたものである。物理学が要素論を基礎にするのに対して、全体論は生物学によりどころを求めている、とされる(野家、1998)。とはいえ、生物現象にかんする生気論やエンテレヒー概念などが大きな批判を浴びたこともあって、自然科学や自然哲学における全体論はかならずしも盛んではなく、物理学の還元論的な考え方が支配的といってよいだろう。全体論(ホーリズム)という言葉を初めて用いたのは、南アフリカの哲学者スマッツ(Jan Christiaan Smuts, 1870-1950)であるとされる(野家、1998)。スマッツの説明を引用しよう。
全体は単なる機械的なシステムではない。それは確かに部分から成り立っているが、純粋に機械的なシステムの必然的結果としての部分の総和以上のものである。機械的なシステムの本質として、内的なものが欠けており、システムやその部分の内的な傾向や関係、作用が全く欠けている。機械的なシステムにおけるすべての作用は外的なものであり、機械的な物体による他の物体への外的な作用か、あるいは前者に対する後者の外的な作用かのどちらかである。同様に、物体またはシステムの部分を考えると、部分にとって可能な唯一の作用は、一般的には部分相互か、その物体に対する外的な作用である。物体の部分あるいはその諸部分における作用あるいは機能に内的なものではない。機械的な物体とはそのようなものであり、機械的仮説に基づいてそのような物体が存在すると考えられてきた。部分の総和以上のものである全体は内的な何ものかであり、構造と機能が内的性質をもち、何か特別な内的関係や、内的な特性と本質をもち、それが、総和以上のものを作り出している。(Smuts, 1927=2005、訳p.104)
OEDに立ち戻ると、およそどのような経験的実体や経験的現象であれ、「Ⅰ.組織された、あるいは関係づけられた、ものの集合」というのが、システムという言葉のもっとも基本的な意味だった。この組織された、あるいは関係づけられた、ものの集合を、もともとの構成単位としての「もの」に還元して、集合のふるまいや性質を説明できるし、そうすべきであると考えるのが要素還元論であり、ぎゃくに組織されたり関係づけられたりすることによって、「集合」は要素に還元できない固有のふるまいや性質を発揮すると考えるのが全体論(ホーリズム)である。スマッツの文章では、要素還元論的な見方を指す「たんなる機械的なシステム」という表現があり、システムという言葉自体が、かならずしもただちに全体論を意味するわけではない。だが他方で、全体は「部分の総和以上のものである」とも述べられており、ここから全体論的なシステム概念へは、あと一歩である。
ここで、システム理論の話に踏み出す前に、要素還元論と全体論の対立という文脈で、部分と全体という問題についてすこし考えてみよう。スマッツの文章にもあるように、システム理論では、部分である諸要素からなる全体としてのシステムの性質を表現するのに、しばしば「全体は部分の総和以上のものである」といわれる。システムが示す部分の総和以上の性質は、システム理論では創発特性とよばれる。問題は、この「部分の総和以上」の「以上」が何を意味するかである。
この問題について、ネット上でたいへん気になる記事があった。それは、グーグル社が2012年に行ったプロジェクト・アリストテレスという研究の内容とその結果についての紹介である。研究内容そのものはきわめて真っ当であり、組織のなかのチームが効果的に機能するための要因ないし条件を、さまざまな観点から解明しようとするものである。気になったのは研究プロジェクトの名称の由来で、「アリストテレスの言葉『全体は部分の総和に勝る』(Googleの研究者も、「従業員は単独で働くよりもチームで働いた方が大きな成果を上げられる」と考えています)にちなみ、『Project Aristotle』と名付けられたこのプロジェクトの目的は、『効果的なチームを可能とする条件は何か』という問いに対する答えを見つけ出すことです」という説明がついている点である(re:Work)。
この説明を額面どおりに受けとると、あたかもチームで仕事をすれば、かならず個々人で仕事をするよりも生産性あるいは効率が上がる、とも解釈できる。そのように述べている孫引きサイトも散見される。そのような誤解が生まれた原因は、アリストテレスの引用とされる「全体は部分の総和に勝る(the whole is greater than the sum of its parts)」という文章にある。この引用は、英語圏ではある程度ポピュラーなようだが、すでにいくつかのサイトで疑義が示されている。アリストテレスの原典にあたれば、アリストテレスはそのようなことを言っていない、というのである。じっさい、原典のそれらしい部分にあたると、アリストテレスの言い方は異なっている。
しかし、或るものから複合されて、その結果、全体として一つであるような複合体は、すなわち、穀粒の集積のようにではなしに語節がそうであるように結合されたものは、──というのは、語節はたんなる字母どもではなく、βαはβとαとではなく、肉は火と土とではないからである。なぜなら、複合体、たとえば肉または語節は、それぞれの要素に分解されると、もはや〔肉とし語節としては〕存在しないが、字母どもはそのまま存在し、火や土もまたそうだからである。そうだとすれば、たしかに語節は或るなにものかである、すなわちそれはたんに字母ども(ある子音と母音と)であるのではなくて、さらにこれらとは異なる或るなにものかである。(アリストテレス, 訳p.268頁、1041b-b10)
やや古風な訳文だが、要するにアリストテレスは、「全体として一つであるような複合体」は、「穀粒の集積」のようなたんなる部分の総和とは「異なる」なにものかであると言っているのであって、それが部分の総和に「勝る」とはまったく言っていない。その意味で、プロジェクト・アリストテレスというのは、ミスリーディングなネーミングであったといえよう。この「異なる」なにものかがシステムであり、その性質が創発特性である。システム哲学者のラズロー(Ervin Laszlo, 1932- )の次の文章は、あたかも2000年以上の時を超えてアリストテレスの文章を現代風に表現したかのようである。
「全体」と「集積体」は、神秘的な形而上学的概念ではなく、数学的にすら明確に定義できるような、複雑な実在の諸状態です。全体はそれを構成する諸部分の単なる加算的総和でないのに対して、集積体はそれを構成する諸部分のたんなる加算的総和である。(Laszlo, 1972=1980、訳p.40)
異物としてのシステム
社会思想のなかの個人主義と集合主義や、哲学のなかの要素還元論と全体論という対立的な考え方についての検討をとおして、システムをどのように捉えるかについての思想的な文脈がはっきりしてきたのではないかと思う。アリストテレス以来の全体論的な見方が示すように、システムは部分の総和とは異なる何かであると述べたとしても、それじたいは中立的な命題である。しかし、この命題が社会現象にそくして解釈されると、それは中立的とはいえないイメージを生み出す。その中立的でないシステムのイメージを、典型的かつ象徴的に示しているのが、ヴェーバー(Max Weber, 1864-1920)が『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』のなかで展開した、有名な「鉄の檻」の議論である。
‥‥ピュウリタンは天職人たらんと欲した──われわれは天職人たらざるをえない。というのは、禁欲は修道士の小部屋から職業生活のただ中に移されて、世俗内的道徳を支配しはじめるとともに、こんどは、非有機的・機械的生産の技術的・経済的条件に結びつけられた近代的経済秩序の、あの強力な秩序界(コスモス)を作り上げるのに力を貸すことになったからだ。そして、この秩序界は、現在、圧倒的な力をもって、その機構の中に入りこんでくる一切の諸個人──直接経済的営利にたずさわる人々だけではなく──の生活のスタイルを決定しているし、おそらく将来も、化石化した燃料の最後の一片が燃えつきるまで決定しつづけるだろう。バックスターの見解によると、外物についての配慮は、ただ「いつでも脱ぐことのできる薄い外衣」のように聖徒の肩にかけられていなければならなかった。それなのに、運命は不幸にもこの外衣を鋼鉄のように堅い檻としてしまった。禁欲が世俗を改造し、世俗の内部で成果をあげようと試みているうちに、世俗の外物はかつて歴史にその比を見ないほど強力になって、ついには逃れえない力を人間の上に振るうようになってしまったのだ。(Weber, 1920=1989、訳pp.365-366)
ヴェーバー自身はシステムという言葉を使っていないが、「鋼鉄のように硬い檻」というフレーズは、人間をどこまでも強力に拘束する資本主義というイメージを明確に表現している。資本主義は、人間にとって「世俗の外物」として完全な異物となり、人間を疎外し、抑圧するものになってしまったのである。ヴェーバーの黙示録的なペシミズムに満ちた文章とあいまって、鉄の檻は近代社会における人間抑圧的なシステムのイメージの典型となった。
ヴェーバーとはまったく異なる表現様式だが、チャップリンの『モダン・タイムス』(1936年)のなかにも、より具体化された人間抑圧的なシステムが描かれている。映画の冒頭、チャップリン演じる主人公は、工場の生産ラインでベルトコンベアを流れる部品のナットをスパナで締める単純作業をしている。ラインのスピードは一定で速く、工員たちは機械のように一定のリズムで正確な作業をしなければならない。ところが、主人公はしょっちゅう気が逸れて失敗し、何度もラインを止めなければならなくなる。こっぴどく怒られながら作業を再開するのだが、社長の号令一下、ラインのスピードが上がると、しまいにはベルトコンベアに乗って機械に吸い込まれ、図表2の左の映像のように、機械のなかで歯車のナットを締めるありさま。なんとか脱出して作業を再開するが、しだいにその辛さに耐えかねて、トイレで一服しようとすると、図表2の右の映像のように、巨大スクリーンに社長の顔が現れて一喝され、やむなくまた作業に戻らなければならない。とうとう主人公は、ラインを離れてもナットを締める動作が止まらなくなり、あげくに女性の服のボタンをナットと勘違いして、追いかけまわして締めようとする始末。精神を病んで、病院送りになる。

映画のなかでは、こうした一連の場面が、チャップリン独特の身体表現で、コミカルなドタバタ喜劇として展開される。この場面は、機械のラインに人間を組み込んで合理的に設計されているはずのマン・マシン・システムが、システムをはみ出す人間のちょっとしたエラーでたちまち機能不全を起こすと解釈できる。システムを改良するという観点から見れば、いわゆるヒューマン・エラーを減らすためには、人間を機械に合わせて訓練するのが有効である。(もちろん、機械を人間に合わせて改良するという手段も考えられるのだが)。これは、フーコー(Michel Foucault, 1926-1984)が『監獄の誕生』のなかで展開した、近代社会において人間の規律を強化するシステムの具体的な一例といえるだろう。規律を強化するために、人間は空間的に特定のかたちで配置され、時間的に行為を管理され、身体動作まできちんと磨き上げられなければならない(Foucault, 1975=1977、訳pp.147-158)。
ところが、システム設計の合理性と人間の本性はかならずしも一致しない。むしろ人間の本性は、かならずシステムをはみ出すといっていいだろう。だからこそ、システムの合理化を進めようとすればするほど、人間の規律の強化が必要になる。『モダン・タイムス』では、きわめて具体的な工場の生産ラインを舞台に、この鉄の檻のなかでの規律の問題が喜劇的に描かれているが、精神を病んでしまう主人公の人生は、現実世界で考えれば深刻な悲劇であり、笑って済まされる問題ではない。21世紀の現代では、工場はロボット化が進み、人間がチャップリンのような状況に追い込まれることは少なくなってきているが、生産システムの効率を高めるための合理化という方向性に変わりはない。
もう一つ、主人公がトイレで巨大スクリーンに現れた社長に一喝される場面は、のちにオーウェル(George Orwell, 1903-1950)の小説『1984年』(Orwell, 1949=1972)で描かれた、監視のためのテレスクリーンを彷彿とさせる。この小説は、資本主義ではなく社会主義の旧ソビエト連邦をモデルにして、スターリンによる全体主義的な独裁体制を批判したディストピア小説とされている。映画化されてテレスクリーンが現れる場面の一つでは、主人公がテレスクリーンの死角でこっそりと日記を書いているのだが、『モダン・タイムス』のような明るい喜劇とは対照的に、あくまで暗く深刻なトーンで描かれている(図表3)。

これまたフーコーの『監獄の誕生』に引きつけていえば、ベンサムが考案した監獄の監視のためのパノプティコン(一望監視施設)の現代版だと考えられる。もともとの監獄の場合には、パノプティコンは、閉じた空間のなかで囚人をそれぞれ隔離された独房に入れて円形に配置し、中央の監視塔から一望で全体を監視できるようにした施設であり、監視塔からはすべての囚人が見えるが、囚人からは看守の姿は見えず、監視の視線だけがつねに感じられるようになっている。パノプティコンは、権力を可視化すると同時に没個人化するというかたちで、巧妙な監視システムとなっている(Foucault, 1975=1977、訳pp.202-204)。21世紀の現代では、『1984年』のテレスクリーンを超えて、街中のいたるところに監視カメラが設置され、使い方次第では市民のあらゆる行動を監視することが可能になりつつある。ある意味では、社会全体が、監視カメラのネットワークによって、パノプティコンのように監視される監獄となってしまうというディストピアの実現である。
このように、人間にとっての異物としてのシステムは、一方では資本主義のシステムとして、他方では社会主義のシステムとして、しばしば規律による労働強化と監視を進める社会をイメージさせるように描かれる。現代社会のシステムは、もともと人間がつくり出したものかもしれないが、結果的に人間を抑圧するものになっている、というわけである。さらにそこでは、資本家も権力者もしだいに姿が見えなくなり、だれか具体的な個人が人びとを支配し、管理するのではなく、まさにシステムそのものが異物として人間を支配し、管理するように感じられるようになる。
このような異物としてのシステムによる人間支配のイメージこそ、社会システム理論に対する批判の背景となっている。科学的に理論を考える方法論として集合主義や全体論をもちだしても、それじたいが人間の主体性や自由を抑圧する思考法だと批判される。個人主義の観点から、人間の主体的な行動によって社会システムが創発すると考えることが正しく、個人の行動という要素に還元して社会システムを理解することができる、というわけである。このような考え方では、個人の存在とその主体性や自由が、事実的というより規範的に前提とされている。だから、社会システム理論は人間を抑圧するシステムを正当化する理論だ、とさえ言われるのである。
あとでルーマン理論の解説のなかで触れることになるハーバーマス=ルーマン論争において、ハーバーマスの側からの批判の背景にあるのも、このようなシステムのイメージである。ハーバーマスの議論には、もう一つ、これもヴェーバーに端を発する、システムにおける(誤った)合理化の進展という重要な論点があるが、それもふくめてのちの議論にゆだねることにしよう。
参考文献
アリストテレス、『形而上学』(出隆訳「形而上学」『アリストテレス全集12』岩波書店、1968年).
Comte, Auguste, 1926, Discours sur l’esprit positif, Calssiques Garnier, Paris, Garnier Frère,(霧生和夫訳「実証精神論」清水幾太郎監修、霧生和夫・清水礼子訳『世界の名著46 コント・スペンサー』中央公論新社、1980年:141-233).
Durkheim, Émile, 1893, De la division du travail social, Paris, Félix Alcan.(田原音和訳『社会分業論』(現代社会学大系2)青木書店、1971年).
今村仁司、1998、「社会主義」『岩波哲学・思想事典』岩波書店:691-693.
Erving Laszlo, 1972, The Systems View of the World: The Natural Philosophy of the New Development in the Sciences, George Brazillier, INC(伊藤重行訳『システム哲学入門』紀伊國屋書店、1980年).
Foucault, Michel, 1975, Surveiller du punir: naissance de la prison, Paris, Gallimard(田村俶訳『監獄の誕生─監視と処罰』新潮社、1977年) 野家啓一、1998、「ホーリズム」『岩波哲学・思想事典』岩波書店:1501.
Orwell, George, 1949, 1984: A Novel, New American Library(新庄哲夫訳『1984年』ハヤカワ文庫、1972年).
Oxford English Dictionary, ‘system’, https://www.oed.com(2023年1月8日アクセス).
re:Work、「『効果的なチームとは何か』を知る」、https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/#define-team(2022年12月7日アクセス).
Smuts, Jan Christiaan, 1927, Holism and Evolution, 2nd Edition, Macmillan and Co(石川光男・片岡洋二・高橋史朗訳『ホーリズムと進化』玉川大学出版部、2005年).
Spencer, Herbert, 1884, The Man versus the State, D. Appleton(森村進訳『ハーバート・スペンサー・コレクション』ちくま学芸文庫、2017年:247-426).
Spencer, Herbert, 1898, The Principles of Sociology, 3 vol., D. Appleton.
Weber, Max, 1920, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie 1, Tübingen, J.C.B. Mohr: 17-206(大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、1989年).